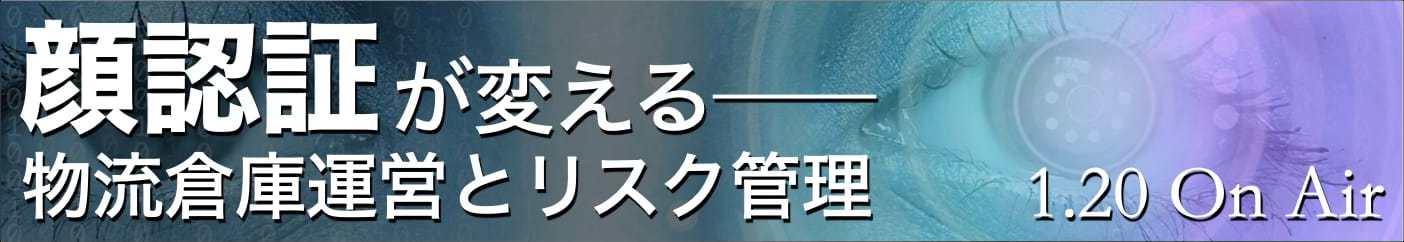ロジスティクス総合トラック(千葉県浦安市)が展開する「メタル便」は、大手運送会社が扱わない特殊な鋼材や長尺物の輸送に特化した全国ネットワークサービス。共同配送のコンセプトで、メタル便を2000年にスタートして、15年までは東名阪で個別にメタル便サービスを展開。地域ごとのパートナー企業と連携し、一般の路線便では対応できない特殊鋼材を全国各地へ効率的に輸送している。

▲総合トラックの梶大吉社長
「我々の強みは全国に発送できること」と語るのは、総合トラックの梶大吉社長。同社の拠点がある浦安の鉄鋼団地を起点に、全国各地のパートナー企業と連携し、特殊な形状や重量の鋼材を日本全国へ届けるネットワークを構築している。
特殊な鋼材を低コストで輸送できることから引き合いも多く、売り上げは毎年10-15%成長。ネット通販の急拡大で、大手が輸送効率と採算重視で長尺や重量物を断り始め、平ボディーやウイング車からハコ車にシフトしていったが、「それを見て、メタル便の全国提携を意識的に展開した」という梶氏の狙いがうまくはまった形だ。関東から九州北部までのいわゆる「太平洋ベルト地帯」での輸送では、必ず帰り荷があり、無駄のない運行が行われる。浦安の社屋には20台ほどの平ボディートラックがあり、朝は10-15分おきにトラックが荷さばき場に入って、積み付けが終わり次第出発していく。
オフィスでは10人の配車スタッフが次々に入る注文をさばいて、配車表を作り上げる。早朝から猛烈な勢いでトラックが稼働しているにもかかわらずどの車両もピカピカだ。それについて梶氏に聞くと、むしろ「トラックが常に稼働しているので、整備をしている暇が無い」のだという。車両がどれもきれいなのは、「修理代が高くなる導入6-7年目まで使わず、どの車両も5-6年で更新している」からなのだ。

車両は整備コストが高くなる前に更新。車両には導入年度が記されており、画像の車両の「2202」は「22年に導入された2号車」を意味する
 独自の中継方式で物流コストを大幅削減
独自の中継方式で物流コストを大幅削減
メタル便の最大の特徴は、複数の運送会社による中継輸送方式だ。例えば、関東から鹿児島まで5メートルの長尺物を輸送する場合、一般的な運送会社では専用のトラックをチャーターする必要があり、往復の高速料金や日数を含めると、20万-35万円のコストがかかるのが相場だ。しかし、メタル便では複数の拠点を経由する「リレー方式」を採用することで、2-3万円まで輸送コストを抑えることに成功している。
例えば熊谷から鹿児島への荷物は、まず熊谷から浦安に運び、浦安から大阪への定期便に乗せ、大阪から福岡、熊本、鹿児島という具合に中継していく。梶社長によると「各区間の中継を受け持つ各協力会社が運賃を申請し、それを合算するボトムアップ方式で価格が決まる」という。各社が混載で行う「リレー方式」によって大幅なコスト削減を実現している。
 「暖簾分け」モデルで全国に広がるネットワーク
「暖簾分け」モデルで全国に広がるネットワーク
興味深いのは、メタル便の拡大方法だ。フランチャイズとは異なり、「のれん分け」のような形で各地域にメタル便のブランドを広げている。東京、大阪、名古屋の「メタル便」はそれぞれ独立した会社であり、本部からの売上保証要求などは一切ない。

▲同社の配車室。10人の配車係が全国への配送の手配を行う
「最初からメタル便だけで利益を上げるのは難しい。でもお客さんのためには手を組んだ方がいい」との考えから、各地のパートナー企業にブランド名を無償で貸与し、ノウハウも提供している。現在、東京・大阪・名古屋のほか、金沢、新潟、山口、岡山(中国・四国地区)、熊本(九州地区)などに拠点があり、日本全国をカバーしている。
東京、大阪、名古屋の3大都市圏ではメタル便専業の会社が運営している一方、そのほかの地域では既存の運送会社がサブブランドとしてメタル便を運営するケースが多い。しかし、参入後は「劇的に成長する」と担当者は語る。例えば、岡山の赤田運送は、メタル便に参加してから5年間で倉庫スペースを5-6倍に拡大し、売上も大幅に伸ばしたという。
 ニッチな市場で確固たる地位を築く
ニッチな市場で確固たる地位を築く
メタル便が扱う代表的な貨物の一つにガードレールがある。日本国内のガードレールメーカーは実質的に2社のみで、新設時は大量輸送されるが、部分的な交換となると1本単位の輸送が必要となる。こうした長尺物の少量輸送は大手運送会社では割に合わないため、メタル便の独壇場となっている。
こうしたニッチな市場に特化することで、メタル便は着実に事業を拡大してきた。全国各地のパートナー企業との連携により、「ピッチャー」(荷物を送り出す地域)と「キャッチャー」(荷物を受け取る地域)のバランスを取りながら、効率的な物流ネットワークを構築している。
 課題は東北地方のネットワーク
課題は東北地方のネットワーク
現在の課題としては、東北6県へのサービス拡大が挙げられる。人口密度が低く面積が広い東北地方は「完全にキャッチャー」の立場になるため、採算性の問題からまだ拠点が設置されていない。梶氏は「ほかの地域では帰り便にも荷物があるけれど、東北、特に日本海側は帰り荷が無い」ため、地域格差の課題に頭を悩ませているようだ。
また、例えば中国・四国地区では業務量が大きく増加し、新規のパートナーが必要な状態。しかし、これまで貢献してきたパートナー企業の「縄張り」を尊重するため、新規参入は慎重に進めざるを得ない。そのため、既存パートナーの下に新たな協力会社を配置する取り組みを行っている。
メタル便は、大手運送会社が手掛けない特殊貨物輸送の分野で独自のビジネスモデルを確立し、各地域のパートナー企業と共に成長を続けている。鋼材輸送という専門分野で培ったノウハウと全国ネットワークは、日本の物流業界における新たな可能性を示している。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com