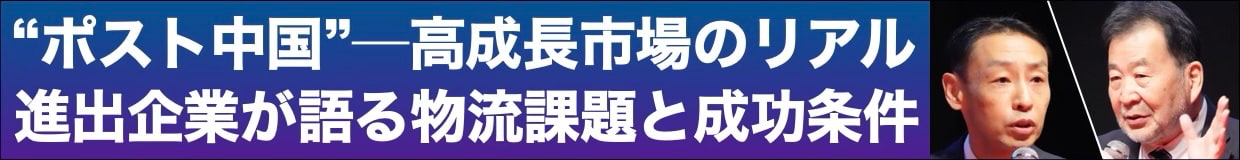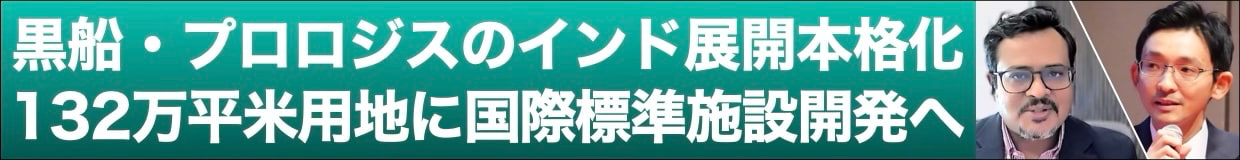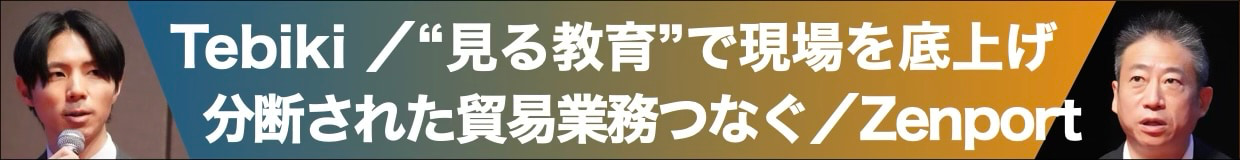話題名目GDPで日本を抜いて世界第4位となったインド。14億人を超える人口と若年層中心の労働力、急速に拡大する中間所得層を背景に、製造・貿易・デジタル分野が一気に成長を遂げている。また、米中貿易摩擦やサプライチェーンの分散化が進む世界経済の変化を受けて、日本企業にとってインドは「次の軸」として存在感を高めている。
こうした情勢を背景に、LOGISTICS TODAYは23日、駐日インド大使館と共催で「日印物流パートナーシップの新時代/India–Japan Next Generation Partnership with Focus on Logistics」と題してイベントを開催。ここではその概要を紹介する。
——————————————————————————
申込は締め切りました
アーカイブ視聴 申込はこちら
——————————————————————————
イベントの会場となったのは東京都千代田区のインド大使館。事前の申し込みは100人を超え、物流・製造・商社関係の企業やコンサルティング関係者などが集まり、インドの物流インフラ整備と日系企業の展開戦略を巡る意見交換が行われた。モデレーターはLOGISTICS TODAYの赤澤裕介社長兼編集長と鶴岡昇平が務めた。
 向上するインドの物流パフォーマンス
向上するインドの物流パフォーマンス
開会挨拶に立った駐日インド大使館のデブジャニ・チャクラバルティ公使(経済・商務担当)は、「物流は単にモノを運ぶだけではなく、経済を動かす基盤である」と強調。モディ政権下で推進されている「PMガティ・シャクティ国家物流計画」や「国家物流政策」について紹介し、複数省庁・州政府を跨いだGISデータ統合および物流データバンク整備により、コンテナ輸送のリードタイムが平均2.6日まで短縮された成果に言及した。2023年のロジスティクス・パフォーマンス指数(LPI)では世界38位まで改善しているという。2047年の先進国入りを目指し、インドと日本のさらなる連携深化を期待しているとアピールした。

▲駐日インド大使館のデブジャニ・チャクラバルティ公使(経済・商務担当)
 野村総研、インド物流の現状をビデオ登壇で分析
野村総研、インド物流の現状をビデオ登壇で分析
続いて、野村総合研究所インド法人のグローバル・ナレッジ・センター梶河智史副センター長がビデオ登壇し、「インド物流の最新動向」と題して講演した。梶河氏は、同国が25年に日本を抜き世界第4位のGDP規模になる可能性があること、若年層主体の人口構成が今後の成長を下支えしていることを紹介。一方で、「物流インフラや通関の効率性にはまだ大きな改善余地がある」と指摘した。
道路網の拡充は進む一方、鉄道・港湾分野では地域差が大きく、サービス品質の平準化が課題という。ただし、政府主導による高速道路延伸や主要空港の整備、民間投資による物流施設の増加も目立っている。
 商船三井ロジ・現地駐在員が語る「いまのインド」
商船三井ロジ・現地駐在員が語る「いまのインド」
商船三井ロジスティクスのインド法人MOLロジスティクス・インディアセールスチームの広瀬裕一デュプティ・ゼネラル・マネージャーがビデオメッセージで登壇。インド政府が推進する品質認証制度「BIS(インド規格)」への対応が日系企業にとって重要課題になっていると説明した。また、中古設備の輸入規制強化を背景に、船積み前検査証明書(CEC)の取得や包装仕様の厳格化が求められており、「輸入プロセスにおける実務上の難易度は年々上昇している」と語った。
 インフラ整備が進むインドにいち早く進出し、先行者利益を
インフラ整備が進むインドにいち早く進出し、先行者利益を
モデレーターを務めたLOGISTICS TODAYの赤澤裕介編集長は、「日本の物流再構築には海外との連携が不可欠。特にインド・アフリカを抜きにしたグローバル戦略はありえない」と述べ、政府主導のインフラ投資が加速している現段階で進出することが「先行者利益を得る好機だ」と指摘した。

▲(左から)モデレーターを務めたLOGISTICS TODAYの鶴岡昇平、赤澤裕介社長兼編集長
——————————————————————————
申込は締め切りました
アーカイブ視聴 申込はこちら
——————————————————————————
 パネルで語る「人材・文化・連携の鍵」
パネルで語る「人材・文化・連携の鍵」
後半のパネルディスカッションには、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズIoT&デジタルエンジニアリング統括本部ディレクターの藤永和也氏、安田倉庫執行役員国際業務部長の日比野洋之氏、プロロジス開発部物流コンサルティングチームディレクターの本庄哲太氏の3人が登壇した。

▲(左から)日本タタ・コンサルタンシー・サービシズIoT&デジタルエンジニアリング統括本部ディレクターの藤永和也氏、安田倉庫執行役員国際業務部長の日比野洋之氏、プロロジス開発部物流コンサルティングチームディレクターの本庄哲太氏
藤永氏は「日本が経済的に成長を続けるにはインドとの連携が欠かせない」と述べ、40年にわたる経験を踏まえ「州ごとの制度差、宗教・言語・文化の多様性を理解することが成功の鍵」と強調。さらに「インドは世界的なIT拠点であり、日本のフィジカル(物流)力とインドのデジタル技術を融合させれば“サイバー×フィジカルロジスティクス”という新たな競争力を生み出せる」と提案した。
日比野氏は、安田倉庫が23年にシンガポール企業をM&Aし、インド11拠点を取得した経緯を紹介。「中国中心の貿易構造がインドへシフトしつつある。今後はインド企業の日本進出も支援していきたい」と語った。現地では「信頼できる人材確保とエンゲージメントの向上が成功の鍵」とした。

本庄氏は「日本の“2024年問題”を契機に生まれた共同輸送やDX(デジタルトランスフォーメーション)のノウハウは、やがて海外でも求められる」と述べ、「日本発の物流改革モデルをインド市場で実装する可能性が高い」と展望を語った。
プロロジスでは23年からインドでの事業を本格化し、ムンバイ、バンガロール、デリー、チェンナイ、プネーの5都市で133万平方メートルの開発用地を確保。バンガロール郊外のホスコテやプネーなど複数拠点で建設が進む。インドでは依然として「グレードA」物流施設の供給が少なく、同社は自己資金による長期運用型の開発を進め、質の高い施設を提供することで多国籍企業の需要に応えていくという。
——————————————————————————
申込は締め切りました
アーカイブ視聴 申込はこちら
——————————————————————————
 Zenport・Tebiki、テック企業が示す新たな視点
Zenport・Tebiki、テック企業が示す新たな視点
貿易管理プラットフォームを展開するZenport(ゼンポート、東京都千代田区)の太田文行社長は、「グローバルのサプライチェーンを見ると、まだ多くの構造が整っていない。データ連携を軸に貿易実務を効率化し、国境をまたぐ物流をシームレスにすることで、日印双方の取引がよりスムーズになる」と語った。
また、「インド市場は潜在的な成長力が非常に大きい。日本企業にとっても、現地とデジタルでつながる仕組みづくりがこれからの鍵になる」と述べた。

▲Zenport代表取締役の太田文行氏
クラウド動画教育サービスを提供するTebiki(テビキ、新宿区)海外事業部の檜山達矢マネージャーは、動画マニュアルを活用した現場教育支援の仕組みを紹介。「現場の作業を映像化し、AI(人工知能)を活用して多言語で字幕や音声を生成できるのがTebikiの強み。現在はおよそ400言語に対応しており、海外拠点でも同一品質の教育を可能にしている」と説明した。
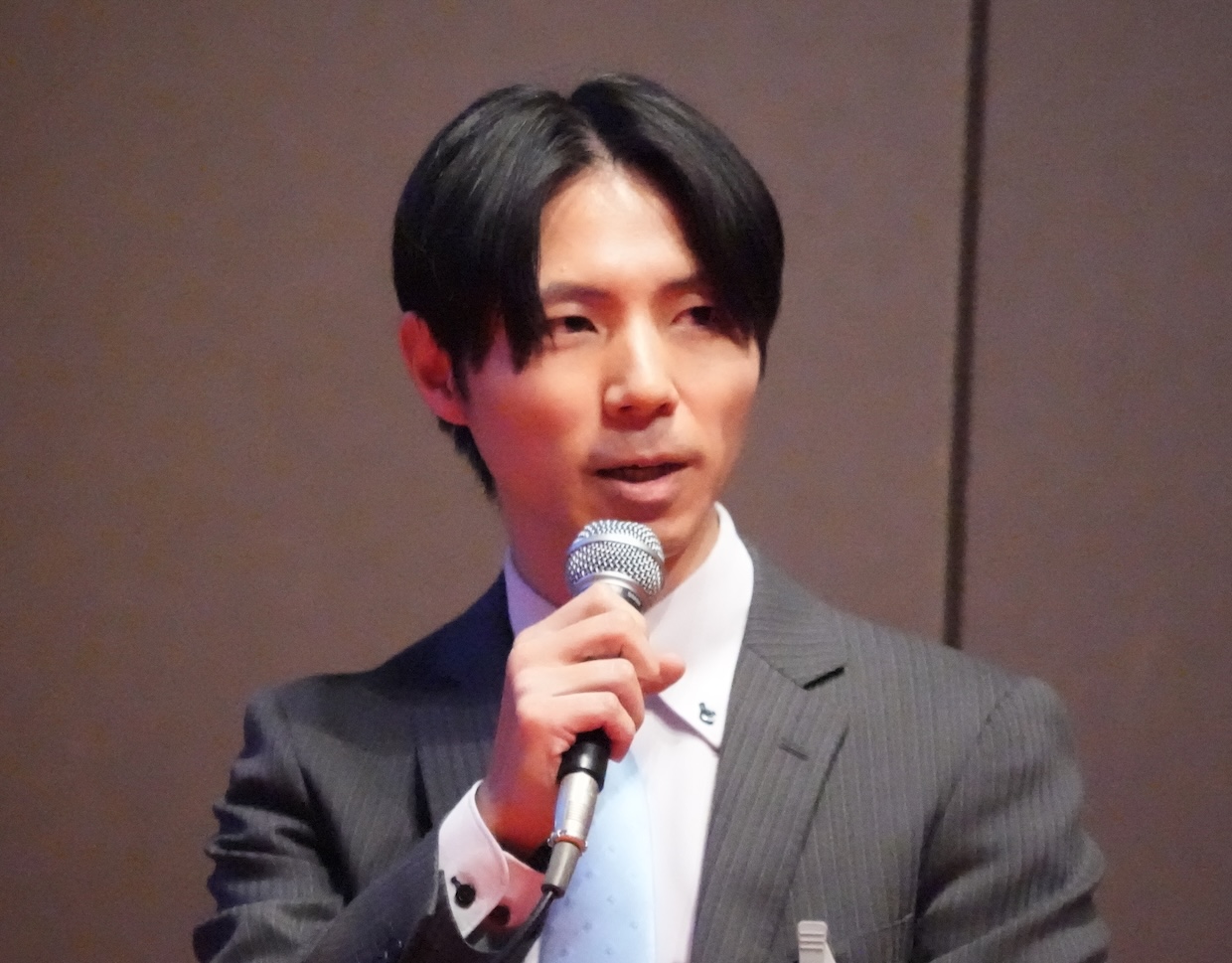
▲Tebiki海外事業部の檜山達矢マネージャー
インド市場についても「多様な言語・文化を持つ国こそ、動画によるマニュアル化の効果が大きい」と強調。赤澤編集長は「インド進出を考える企業にとって、こうした映像教育ツールは“マスト”になっていく。現地とのコミュニケーションギャップを埋める重要な手段だ」とコメントした。
 「人づくり」が持続的発展の礎
「人づくり」が持続的発展の礎
登壇者の議論を踏まえ、赤澤編集長は「インドはITの力、日本は現場力。両国が補完し合うことで新たな物流エコシステムを構築できる」と総括。藤永氏も「インドで成功した日系企業は例外なく“人づくり”から始まっている」とし、教育・技能育成・相互理解の重要性を強調した。
パネルディスカッション終了後は大使館内で交流会が開かれ、大使館からは特製のチャイが振る舞われた。参加者同士の意見交換も続き、会場は終始温かな熱気に包まれた。
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。