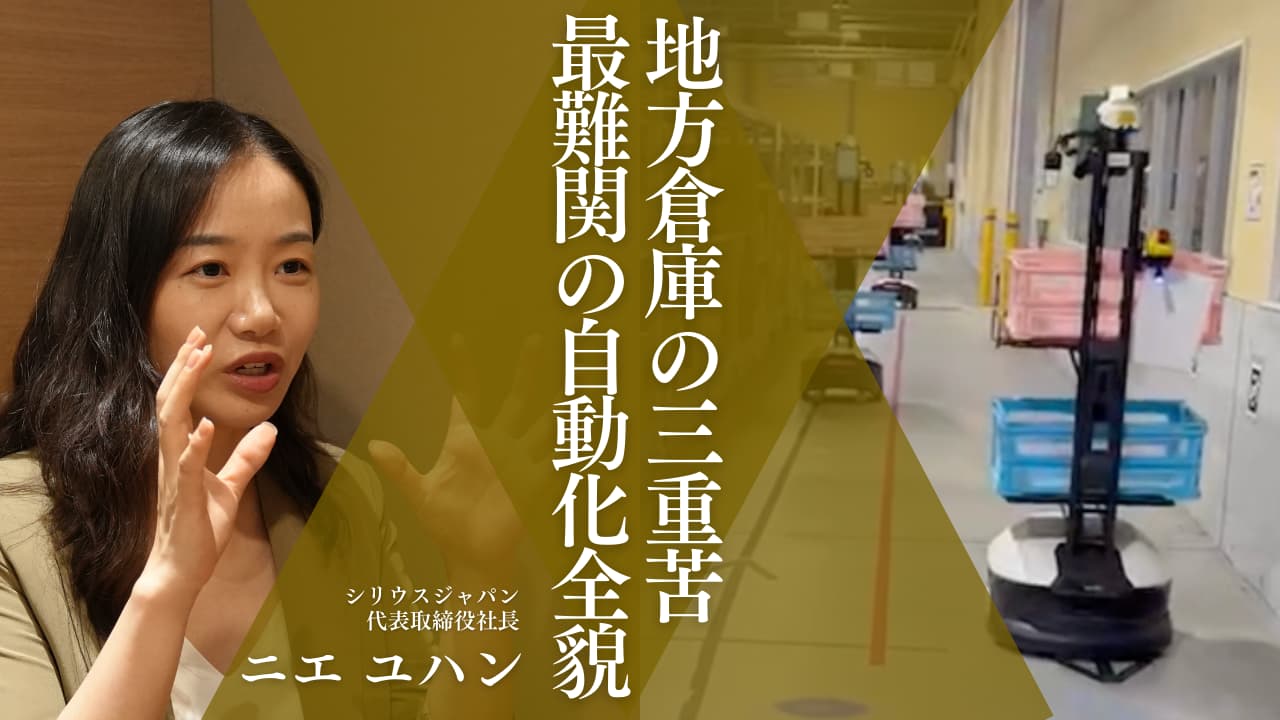
ロジスティクス「ピッキング現場1000平米、通常作業者60人、生産性要求は毎日4万ピース」。地方の製品雑貨メーカーが提示したこの条件に、多くのロボットメーカーが「自動化提案は不可能」と匙を投げた。深刻な人手不足、高密度なオペレーション、そして高い生産性要求という三重苦。日本の多くの地方企業が抱えるこの根深い課題に、自律走行型搬送ロボット(AMR)メーカー、シリウスジャパンは真正面から向き合った。
「これは手術。成功するまでコストは請求しない」。シリウスジャパンのニエ・ユハン(グレース)社長(以下、グレース社長)がそう語る、常識破りの挑戦。これは、単なるロボット導入事例ではない。絶望的な現場を救うために、顧客と共に未来を創り上げた、壮絶なプロジェクトの全貌だ。
 絶望的な現場、台車がひしめく1000平米の格闘
絶望的な現場、台車がひしめく1000平米の格闘
四国地方に拠点を置く、ある製品雑貨メーカー。100円ショップなどに商品を供給するこの企業の物流現場では、毎朝、時間との戦いが繰り広げられていた。前日の夜までに受注した4万ピースもの膨大なオーダー。それを、全国数百店舗分に仕分け、その日の夕方までに出荷を完了させなければならない。朝礼を終えた9時半、作業開始の合図と共にピッキングエリアが一斉に活気づく。作業の中心を担うのは、近隣に住む主婦層のスタッフたちだ。彼女たちの多くは、家庭と両立しながら長年この現場を支えてきたベテランだが、残業が難しく、17時半という限られた時間の中で、その日の目標を達成する必要があった。
AMR導入以前、その光景はまさしく人海戦術による格闘そのものだった。一人ひとりの作業員が、大きなピッキング用の段ボールを載せた台車を押す。手元の紙の出荷伝票と、棚に並ぶ数百種類もの商品を何度も見比べながら、倉庫を歩き回る。
「従来のオペレーションでは、重たい商品を何度も持ち上げ、腰をかがめて台車に載せる。この繰り返しは、特に女性や高齢のスタッフにとっては大きな身体的負担でした」と、シリウスジャパンのグレース社長は当時の状況を説明する。このオペレーションを維持するためには、平常時でも60人、年に2〜3回やってくる繁忙期には90人もの作業者が必要だった。だが、地方の深刻な採用難が、その人海戦術の限界を突きつけていた。
「派遣会社にお願いしても、もう人が集まらない」
仮に人を集められたとしても、90人もの作業者と台車が1000平米という限られた空間で行き交えば、通路は渋滞し、人と台車がぶつかり合う。かえって生産性は低下し、出荷の遅れという形で経営を圧迫していた。高密度、高生産性、そして地方の採用難という「三重苦」。この絶望的な状況を打破すべく、同社は自動化の検討を開始。しかし、この厳しい条件を聞いたあるロボットメーカーは、早々に「提案は不可能」と匙を投げたという。
 「手術の成功が最優先」――シリウスの常識外れの覚悟
「手術の成功が最優先」――シリウスの常識外れの覚悟
他社が去った後、2022年9月の国際物流総合展で、このメーカーの担当者はシリウスジャパンのブースを訪れる。これが、挑戦の始まりだった。「お互いに動きは非常に早かったですね。9月に出会って、11月にはもう10台のロボットを200平米のエリアで動かす実証実験を始めていました」とグレース社長は振り返る。
しかし、シリウスジャパンの提案は、常識を逸脱していた。小規模な実証実験の成功を受け、シリウスジャパンは「部分的な検証では意味がない」と判断した。
「台車とロボットが混在する環境は、どちらにとっても邪魔になり、最も効率が悪い。やるなら、現場のオペレーションを全てAMRに置き換えるしかない」(グレース社長)

▲シリウスジャパンのグレース社長
そう決断したシリウスジャパンは、23年2月、まだ契約も不透明な段階で、60台ものAMRを顧客の現場へ送り込むことを提案する。フルスケールでの実証実験だ。失敗すれば、すぐに人手でのオペレーションに戻さねばならず、顧客にとっても大きなリスクを伴う。
「これは『手術』のようなもの。成功するかどうかは、やってみなければわからない。だから、目標である日産4万ピースを達成できるまで、私たちにコストを請求しない、という覚悟で臨みました」(グレース社長)
この“異常”とも言える覚悟とコミットメントが、顧客の心を動かした。こうして、他社が匙を投げた最難関プロジェクトの幕が上がったのである。
 四国地方に降り立った「ゴースト」とアルゴリズムチーム
四国地方に降り立った「ゴースト」とアルゴリズムチーム
フルスケールでの実証実験は、壮絶を極めた。特に、顧客の協力で拡張された1500平米のスペースに60台のAMRを高密度で稼働させ、かつ高い生産性を維持するための「交通ルール(走行パターン)」の確立は、前例のない挑戦だった。
「通常の交通ルール、例えば単にAMRの渋滞を避けるだけでは、この現場の要求は満たせません。目標生産性を達成するための、全く新しい走行パターンを現地で開発する必要がありました」。
そのためにシリウスジャパンは、中国本社からトップレベルのアルゴリズムチームを現地に派遣した。その中には、シリウスの創業メンバーの一人も含まれていた。彼らは4か月もの間、現場に滞在。顧客の業務が終わる18時から現場に入り、夜通し開発とテストを繰り返すという、昼夜逆転の生活を送った。

▲深夜に行われたオペレーション実証(ゴーストモード)の様子
当初、テストには派遣スタッフを雇っていたが、コストも時間もかさむ。そこで開発されたのが「ゴーストモード」だ。これは、人が介在せずとも、AMRがピッキング作業をシミュレーションする機能。深夜、静まり返った倉庫の中で、60台のロボットだけが自動で動き、停止し、カウントダウンを終えると再び走り出す。その光景は、まさにゴースト(幽霊)のようだったという。
この生々しい現場での試行錯誤の末に、「縦列で待機し、順番に自動で列から出ていく」といった、高密度環境下での輻輳(ふくそう)を解消する独自の機能が生まれた。現在のシリウスジャパンが提供する高度なシミュレーションソフトは、こうした机上の空論ではない、日本の現場で血と汗の滲むようなテストを経て生まれた知見の結晶なのである。
■「ゴーストモード」によるオペレーション実証の様子
 数字が語る「本当のAMRの使い方」と現場の変化
数字が語る「本当のAMRの使い方」と現場の変化
23年8月、ついに本格稼働が始まった。その成果は、目覚ましいものだった。
「本格稼働からわずか3ヶ月後には、作業者30人とAMR60台の体制で、1日の最高生産性が5万ピースに到達しました」。
これは、従来の60人体制での目標値4万ピースを、半分の人員で25%も上回る驚異的な数字だ。作業者一人当たりの生産性に換算すると、1時間あたり約95ピースだったものが約238ピースへと、実に2.5倍に向上したことを意味する。だが、この導入がもたらしたのは、数字上の成果だけではない。長年現場を支えてきた作業員たちの働き方と意識にも、大きな変化が生まれた。

一つは、徹底した「属人性の排除」。AMRの操作は極めてシンプルで、UI(画面)の文字も大きく分かりやすい。そのため、普段はピッキングを行わないオフィスのスタッフでも、繁忙期にはすぐにヘルプに入ることができる。「誰でも即戦力になれる」環境が、ピーク時の波動吸収を容易にした。
もう一つは、「身体的負担の劇的な軽減」だ。あの重たい台車を押して倉庫内を歩き回る作業は、過去のものとなった。作業者は自分の持ち場(ゾーン)で、次々とやってくるロボットに対応するだけ。ベテランスタッフの中には50歳を超える方もいるが、ハンディターミナルの小さな文字に目を凝らす必要もなくなり、「圧倒的に楽になった」と好評を得ているという。
そして最も象徴的なのが、スタッフの「ロボットへの愛着」だ。「最初は、大きなロボットが動く様子を怖がっていたスタッフもいました。しかし、安全性を理解し、使い慣れていくうちに、今では自分の仕事のパートナーとして、とても大切に扱ってくれています。一日の終わりに、ロボットたちが待機場所へ寸分の狂いもなく綺麗に整列している様子は、まさにその証拠です」(グレース社長)。

 未来を共に創るパートナー
未来を共に創るパートナー
この事例は、なぜシリウスジャパンにとって「最も象徴的」(グレース社長)なのだろうか。それは、単に製品の性能が優れていたからだけではない。他社が「不可能」と判断した課題に対し、顧客以上の覚悟でリスクを取り、現場に深く入り込み、文字通り「やりきる」姿勢で未来を共に創り上げたからだ。顧客が1年半のリース期間を経てAMRを買い切りに移行し、さらに別のピッキングエリアへ20台を追加導入したという事実が、その信頼の厚さを物語っている。
「地方の深刻な人手不足」。「限られたスペースでの高効率オペレーション」。これは、日本中の多くの企業が抱える、待ったなしの課題だ。シリウスジャパンの挑戦は、AMRがもはや単なる自動化ツールではなく、企業の存続すら左右する経営課題に対する、強力なソリューションであることを証明した。彼らは、ロボットを売るだけのメーカーではない。顧客の絶望に寄り添い、不可能を可能にするまで諦めない。シリウスジャパンは、そんな未来を共に創るパートナーなのである。





















