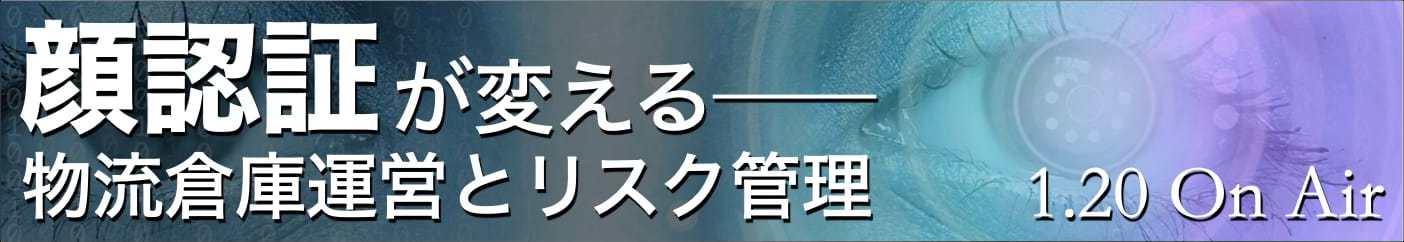ロジスティクスかつては、荷役がないことなどから、ドライバーに人気が高かった海上コンテナ輸送。荷役がないのは今も同じだが、運賃の値上げがなかなか進んでいないほかにも多くの課題があり、以前ほどドライバーが集まりにくくなっている。海上コンテナ輸送を巡る状況を、国際コンテナ輸送(東京都品川区)に取材した。
同社は商船三井のハウストラッカーとして1968年に創業。海上コンテナ輸送専門の運送事業者として全国各港にも拠点を展開する。京浜地区ではおよそ400本のシャーシを保有し、自社と協力会社を合わせて毎日100台規模のトラクターを稼働させ、1日あたり150本のコンテナを輸送している。

▲国際コンテナ輸送・矢上隆弘京浜支店長
同社が最大の課題として挙げるのが、東京港を中心としたヤードでの長時間待機だ。矢上隆弘京浜支店長は「東京港の長時間待機が常態化している上に、先日は青海のターミナルでシステム障害が発生。10時間を超える荷待ちも発生している。当社やほかのコンテナ輸送会社では、システムが回復するまで青海ターミナルの搬出入は断らざるを得ない状況にある」と語る。
長時間待機は拘束時間規制の強化と直結する。2024年問題によってドライバーの労働時間管理が厳格化されるなか、待機が常態化している現状は業務継続の大きなリスクとなっている。
かつて海上コンテナ輸送は「配達先での荷役作業がなく、稼げる仕事」として人気があった。しかし残業規制により時間外労働が制限され、収入は減少。ドライバーの流出が続いている。若年層の参入も進まず、同氏は「免許取得に100万円近い費用がかかる。稼げないので若い人は入ってこない」と語る。結果として平均年齢は50歳を超え、世代交代は停滞している。
会社によっては2トンから4トン、さらにけん引免許も取得してコンテナ車へとドライバーのキャリアパスを描いているケースもあるが、「最近の若手は、コンテナは運びたがらない」と矢上氏。「コンテナのターミナルからの搬出に時間がかかり、帰りはコンテナの搬入でまた待たされる。荷物を運ぶ以外の時間が多すぎて稼げないからと、コンテナのドライバーの新たななり手が入ってこない」のだという。
さらに免許制度のハードルも課題である。大型車両の経験がなければけん引免許は取得できず、実務に就くまでに時間がかかる。ドライバー不足は単なる人材確保の問題にとどまらず、輸送力そのものの縮小につながりかねない状況にある。
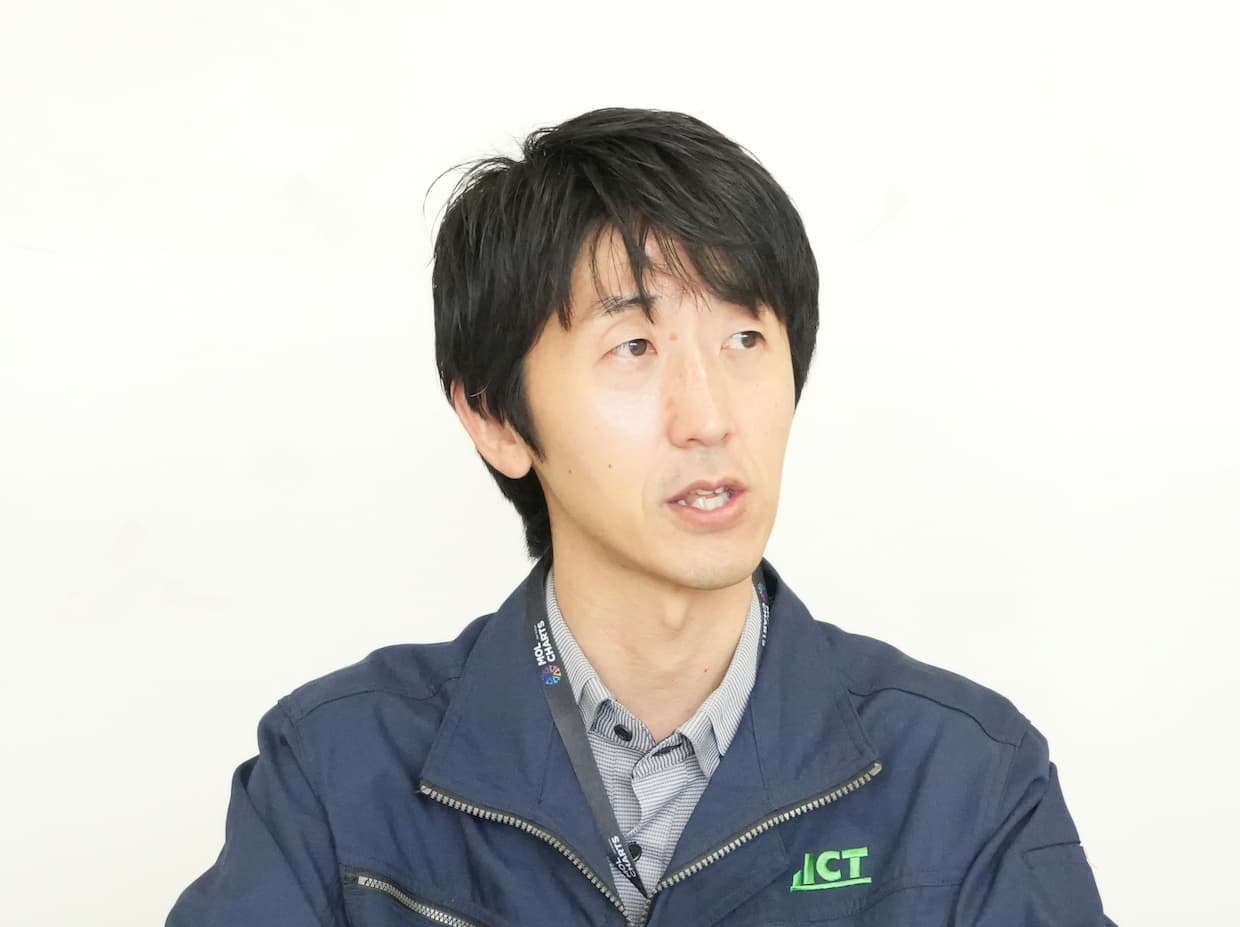
▲同社企画部兼管理部、匂坂優希グループリーダー
同社の依頼主は真荷主ではなく主にフォワーダーや通関業者、あるいは「乙仲」と呼ばれる海運貨物取扱業者である。この多重下請け構造が運賃交渉を難しくしている。燃料費や車両費、整備費の上昇、さらには待機料や高速道路料金の負担を運賃に反映させるのは容易ではない。法改正で実運送体制管理簿の作成義務化など、多重下請け構造の是正が制度化されたが、それはあくまでもトラック運送事業者の間での話。コンテナ輸送業者と荷主の間にいくつも介在する事業者には強制力がおよばず、コンテナ輸送の健全化の決定打とはならない。
「東京だけで100社以上のお客さんと交渉しているが、半数以上は値上げに応じていない。運べなくなって初めて運賃が上がる、まさにチキンレースだ」と語るのは、同社の企画部兼管理部の匂坂優希グループリーダー。荷主と直接交渉できない構造が、適正な価格転嫁を阻んでいる。
同社が京浜地区で抱えるシャーシは400本に上る。毎年数本ずつ更新を進めているが、価格高騰により入れ替えは遅れている。「年間10本更新しても40年かかる。車両費の負担は重い」と矢上氏は明かす。車両の老朽化は安全面のリスクとも直結し、資金負担の大きさが経営を圧迫している。

同社京浜支店、平田知之運行グループリーダー
前述のコンテナの荷待ち問題の大きな原因となっているのが、港湾の処理能力不足だ。待機場の整備や新システム導入など、行政や港運会社による改善策は試みられてきたが、効果は限定的である。同社京浜支店の平田知之運行グループリーダーは「以前10億円を投じた待機場も3日で機能しなくなったことがあった」と指摘する。
各種コストの増加やままならぬ運賃交渉。そして、「免許を取るのが大変な割に儲からない仕事」になってしまったことなど、コンテナ輸送を取り巻く状況は課題が山積している。しかし、業界団体などを通じ、トラックGメンと意見交換を行うなど、手をこまねいて待っているだけではない。
輸出入貨物は増加しており、海上コンテナ輸送の役割はますます重要になっている。しかし現場は限界に近い。港湾物流の持続可能性を確保するためには、行政による処理能力の強化と業界全体での適正運賃の確立、さらにドライバーの待遇改善が不可欠だ。矢上氏は「手取りを増やし、コンテナ輸送も稼げる仕事だと思ってもらえるようにならなければ、コンテナ輸送が持続していかなくなるだけでなく、国際物流の存続も危うくなるだろう」と強調した。(土屋悟)
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。