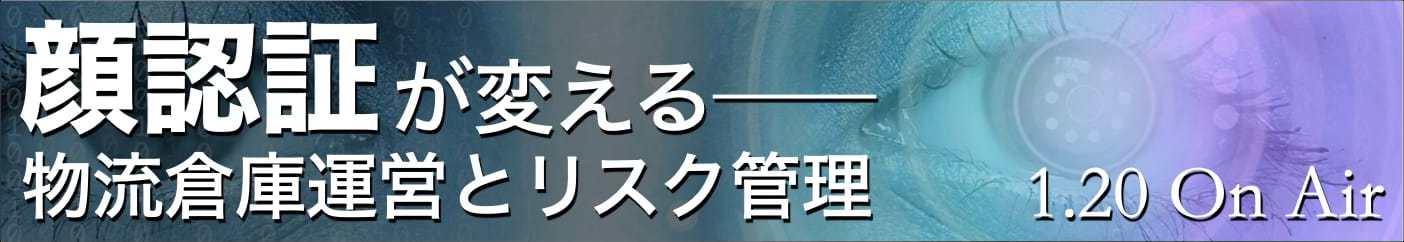行政・団体東京流通センター(TRC、東京都大田区)を拠点とする「平和島自動運転協議会」が5月22日発足し、TRC構内でオープニングセレモニーが開催された。「HeAD Light Field」(ヘッドライトフィールド)と名付けられた拠点で、自動運転に関する実証実験や企業間のオープンイノベーションを推進し、物流業界が抱える2024年問題などの社会課題解決を目指す。東京流通センターの依田渉運営管理部長は、平和島が自動運転の社会実装に最適な条件を備えていると強調した。

 根本から状況を変える自動運転、「平和島は社会実装に最適な条件」
根本から状況を変える自動運転、「平和島は社会実装に最適な条件」
セレモニーでは、まず協議会の事務局を務める日本経済研究所の小林純子執行役員が登壇。

▲日本経済研究所の小林純子執行役員
「物流の2024年問題など、なかなか閉塞感が打破できない中で、自動運転は根本から状況を変える可能性を秘めている」と期待を寄せた。そして、「技術面、法制度、社会受容性といった課題は大きく、1社では対応が難しい。この協議会が継続的な取り組みを進め、社会を変革していく機会となることを願う」と述べ、情報発信への協力も呼びかけた。
続いて、施設運営を担う東京流通センターの依田渉運営管理部長が「ヘッドライトフィールド」の設立背景とコンセプトを説明。TRCが半世紀以上にわたり物流効率化による社会課題解決を使命としてきた歴史に触れ、「昨今の2024年問題や人手不足、2030年問題といった危機に対し、自動運転車両の早期社会実装が社会的に求められている」と問題意識を共有した。

▲TRCの依田渉運営管理部長
その上で依田氏は、平和島が自動運転の社会実装における「社会受容性」「安全性」「経済性」の3つの観点で最適な条件を備えていると力説した。社会受容性については、「平和島は流通業務団地であり、倉庫やトラックターミナル以外の建設が制限され、一般歩行者との交錯が極端に少ないため、地域住民からの反対や懸念も起こりにくい環境だ」と説明。安全性に関しては、「道路構造が比較的単純で、交通の流れも業務用に最適化されており、一般道走行の課題が大幅に軽減される」とした。経済性では、「24時間365日稼働する日本有数の物流拠点であり、トラックの集積数は日本一と言っても過言ではない。自動運転導入による物流効率向上や人手不足解消は、日本経済全体への大きな波及効果とモデルケースになり得る」と、そのポテンシャルを語った。
 参画企業各社が抱負、協調領域でオープンイノベーション目指す
参画企業各社が抱負、協調領域でオープンイノベーション目指す
協議会には、自動運転開発企業のチューリング(東京都品川区)、Applied Intuition(アプライドインテューション、米国)、ソニー・ホンダモビリティ(東京都港区)、Wayve(ウェイブ、英国)の4社に加え、日本政策投資銀行(東京都千代田区)と日本経済研究所(同)、東京流通センターが発足メンバーとして名を連ねる。

各社代表も登壇し、協議会への期待を表明。チューリングの田中大介取締役COOは、自動運転システム開発企業として「大量のデータを集めるために、TRCのような設備は非常に大切。平和島から世界へ、という思いで頑張りたい」と語った。ソニー・ホンダモビリティの岡部宏二郎取締役専務は「多様な知見を持つパートナーと協調し、モビリティ業界のイノベーションに貢献したい」と述べた。
最後に、東京流通センターの有森鉄治社長が「施設サイドとして自動運転の実現に協力し、2024年問題を含む社会課題の解決に貢献したい」と締めくくった。
 会員は技術開発企業中心に、運送・荷主・保険業界とも連携視野
会員は技術開発企業中心に、運送・荷主・保険業界とも連携視野
質疑応答では、協議会が募集する会員の対象について問われ、事務局の日本経済研究所は、「主に自動運転関連の技術・サービス開発などに取り組む企業を想定している」と回答。その上で、「運送事業者や荷主企業、さらには実装に向けて対話が必要となる保険会社など、さまざまな関係者との連携も視野に入れている。政府や自治体との連携も重要だ」と述べ、幅広いステークホルダーとの協調の可能性を示した。今後の活動スケジュールについては、国の示す自動運転社会実装のタイムラインを参考にしつつ、具体的な取り組みを進め、適切なタイミングで対応できる環境を整備していくとした。
「ヘッドライトフィールド」では、TRCの私道、センタービル内のコミュニケーションルーム、A棟屋上駐車場(8000坪)やその他構内広場などを実証実験やデータ取得のフィールドとして会員企業に無償提供する。

▲同日公開された会員向けのコミュニケーションルーム