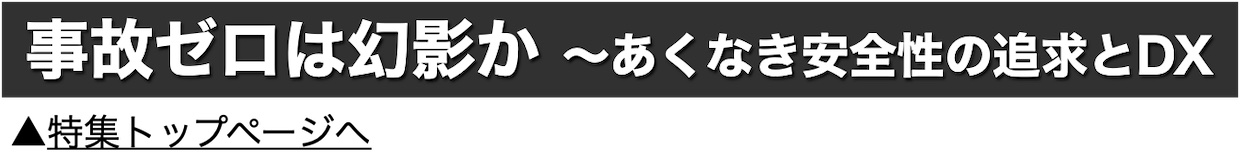話題AI(人工知能)による危険予測、リスク運転の検知など、近年のドライブレコーダーにはさまざまな機能が搭載されるようになった。しかし、どれだけ機能が多岐に渡ろうと、それをきちんと運用できなければ意味がない。

▲無事故プログラムDR(出所:BIPROGY)
AIドラレコ「無事故プログラムDR」を開発したBIPROGY(ビプロジー)は、機能よりも運用方法に対するアドバイスを重視しているという。適切な運用方法を伝えることで、同社はAIドラレコによる事故防止を実現したい考えだ。「事故防止には機能よりも運用」とする根拠はどこにあるのか、BIPROGYのパブリックサービス第二事業部の市村孝行氏に話を聞いた。
 しっかりした機能を備えているからこそ、提案に説得力が生まれる
しっかりした機能を備えているからこそ、提案に説得力が生まれる
もちろん、BIPROGYは機能をおろそかにしているわけではない。同社のAIドラレコ、無事故プログラムDRにはたくさんの機能が搭載されている。
特徴的な機能の一つがリスク運転の検知だ。ドライバーが危険な運転をすると、運行管理者に現場の映像とともにメールが送られる。「危険な運転」には信号無視や速度違反、一時不停止などの違反行為だけではなく、急ブレーキや急ハンドル、急発進など、事故につながりやすい行動も含まれる。ギアチェンジした後の安全確認をせずにすぐ後退を始めると、確認を促すメッセージが流れる機能もある。単に交通ルールを守っていれば「安全」とされるわけではない。
オプションとして、AIがドライバーや歩行者の行動を予測し、危険を知らせる「BP-BOX」というサービスもある。AIが衝突などの危険があると判断した場合、数秒前にドライバーに回避行動を促して事故防止を図る。BP-BOXによる警告も運行管理者に通知されるため、リアルタイムに全社的な状況把握が可能だ。
またSDカードが抜けたり、ドラレコ本体の電源が切れたりした場合も管理者に通知が届くため、事故にすぐ気がつけるほか、盗難や不正の対策にもなる。ドラレコに求められる機能がひと通りそろっているからこそ、提案にも説得力を持たせることができる。
 AIドラレコが事故防止につながる理由
AIドラレコが事故防止につながる理由
そもそも「AIドラレコが事故防止につながる」というロジックは何を根拠としているのか。それはAIが抽出するデータの真実味にある。
今までの安全教育は座学や、事故現場の映像を見せるといったものが一般的だった。しかし、それだとドライバーは事故を自分ごとと捉えることができず、限定的な効果しか得られないことも少なくない。しかし、AIドラレコなら危険運転をした本人に、本人の運転を見せながら指導をすることができる。これほど真実味のある説得材料はほかにない。 ドラレコなら危険運転が発生しやすい場所や時間帯も簡単に把握することができるため、会社全体で問題を共有したり、対策を講じたりもしやすい。
ドライバーが自分ごとと捉えられるかどうかで、指導の質は天と地ほどの差が出る。AIドラレコは、社内の安全意識を高める上でまさに最適なツールなのだ。
 豊富な機能を生かせるかどうかは運用次第
豊富な機能を生かせるかどうかは運用次第
BIPROGYはシステムインテグレーター(SIer)として60年以上の実績を持つ老舗企業だ。システムの中身には自信を持っているが、「いくら機能を説明しても、使ったときのイメージが湧かなければ、企業は導入を決めてくれない」と市村氏は語る。

▲パブリックサービス第二事業部の市村孝行氏
さらに同氏は「ドラレコはあくまでもツールであって、大切なのは効果的な運用ができるか。各企業の実情や課題に合わせた提案ができるのは、これまで多くのシステム開発を手がけてきたSIerとしての強みだと思う」と胸を張る。
そのため市村氏をはじめとするBIPROGYの社員は必ず現場で話を聞き、どのような運行管理をしているのかを確認する。ドラレコの開発に取り組んだ当初は、配送のトラックに乗せてもらうこともあったという。
「若い人には必ず現場に行くように言っている。現場を見ることで、利用する側が課題と感じていること、求めていることを、より深く理解できるようになる」(市村氏)
これまで同社は1400社、7万台ものドラレコを導入してきたが、企業によって安全対策への取り組みは異なり、業務内容によって利用する道路も異なる。例えば同社のドラレコは各地の生協で多く利用されているが、生協の配送車は市街地の細い路地を通ることが多い。地域密着の仕事だけに、安全意識が非常に高いと感じることが多いという。当然、ドラレコに求めるレベルも高く、ドライバーにいかにフィードバックをするのか、その答えをメーカーに求めてくることもある。そうした現場の声を吸い上げ、対策を提案できるのも、事業用コンピューターの黎明期からシステム開発を手がけてきたBIPROGYの経験と組織力があればこそだ。
年々、ドラレコに付属する機能は増えている。しかし、何でもできるからといって、会社の実情に寄り添えるかというとそうではない。どれだけ高性能の道具でも、使い道が分からなければ宝の持ち腐れになる。BIPROGYが単に機能を追及するだけではなく、運用までしっかりフォローする理由はそこにある。本当に重要なのは「何ができるか」ではなく、「現場でどう運用するか」だ。
 安全意識の高い「光るドライバー」を育成
安全意識の高い「光るドライバー」を育成
市村氏はBIPROGYを代表して、「AIドラレコは『光るドライバー』を一人でも増やすために使ってほしい」と話す。「光るドライバー」とは、高い安全意識を持って、的確な運転をするドライバーのことだ。

「安全意識の高い会社は、危険運転が多いドライバーを探すためにではなく、光るドライバーを探し、皆の手本にするためにドラレコを使う。そうした光るドライバーを増やしていけば、会社全体の安全意識も高まっていくはずだ」と市村氏は言葉に力を込める。
成績の悪いドライバーを炙り出して罰するような運用の仕方では、社内の安全意識は高まらない。データの捉え方一つにしても、いくつもの導入事例を持つ開発会社ならではのノウハウが生きてくる。
 次の目標はドライバーカルテの実現
次の目標はドライバーカルテの実現
市村氏は「交通事故や違反を減らすには、まず運行管理者や指導者の意識を向上させる必要がある」と話す。現場のトップが自ら課題を認識しない限り、全社的な取り組みは望めない。生協のように、はじめから現場の安全意識が高い例はむしろ少数だ。
市村氏もそこは課題に感じているようで「今後はドライバーを指導する立場の人たちをどう育成するのか、という点も考えていきたい」とする。その根底には機能を追求するだけでなく、いかにうまく使ってもらえるかにこだわるBIPROGY的な考えがある。
「無事故プログラムDRの導入をきっかけに、安全対策が不十分だった企業にも取り組みが広がればうれしい。私たちがドラレコを提供するようになってから十数年が経ち、社内にもさまざまな運用ノウハウが蓄積されている。そうしたノウハウを生かした提案で、安全意識の向上をサポートしていきたい」(市村氏)
市村氏は今、膨大なデータを整理・分析できるAIの利点を生かし、「ドライバーの『カルテ』をつくりたい」と考えている。ドラレコから得られるデータをもとに、各ドライバーの特徴や、改善すべき点などを分析、診断書のような形で分かりやすくまとめる。
「病院のカルテのようなイメージ。そうすれば、運行管理者が変わったり、本人が営業所を変わったりしても情報が引き継がれ、中期的な観点からドライバーの育成ができる。ドライバーとしての成長も一目でたどれる。さらに安全意識を業界全体に広げるためにも、絶対にやるべきだ」とコメント。「そういうこともAIならできる」と目を輝かせる。
市村氏にとってAIはツールに過ぎない。大切なのは、それをどう交通事故の削減や、ドライバーの働き方改善に役立てられるかだ。市村氏はまさに「機能よりも運用」というBIPROGYの開発理念を体現する存在といえる。