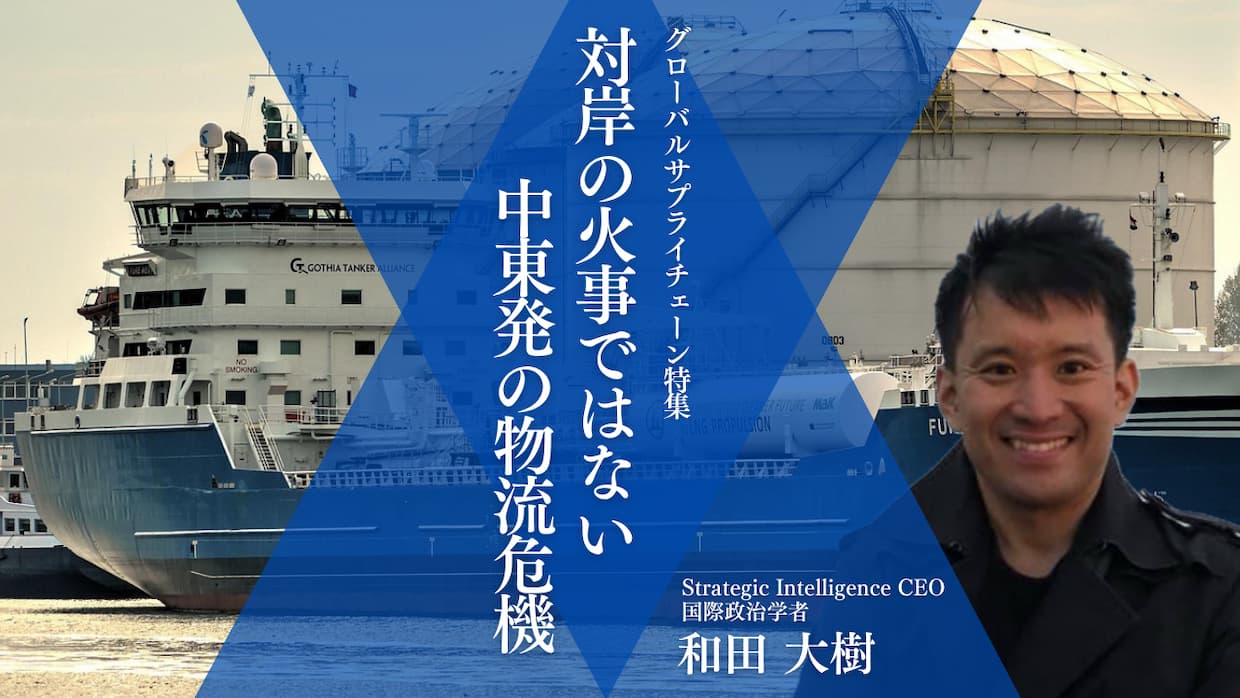
話題トランプ関税の再来に揺れるグローバルサプライチェーンだが、リスクは太平洋の向こう側だけではない。2025年6月の「12日間戦争」を契機に、中東情勢は再び緊迫の度を増している。ホルムズ海峡の緊張、イランとイスラエルの対立、そして紅海におけるフーシ派の活動活発化──。これらの地政学リスクは、対岸の火事ではなく、日本のエネルギー安全保障と国際物流網を根底から揺るがしかねない構造的な脅威だ。
この複雑で流動的な情勢を、日本の物流・サプライチェーン担当者はどう読み解き、備えるべきなのか。LOGISTICS TODAYは、国際安全保障研究に取り組む和田大樹氏(Strategic Intelligence社長)に緊急インタビューを実施。最新の中東情勢が日本のサプライチェーンに与える具体的なインパクトと、今企業が取るべき対策について話を聞いた。
 対岸の火事ではない、中東発の物流危機
対岸の火事ではない、中東発の物流危機
──現在のグローバルサプライチェーンに影響を及ぼしている中東の地政学リスクの全体像は。
和田氏:現在の中東情勢は、複数のリスクが連鎖し、増幅しあう「複合的危機」の様相を呈している。その中心にあるのが、2025年6月の「12日間戦争」以降、再び顕在化したイランとイスラエルの深刻な対立だ。特にイランの核開発問題は、イスラエルにとって国家の存亡に関わる脅威であり、イスラエルは核開発の初期段階であっても、先制攻撃を含む軍事行動を躊躇しない構えを見せている。ネタニヤフ政権はイスラエルが戦争状態にあることを強く自覚しており、安全保障を脅かす小さな兆候に対しても極めて敏感になっている。高い確率でイスラエルによるイランへの先制攻撃が起こり得るという前提で、我々は事態を注視すべきだろう。
この二国間の対立に連動するのが、ホルムズ海峡と紅海という、世界の海上物流における2大チョークポイント(航路上の隘路)の不安定化だ。イランは12日間戦争の際、世界の原油輸出の約2割が通過するホルムズ海峡の封鎖をちらつかせた。封鎖はイラン自身の経済にも大打撃を与えるため、現時点では外交的な脅しに留まる可能性が高いと見られているが、米国による経済制裁の再強化など、イランが追い詰められれば、その可能性はゼロではない。
さらに、イランの支援を受けるイエメンの武装勢力フーシ派は、紅海でイスラエル関連と見なした船舶への攻撃やシージャックを繰り返している。紅海はスエズ運河を通じて欧州とアジアを結ぶ大動脈であり、彼らの活動はすでに世界のサプライチェーンに直接的な打撃を与えている。
地政学リスクが物流コストを直撃する。

──イラン・イスラエル間の緊張や、ホルムズ海峡、紅海の不安定化は、具体的に日本の国際物流やサプライチェーンにどのような影響を及ぼすのか。
和田氏:最も直接的かつ深刻な影響は、輸送コストの高騰だ。ホルムズ海峡が封鎖されなくとも、周辺での小規模な軍事衝突や妨害行為が増加するだけで、原油価格は数日以内に10%以上急騰する可能性がある。日本の原油輸入の約9割を中東に依存していることを考えれば、燃料コストの増大が物流企業の収益を圧迫することは避けられない。
紅海ルートも同様だ。フーシ派による攻撃の激化を受け、すでに日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手3社は紅海ルートの航行を停止し、アフリカ喜望峰経由の迂回ルートを選択している。これにより航行日数が大幅に伸び、輸送コストは増大する。さらに、リスク増大に伴う保険料の高騰も深刻で、2025年初頭の時点で前年比20%増という報告もある。これらのコストは最終的に荷主、そして消費者に転嫁され、日本経済全体に影響を及ぼす。
また、日本企業の海外事業そのものにも影響が出始めている。イスラエル駐在員を帰国させたまま戻す計画を中止した企業や、イランが米軍基地を攻撃したカタールへの進出計画を見送った企業など、リスクを回避する動きはすでに現実のものとなっている。
 企業が今すぐ取るべき6つの対策
企業が今すぐ取るべき6つの対策
──まさに「対岸の火事」ではないということが理解できた。こうした不可避な変数に対し、日本の荷主や物流事業者は、どのような対策を講じるべきか。
和田氏: 長期的な視点でのリスク管理強化が不可欠だ。具体的な対策として、6つの柱を提示したい。
第1に「サプライチェーンの多元化」。エネルギーであれば、中東への石油依存度を下げ、豪州や米国などからのLNG調達を拡大する。部品調達であれば、東南アジアや南米など、中東情勢の影響を受けにくい地域にサプライヤーを多角化することが求められる。
第2に「リスクモニタリングの強化」。地政学リスクをリアルタイムで監視する専任チームを設置し、外部の専門分析機関とも連携すべきだ。AIを活用したリスク予測ツールを導入し、船舶の追跡データと地政学イベントを統合したダッシュボードで航路変更の判断を迅速化する、といった取り組みも有効だろう。
第3に「コスト管理と保険の見直し」。原油価格の急騰に備え、先物取引などで燃料コストをヘッジすることや、リスク増に対応した包括的な貨物保険に切り替えるといった財務的対策が重要になる。
第4に「危機対応計画の策定」。ホルムズ海峡封鎖といった最悪の事態を想定し、代替航路の選定基準や緊急時の在庫確保方針などを明記した具体的なマニュアルを策定し、定期的にシミュレーション訓練を実施すべきだ。
第5に「持続可能な物流戦略への転換」。これは守りだけでなく、攻めの対策でもある。電気トラックや水素燃料船といった脱炭素技術への投資は、長期的にはエネルギー価格変動リスクの軽減につながる。また、IoTやデジタルツインを活用した物流網の可視化は、平時の効率化だけでなく、危機時のサプライチェーン混乱を最小限に抑えることにも貢献する。
最後に「人材育成と組織強化」。地政学や国際安全保障に精通した人材を社内に育成し、物流、財務、リスク管理部門を横断したタスクフォースを設置することで、統合的な危機対応策を策定できる。
これらの対策は、一朝一夕に実現できるものではない。しかし、中東における紛争はもはや一過性のイベントではなく、グローバル経済に組み込まれた構造的リスクだと認識する必要がある。地政学リスクを経営の「変数」として捉え、平時から備えを怠らない企業だけが、この不確実性の時代を乗り越えることができる。◇
和田氏へのインタビューを通じて見えてきたのは、中東の地政学リスクが、もはや遠い国の出来事ではなく、日本の物流コストやサプライチェーンの安定性を直接脅かす「経営変数」になったという厳然たる事実だ。ホルムズ海峡や紅海といった物流の動脈は、常に寸断のリスクに晒されている。
和田氏が提示した6つの対策は、単なる危機管理マニュアルではない。それは、不確実性を前提とした新しい時代のサプライチェーンを構築するための戦略的指針だ。サプライチェーンの多元化やリスクモニタリングの強化といった「守り」の対策と同時に、持続可能な物流戦略への転換といった「攻め」の視点を持つことの重要性が浮き彫りになった。
「対岸の火事」と傍観する時間は終わった。自社のサプライチェーンに潜む中東リスクを直視し、和田氏の提言を参考に、今こそ具体的な行動を起こすべき時だろう。























