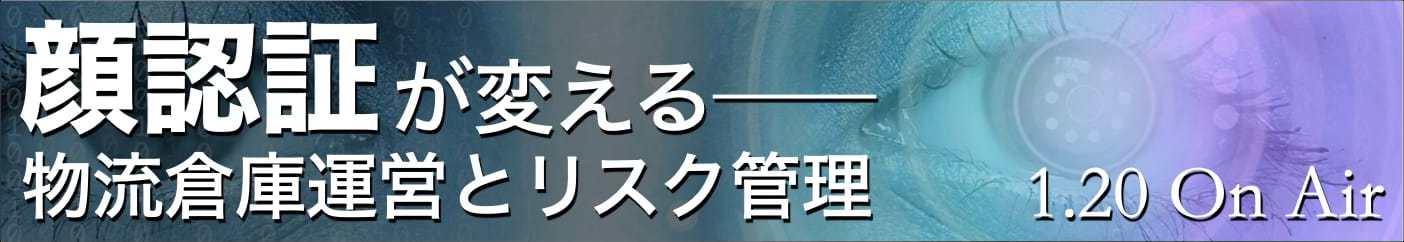行政・団体自民党の新総裁に高市早苗氏が選出された。現時点では党内の代表に選ばれた段階であり、国会での首相指名や野党との連立構想など、政局には依然として不透明な部分が残る。それでも、自民党が第一党である以上、高市氏が次期総理に最も近い位置に立つことは間違いない。こうした状況下、物流業界が今後の政策動向を注視するのは当然といえよう。(赤澤裕介編集長)

▲自民党総裁選の5候補。右から2番目が新総裁に選出された高市早苗氏(自民党公式サイトより)
 歴史的転換点に立つ物流関連法制
歴史的転換点に立つ物流関連法制
このタイミングで注目されるのが、2024年以降に相次いで成立した一連の法改正だ。物流関連2法とトラック事業適正化関連法は、長年の構造的課題を抱えてきた日本の物流・運送業界にとって、単なる制度改正にとどまらない意味を持つ。荷主・元請け・下請けの力関係にメスを入れ、取引の公正化とコストの適正化を制度として明文化した、まさに歴史的な政策転換といえる。
「物流関連2法」は、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(旧・物流総合効率化法)と「貨物自動車運送事業法」の改正を指す。24年5月15日に公布され、25年4月1日から順次施行されている。これにより、物流効率化を荷主と運送事業者の双方にとっての責務として位置づけ、共同輸送やモーダルシフトの推進を法的に支える枠組みが整備された。なお、法改正により旧・物流総合効率化法は「物資の流通の効率化に関する法律」へと名称が変更されている。
<関連記事>物流法改正案閣議決定、荷待ち削減計画義務化など
https://www.logi-today.com/586774
さらに踏み込んだ内容を持つのが、25年6月4日に成立、同11日に公布されたトラック新法だ。正式には「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」と「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」から成る。運送事業者の5年ごとの許可更新制の導入、再委託回数の原則2次までの制限、そして「適正原価制度」の法定化が盛り込まれた。公布から3年以内、すなわち28年6月までに施行される予定だ。
この「適正原価制度」は、運送事業者が人件費、燃料費、車両償却費など実際に発生するコストをもとに原価を算出し、それを契約交渉の基礎とする仕組みだ。従来のように荷主側が市場価格や過去の慣行で運賃を決定する構造を改め、実態に基づくコストベースで取引を行うことを求めている。多重下請け構造の是正と並んで、この制度が本格的に機能すれば、物流業界はようやく「安さを競う時代」から「持続可能性を競う時代」へと転換することになる。
<関連記事>「トラック新法」成立、運送業界に新たな規律
https://www.logi-today.com/786802
ただし、法の成立は出発点にすぎない。問題は、この制度をどう運用し、現場に浸透させていくかだ。行政が監督権限を強化するだけでは不十分で、荷主・元請け・運送事業者が共通の理解を持ち、適正な契約やコスト交渉を行うための仕組みづくりが不可欠だ。教育・研修、人材育成、情報開示、そして行政による相談・支援体制の整備。法律という器に魂を入れる“制度設計”こそが、次の焦点になる。
 問われる「実行力」
問われる「実行力」
この点で、経済安全保障や供給網強靭化を重視してきた高市氏の政策スタンスは、物流政策の延長線上にある。高市氏は自民党トラック輸送振興議員連盟のメンバーでもあり、業界との接点を持ってきた。サプライチェーンの再構築を進めるうえで、輸送ネットワークの安定と透明性は不可欠だ。国内生産拠点を支えるトラック輸送が健全でなければ、経済安全保障そのものが成り立たない。新政権がこの視点を政策の中心に据えられるかどうかが、改革の実効性を左右するだろう。
環境・エネルギー政策も、物流の現実と密接に関わる。EVトラックや水素トラックの導入支援、充電・燃料供給インフラの整備、燃料課税の見直しなど、脱炭素と経済合理性の両立を求められる課題が山積している。環境対策がコスト負担の上乗せに終われば、中小事業者の体力を奪いかねない。現実的な移行シナリオと技術支援を組み合わせる政策的柔軟さが、新政権に求められる。
一方、労働環境の改善と人材確保も、制度の定着を左右する重要な要素だ。時間外労働上限規制の施行から1年半が経過し、現場では人員不足や運行制約が深刻化している。適正原価制度が形骸化せず、ドライバーの待遇改善につながるためには、休憩施設・中継拠点の整備、デジタル運行管理の普及、荷主への取引是正指導など、多面的な対策が不可欠だ。制度を「働く人の現実」と結びつけられるかどうかが問われている。
これらの法改正は、いずれも長年の業界課題に正面から取り組むものとして評価されている。しかし、改革が真に成功するかどうかは、制度を支える“行政と政治の持続力”にかかっている。法律を整えただけで満足してしまえば、数年後には再び同じ問題が顔を出すだろう。現場を見続け、フォローアップを怠らない仕組みをどう構築するか。ここに、政治の実行力が問われる。
高市氏が率いる自民党は、今後も第一党として国政の中心に位置する。その政策判断が、制度改革を「理念」から「現実」へと動かす推進力になるのか。それとも、再び政治の関心が他のテーマに移ってしまうのか。物流政策は今、法律という器を手にした。次の一歩は、その器に魂を入れ、実効性を持たせることだ。それは政権の顔ぶれ以上に、制度を動かす意思と覚悟にかかっている。
物流を「国の血流」とする認識が政治の中で共有されるかどうか。それが、この国の産業基盤と暮らしを支える最大の分岐点となる。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。