ロジスティクスアセンド(東京都新宿区)は10月31日、都内で「ロジックス カンファレンス #2」を開催した。テーマは「迫るCLO義務化-先駆者が語る『理論』と『実践』-」。2026年4月にCLO(物流統括管理者)制度が義務化されるのを前に、行政・学術・実務の第一線が制度の意義と今後の方向性を議論した。CLO設置に大きな役割を果たした国土交通省担当者や、国内CLOの先駆けとなる人物などが、CLO設置制度を巡って発言、議論を交わした。

▲アセンド、日下瑞貴社長
冒頭、同社社長の日下瑞貴氏は、「CLOの設置まであと半年」というタイミングを踏まえ、現場で“CLOとは何か”という本質的議論が不十分なまま制度を迎えようとしていると指摘した。「制度だけでは改革は進まない。高度物流人材の育成と実践知の共有が不可欠」と強調した。
 制度は“変革の起点”
制度は“変革の起点”
基調講演では、経済産業省経済産業政策局の中野剛志・地方創生担当政策統括調整官が登壇。「DX(デジタルトランスフォーメーション)の価値はサプライチェーン全体で発揮される」と述べ、製造業に比べ物流領域の統合管理が遅れていたことを説明。働き方改革や2024年問題を搦手(からめて)として制度導入を進め、「制度は終点でなく“自律的変革”の起点」と位置づけた。

▲経済産業省経済産業政策局・地方創生担当政策統括調整官の中野剛志氏
 全体最適と人材育成
全体最適と人材育成
東京大学の西成活裕教授は「部分最適では社会は動かない。流れの視点で最適化すべき」と強調し、フィジカルインターネットや循環型物流の概念を紹介。「知と徳」を備えた高度物流人材の育成が必要と述べ、企業には優秀人材を受け入れる環境整備を求めた。
また、フィジカルインターネットへの前段階として、「サプライヤー側ではなく、モノを受け取る側・求める側の要求=デマンドを起点にした物流の考え方が必要だ」と強調した。

▲東京大学工学系研究科・先端科学技術研究センター教授の西成活裕氏
 “運ばない”物流への転換
“運ばない”物流への転換
西成氏に続いて登壇したのは、流通経済研究所 特任研究員・神戸大学大学院 国際海事研究センター リサーチフェロー/元サンスター グループCLOの荒木協和氏。日用品メーカーで30年以上、倉庫・配送の現場からサプライチェーン全体の再設計まで担い、国内外の物流改革をけん引してきたCLOの先駆けの一人だ。
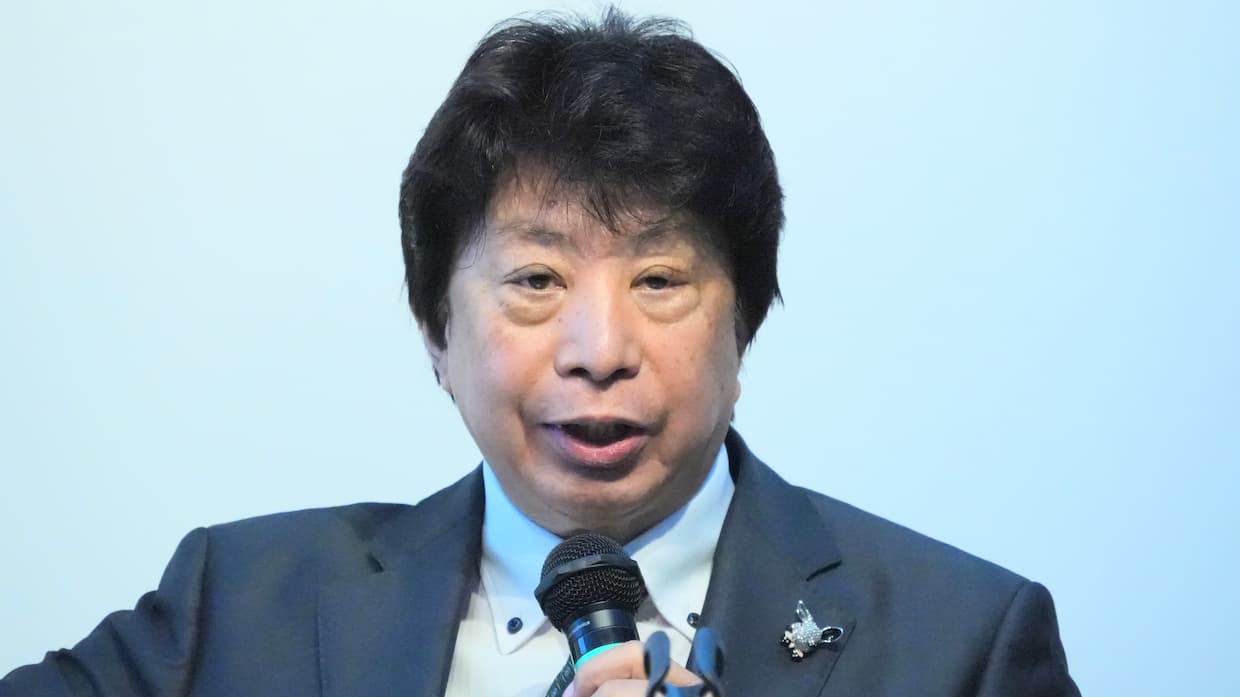
▲流通経済研究所 特任研究員・神戸大学大学院 国際海事研究センター リサーチフェロー/元サンスター グループCLOの荒木協和氏
荒木氏は、これまでの物流の歩みを「効率化に見せかけたサービス過剰競争」と表現。リードタイム短縮や納品回数増加、24時間対応といった“要求水準の積み増し”が続いた結果、ドライバーの負担増と低賃金構造が固定化したと指摘した。「社会や消費者が“当たり前”と思っている物流サービスの多くは、本当は当たり前ではない。まずは戻せるところから戻すべきだ」と訴えた。
そのうえで、CLOに求められるのは「運ぶ工夫」ではなく、「運ばないための設計」だと強調。需要予測と在庫戦略の最適化、SKU整理、共同物流の推進、リードタイムの見直し、配送頻度の適正化など、“そもそも物流を増やさない”構造改革こそが本質だと語った。
また、CLOは単に現場を知るだけでは務まらないとし、管理会計や原価構造、投資判断、社内調整、取引先との交渉まで理解する必要があると述べた。「運賃は上げよ、コストは下げよと言われる。その矛盾を飲み込み、現場の声を経営に、経営の判断を現場に返す。泥臭さとロジックを両立できるかが問われる」と語った。
さらに、制度施行後に想定される「兼任CLO」のリスクに触れ、「CLOは管理職の肩書ではなく、物流戦略の責任者であり、企業を横断する役割。専任化と権限付与がなければ、実効性を失う」と警鐘を鳴らした。
 役職より“実行する人”
役職より“実行する人”
続いて登壇したのは、流通経済研究所 特任研究員/元・味の素株式会社 上席理事物流企画部長の堀尾仁氏。荒木氏と並び、国内物流のCLOの先駆者の一人である。加工食品物流で共同基盤「F-LINE」を立ち上げ、メーカー・卸・小売を巻き込んだ商慣行改革を推進してきた経験を紹介した。

▲流通経済研究所 特任研究員/元・味の素株式会社 上席理事物流企画部長の堀尾仁氏
堀尾氏は、SKU増大や販促・在庫の複雑化、多頻度・少量化によって「メーカー単独では限界が訪れていた」と振り返る。そのうえで、「物流は物流部門だけでは変わらない。誰と組み、どう順番をつけて動くかがすべて」と強調した。
今回の制度については、「積載効率向上、荷待ち削減、荷役改善という“当たり前のこと”を徹底する話」と位置づける。現場からは「CLOと物流統括管理者の違い」「選任できる人材がいない」といった声もあるが、「肩書きよりも地道に改善を進められる人が重要」と断言。「まず荷待ち時間を測るだけでも一歩前進する」と語った。
また、「制度に合わせるのではなく、制度を使って会社を変えるべきだ」と指摘。理念やスローガンでは進まない企業文化の重力を踏まえ、「現場の納得と経営の意思がそろって初めて動く」と強調した。最後に「制度は始まりにすぎない。明日一つでも改善を動かすことが価値につながる」と締めくくった。
 議論から実装へ
議論から実装へ
講演後のディスカッションでは、CLO制度が「仕組みとして機能するための条件」をテーマに、制度設計・現場実務・人材育成の観点から議論が行われた。共通して示されたのは、物流改革の最大の壁は制度でもテクノロジーでもなく、経営層の意識と現場文化の変化であるという認識だ。
まず、中野氏は「制度は答えを示すものではなく、議論と行動を促す装置」と述べたうえで、細かな指示やガイドラインを積み上げるより、企業が動かざるを得ない“きっかけ”が必要だと指摘した。荷待ち2時間ルールはその象徴であり、「説明より行動を先に置くことで、現場の思考が切り替わる」と語った。CLO設置には、企業間連携の窓口を明確にし、責任と権限を伴う担当者の「旗」を立てる狙いがあるという。

▲パネルディスカッションの様子
一方、西成氏は、制度を契機に社内で権限を明確化し、改善の優先順位をつけることの重要性に触れた。「物流は社内調整の塊。誰が意思決定し、どこで線を引くかが曖昧だと、結局何も変わらない」と述べ、短期的効果だけを求めず、信頼関係と長期視点のアプローチが不可欠だと強調した。
議論では、他社との協働の難しさも挙がった。理想を掲げてスタートしても、進行に伴い利害対立が顕在化し、元の企業都合に揺り戻されるケースは少なくない。こうした“協業疲れ”を防ぐには、理念と経済合理性の両立、成果指標の共有、トップ同士のコミットメントが必要との認識が示された。「制度対応で終わらせるのではなく、制度を『使って』企業文化を変える。その覚悟が問われる」という堀尾氏の言葉が象徴的だった。
全体として、CLO制度は「肩書きの配備」ではなく、「実行と学習を積み重ね、外部と連携して構造を変えていくための起点」と位置づけられた。制度施行まで半年余り。企業は“待つ姿勢”から“動きながら形にする姿勢”へと、明確な転換を迫られている。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。




















