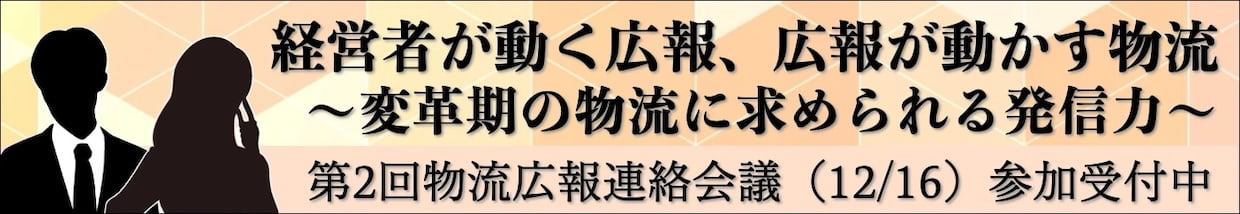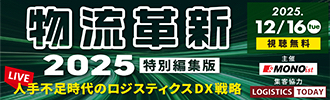ロジスティクス「会社と完全に音信不通で9連休だって?」──常識人なら眉をひそめるところだが、こんな休暇制度が実際に存在する。それがEC(電子商取引)サイトの構築から運用、物流までを手がけるルビー・グループ(東京都渋谷区)が全役職員を対象に10月に導入した「山ごもり休暇制度」だ。これにより、年末年始休暇のほかに年1回、平日5日間に前後の土日を加えた9連休を取得できる。特筆すべきは「山ごもり」の名が示す通り、休暇中は会社との連絡を完全に遮断する点にある。現代のビジネスパーソンにとって、これほど贅沢な“デジタルデトックス”はないだろう。
この制度、実は親会社のイルグルムが2011年に始めた。ルビー・グループマーケティング企画部部長の花房亮太氏は「親会社に続き、我々も今年度から導入した」と語る。この休暇制度の狙いは「属人化の解消」と「心身のリフレッシュ」にあるという。だが、この制度の本当の価値は、単に社員を9日間休ませることではない。属人化の解消に加え、業務の可視化、プロセスの改善といった、組織全体の底力を引き上げる知恵が、巧みに仕組まれている。いわば「休暇という名の組織改革」だ。

▲同社は従来の「EC運営代行(BPO)」に留まらず、顧客の業務プロセスを根本から再設計し「仕組み化」を推進する「業務改革パートナー(BPR)」へと提供価値をシフトする戦略的転換を図る
 1年前から始まる準備と“往復チェック”
1年前から始まる準備と“往復チェック”
休暇に向けた準備期間の話は非常に興味深い。同社は10月スタートの年度制。山ごもり休暇をいつ取るかは、その前年度の9月に決めるという。「場合によっては来年の9月に取る人もいる」(花房氏)といい、この場合、1年先の予定を立てることになる。準備期間はたっぷり1年。逆算してじっくり引き継ぎできる算段だ。
引き継ぎには専用のスプレッドシートを活用する。花房氏は「フォーマットに沿って、どのタスクを誰に託し、何を伝えるべきかを明記する」という。さらに、「記入したら終わりではない。事前にミーティングを開き、休む本人が主導して引き継ぐ」と説明する。責任の所在を曖昧にしない仕組みだ。
さらに、クリアすべきチェック項目が複数待ち構えている。花房氏の説明によれば、「承認権限にしても、休暇中に社内の決裁が滞れば業務が立ち往生する。だからシステム上の変更が済んでいるか、お客様への連絡は万全かなど、休暇前のチェックリストを全てクリアして、初めて安心して山にこもれる仕組み」というのだ。
見逃せないのは、休暇前の準備だけで終わらせない点だ。「休暇前に引き継ぎができているか、帰ってきた翌日の朝に進ちょくを確認する。上長が最後に前後の引き継ぎが完了したことを確認して、この方の山ごもり休暇が完了となる」(花房氏)という。つまり、出発前の点検に加え、休暇後の検証まで怠らない。この“往復チェック”こそが、制度を絵に描いた餅にしない知恵なのだ。
 ドキュメント化を促す“仕掛け”
ドキュメント化を促す“仕掛け”
「当社はお客様の運営を代行する、つまり、簡単には休めない責任ある事業だ」という花房氏の言葉には、同社が背負う覚悟が滲む。「だからこそ、お客様に迷惑をかけない、その先の消費者にも不便をかけない。この一線だけは、何があっても譲れない」と明言する。業務の可視化は、その信念を貫くための現実的な対応策なのだ。
属人化の解消には、ドキュメント化という地道な作業が欠かせない。花房氏は「長年の課題だった、属人的なスキルのドキュメント化を徹底することにした。この制度自体がドキュメント化の必要性を生み出す仕掛けになった」と語る。
花房氏が画面共有で披露した引き継ぎシートを見ると、各業務の手順書へのリンクが整然と並んでいる。社員なら誰でもアクセスできるページに業務手順を具体的に記載し、それを引き継ぎ書とする。ある社員が「マニュアルだけでは不十分。引き継ぐ前に実際に一度作業していただく必要がある」と言うように、文書化と実地研修の両輪で引き継ぎを完遂することもできる。

▲プレス向けにも山ごもり休暇制度を発表した(出所:ルビー・グループ)
 他者の目が回すPDCAサイクル
他者の目が回すPDCAサイクル
この制度の真価は、業務プロセスの継続的な改善にある。花房氏は「誰かから業務を引き継いで代行すると、『この作業はもっとこうすればいい』と気づくことがある。そうすることで業務がブラッシュアップする。他者の目が入ることでPDCA(計画・実行・評価・改善)が回るのは、この制度の隠れた妙味だ」と語る。
引き継ぎを受けた側が新鮮な目で業務を見直すことで、従来の担当者が見逃していた改善点が浮かび上がる。この循環が、組織全体の底力を押し上げている。ある社員の言葉が印象的だ。「仕事は放っておけば膨らむ。お客様の大事な仕事にミスは許されないというプレッシャーや失敗を恐れるあまり余計な作業が増えていく。そんな贅肉をそぎ落とすいい機会になる」
 「私しかできない」からの脱却
「私しかできない」からの脱却
「自分だけが抱え込んで『私しかできない』という妙な優越感に浸っていた時代から、世の中の働き方も様変わりした。会社がこういう制度を用意してくれたおかげで、仕事とプライベートのバランスを上手く取れるよう、社員の意識が少しずつ変わってきている」と休暇制度を評価する花房氏。さらに、「自分自身を見つめ直し、自分の仕事も客観視して、これって俺だけのことか、みんなで共有できるよね、そもそも必要なのかなど、多角的な視点で見つめ直すことになる。その観点も有効」と制度の副次的効果について言及する。
また、ある社員は「自分が言語化しないままやっている作業や抱えている業務が、本当に必要か必要でないかを見直せる。プライベートと仕事の自分がやる範囲を棚卸しできるいい機会。加えて、一部の業務が特定の担当者に集中している状況も、この制度を通じて可視化できた」と思いを述べた。

▲同社社員が山ごもり休暇制度を利用してマレーシア旅行をした際の写真(出所:ルビー・グループ)
 Slackが追いかけてくる現実
Slackが追いかけてくる現実
この制度にも課題はある。花房氏は「システム障害は予告なく発生する。決裁権を持つ者が不在だと対応できない」と語る。そこで同社は緊急連絡先の記載をルール化した。完全遮断とはいえ、最後の最後の接点だけは残しておく。現実的な着地点だ。
もう一つの課題はデジタルツールだ。ある社員は「社内はSlackで情報を共有している。休暇中も自分宛てのメンションやチャンネル通知が目に入る。トラブルの気配を感じると、自分が出るべきか迷う」と語る。便利な道具が休息の質を脅かしている。花房氏も「連絡を禁じるルールだが、Slackへのシステム的制限はかけない。責任感とのトレードオフで、気になることはある」と認める。
 物流業界への波及も視野に
物流業界への波及も視野に
変化の激しいEC業界で9日間も現場を離れる。一見、無謀に映るかもしれない。だが花房氏の考えは「従業員が自分の仕事を見つめ直し、磨き上げる姿勢こそが要。山ごもり休暇はその触媒になる」と明快だ。休むことで働き方が変わる。この逆説にこそ、制度の真髄がある。
同社は自分たちの知見を囲い込むつもりはない。花房氏は「フォーマットに著作権をつけるつもりはない。ノウハウの公開も検討している」と語る。物流業界など、属人化に悩む業界への波及も現実味を帯びてきた。「物流でも属人化は深刻な問題。私たちが一つの道筋を示せれば」と花房氏は言う。
休みにくいことで知られるEC業界で、9日間の完全休暇を成立させる──。この試みの本質は、業務の見える化と属人化の解消、そして絶え間ない改善を通じた組織の成長にある。来年度の実績を踏まえ、同社の取り組みは働き方改革に取り組む多くの企業にとって、一つの指針となるかもしれない。(星裕一朗)
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。