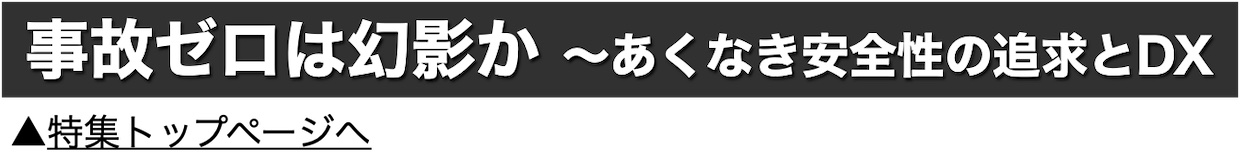話題今までドライブレコーダーは主に事故原因を特定するために使われてきた。しかし、AI(人工知能)の発達により、ドライブレコーダーの役割は「原因特定」から「事故防止」へと変わりつつある。その変化の最先端をいくのがGO(ゴー、東京都港区)だ。
AIドラレコ導入のメリットは、単に「事故というマイナスをゼロにする」ことにとどまらない。詳細かつ客観的なデータは運転を正当に評価することにつながり、ひいてはドライバーの定着や採用につながる。今回はAIドラレコの可能性を広げたGOの取り組みを紹介する。
 事故防止の鍵は「正確なデータを活用した納得度の高い指導」
事故防止の鍵は「正確なデータを活用した納得度の高い指導」
GOのAIドラレコ「DRIVE CHART」(ドライブチャート)に携わる武田浩介氏(スマートドライビング事業本部部長)は、「事故を減らすには、ドライバーを事故を起こしにくい人材にする必要がある」と語る。そのためには「短期でPDCAサイクルを回すことが重要」と強調する。

▲スマートドライビング事業本部部長の武田浩介氏
PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の頭文字をとった言葉だ。これを事故防止に当てはめると、安全運転の習慣化(Plan)、実運転(Do)、リスクの抽出(Check)、安全指導(Action)となる。
従来は効果測定(Check)をアナログな方法で行うしかなく、非効率的かつ不正確なデータしか得られなかった。曖昧なデータをもとにしたアドバイスは具体性を欠き、ドライバーは安全指導を自分ごとと捉えられず、限定的な効果しか得られないことが多かった。つまり、事故防止の鍵は事故につながるリスク運転をいかに正確にチェックできるかにかかっている。
 次世代AIドラレコサービス「DRIVE CHART」の底力
次世代AIドラレコサービス「DRIVE CHART」の底力
DRIVE CHARTは車内外にカメラを設置し、外的要因(道路状況・車の動き)と内的要因(ドライバー)の両方を随時チェックする。単に映像を記録するだけではなく、AIが運行時のリスクを自動で解析・抽出する仕組みだ。車外のカメラは急ブレーキ・急発進といった極端な車の動きだけでなく、一時不停止や車間距離の詰めすぎなどのリスク要因も見逃さない。運転席を向いたカメラは脇見や居眠りといったドライバーの危険運転行動をチェックし、リスクのある運転行動を検知するとAIが自動で録画映像を管理者に通知する。

▲車内外を捉えるDRIVE CHARTのカメラ
同じ作業を人が行うとなると、膨大な手間と時間がかかる。また、録画された映像を見せられれば、ドライバーもリスクを直感的に理解できる。管理者の手間を省き、ドライバーの自覚を促すという意味で、DRIVE CHARTはまさに一石二鳥の優れものだ。
DRIVE CHARTはドライバーを正当に評価するためのツールとしても使える。事故が起こるかどうかは確率の問題であり、普段安全運転を心掛けているドライバーが避けようのない外的要因で事故を起こすこともあれば、危険な運転をしているドライバーがたまたま事故に遭っていないこともある。
DRIVE CHARTにはドライバーの評価機能が備わっている。運転中、リスクのある運転行動が少ないドライバー、つまり安全運転を心掛けているドライバーほど評価点が高くなる仕組みだ。安全運転に対する確固とした評価基準ができたことは、「正しく評価してもらえる」というドライバーのモチベーションにつながる。
 事故防止がドライバーのモチベーションアップにつながる
事故防止がドライバーのモチベーションアップにつながる
DRIVE CHARTの導入が、実際にドライバーのモチベーションアップにつながった例を紹介しよう。
OCS(東京都江東区)はANA系列の企業で、陸路・空路を組み合わせた国際物流を担う。同社は実輸送の多くを協力会社に委託している。事故防止のため、協力各社の車両にDRIVE CHARTを導入したところ、最初の1か月で6000件以上のリスク運転が検知されたという。
特に多かったのは「一時不停止」。これは法律違反になるので、見過ごすことはできない。同社の運行管理部門を束ねる相沢誠氏は、「導入当初は『監視される』との思いから、ドライバーからの反発も大きかった」と話す。
しかし、ドライバーを地道に諭し、スコアが上下するたびに声かけを徹底。良いときにはとにかく褒めることを意識し、年間を通じてスコアが高かった者を表彰したりもした。また、目指すべき目標値をしっかり設定し、協力会社ごとのスコアも公表。安全運転が評価されることを周知し続けた結果、6000件あったリスク運転が、現在では100件を割るほどまでに激減したという。
次に紹介するのは、食材の宅配サービスを手掛けるヨシケイ(静岡市駿河区)のフランチャイズで、東埼玉エリアと兵庫県南西部・播州エリアの配送を担うヨシケイ東埼玉。同社ではDRIVE CHARTの導入後、事故が3分の1程度にまで減少したという。
事故を起こして辞めてしまう従業員が多かったことが、導入のきっかけとなった。事故を起こすのは入社1年以内の新人社員がほとんどで、同社代表の前川将樹氏は、ようやく仕事に慣れてきたタイミングで人が辞めていくことに課題を感じていた。以前は事故防止のためのチェックシートを記入してもらったり、朝礼で注意を促したりしていたが、効果は限定的だった。
そこで事故防止のためにDRIVE CHARTを導入。従業員の評価項目にDRIVE CHARTの評価点を組み込んだところ、社内の安全運転に対する意識は大幅に向上した。具体的には、安全運転を心掛けていれば(DRIVE CHARTの点数が高ければ)、営業成績を5%伸ばしたのと同程度の評価が得られるという。
前川氏は「事故防止に取り組むきっかけは何でもいい」と語る。「大切なのは事故を減らすこと。ドライバーに長く働き続けてもらうには、事故が起きにくい仕組みをつくる必要がある」
 GOが提供する、AIにもできないサービス
GOが提供する、AIにもできないサービス
GOはDRIVE CHARTが検出するリスク運転数が少ない事業者を表彰したり、そのノウハウをほかの事業者に共有したりもしている。ときには事故防止の専門家から意見をもらい、発信することもある。事故防止に取り組む事業者間で情報の垣根があってはならない、との考えからだ。
DRIVE CHART事業に取り組む武田氏も、「我々の目的は事故を減らすことであって、ドライブレコーダーを売ることではない」と言い切る。

▲GOは現場の人同士をつないでいく
昨今、事故防止の観点から自動運転技術に注目が集まっている。しかし、実用化にはまだまだ時間がかかることは必至で、人が荷物を運ぶ現在の方式はしばらく変わりそうにない。安全運転の成否はまさに現場の「人」にかかっており、生身のドライバーに安全運転の大切さを伝えるのは、同じ現場の「人」にほかならない。そのため、DRIVE CHARTは人同士のつながりを強固にするためのサポートもしている。
DRIVE CHARTには「カスタマーサクセス」というチームがある。このチームの目的はただ一つ、顧客の事故を少しでも減らすことだ。AIドラレコでいくらデータを集計しても、情報をうまく活用できなければ意味がない。そこでカスタマーサクセスはデータの活用方法はもちろん、運行管理者とドライバーのコミュニケーションの取り方まで踏み込んだアドバイスを行う。
「事業者ごとに現場の状況は全く違う。どういった運用の仕方をすれば安全運転が実現できるのか、一緒に考えられることがGOの最大の強みだ」と武田氏は語る。
単にツールを導入すれば事故が減るわけではない。現場のリアルなコミュニケーションが事故防止につながる。そしてGOは単にシステムを提供するだけでなく、現場の人と人をつなげる手伝いもしている。人同士をつなげることは、AIにもできないことだ。