イベントLOGISTICS TODAYは、JDSCとKURANDO(東京都品川区)との共催で、オンラインセミナー「AI×データサイエンス 倉庫改革の最前線~データ可視化・活用による倉庫運営の進化論~」を開催した。AI活用による倉庫改革は、もはや絵空事ではない。
JDSCが大手物流企業で実現した「工数14%削減」という具体的な成果は、データ活用が次の段階へ進んだことを明確に示した。改革の最前線を走る両社が、そのアプローチと乗り越えるべき壁について議論した。
セミナーで最も注目を集めたのは、JDSCが明らかにした導入実績だ。同社はセンコーの3拠点(200人規模)で、センター長の判断を支援する「AIセンター長」を運用している。導入からわずか半年強で、これまでブラックボックスだった手待ち時間を原資とし、「14%の工数削減余地」を確認したという。
佐藤飛鳥COOは「倉庫内の手待ち時間は20~25%に上るケースも多い。そのうち約6割の削減が見えてきたことになる」と説明し、AIによる最適化がもたらすインパクトの大きさを強調した。この成果は数字上の変化にとどまらない。佐藤氏は「データをもとに意思決定をする、という文化が醸成されつつあることが非常に大きい」と述べ、改革の本質が組織文化の変革にあるとの認識を示した。

▲JSDC佐藤飛鳥COO
そもそも、なぜ今「倉庫改革」が急務なのか。佐藤氏はその背景にある構造課題として「人手不足」「データの分断」「ノウハウの属人性」の3点を挙げる。従来の人海戦術が限界を迎え、拠点ごと・システムごとにデータは分断され、ベテランの経験に依存した運営が生産性の格差を広げている。
KURANDOの岡澤一弘社長も「時給上昇や付帯作業の増加といった変化は一過性ではなく、コストは上がり続けている」とこれに同意。両社は、この根深い課題を解決する鍵が、段階的なデータ活用にあるという点で一致する。JDSCは、データをAIの成熟度に応じてステップアップさせる手法を提唱。「点」のデータを収集し(Lv.1)、それらを「線」でつなぎ可視化(Lv.2)、AIで計画を最適化(Lv.3)、最終的には自律化(Lv.4)を目指すという考え方だ。 これに対し岡澤氏は、自社のサービス群が目指す流れと「完全に一致している」と指摘し、両者のアプローチが業界の王道であることを裏付けた。

▲KURANDO岡澤社長
しかし、その道のりは平坦ではない。佐藤氏は「AI構築は非常に大変。導入にはユーザー側もトップダウンで投資を覚悟するチャレンジが必要」と語り、水平展開の難しさを認める。同じ会社でも荷主や商材が違えば業務は全く異なり、結局は個別対応が求められるからだ。
また、現場の「AIアレルギー」も大きな壁となる。岡澤氏は「導入初期は『見張られているようだ』と嫌われたが、2~3年経つと『状況がわかるのは良いことだ』と意識が変わってきた」と実感を込めて語る。現場の信頼を得るには、AIがなぜその判断を下したのかを提示する「説明可能性」や、直感的に使えるシステム設計が不可欠だ。両社が目指すのは、単なるツールの導入ではなく、データ活用に慣れることで現場の意識を変え、来るべきAI時代に備えるための土壌を育むことにある。
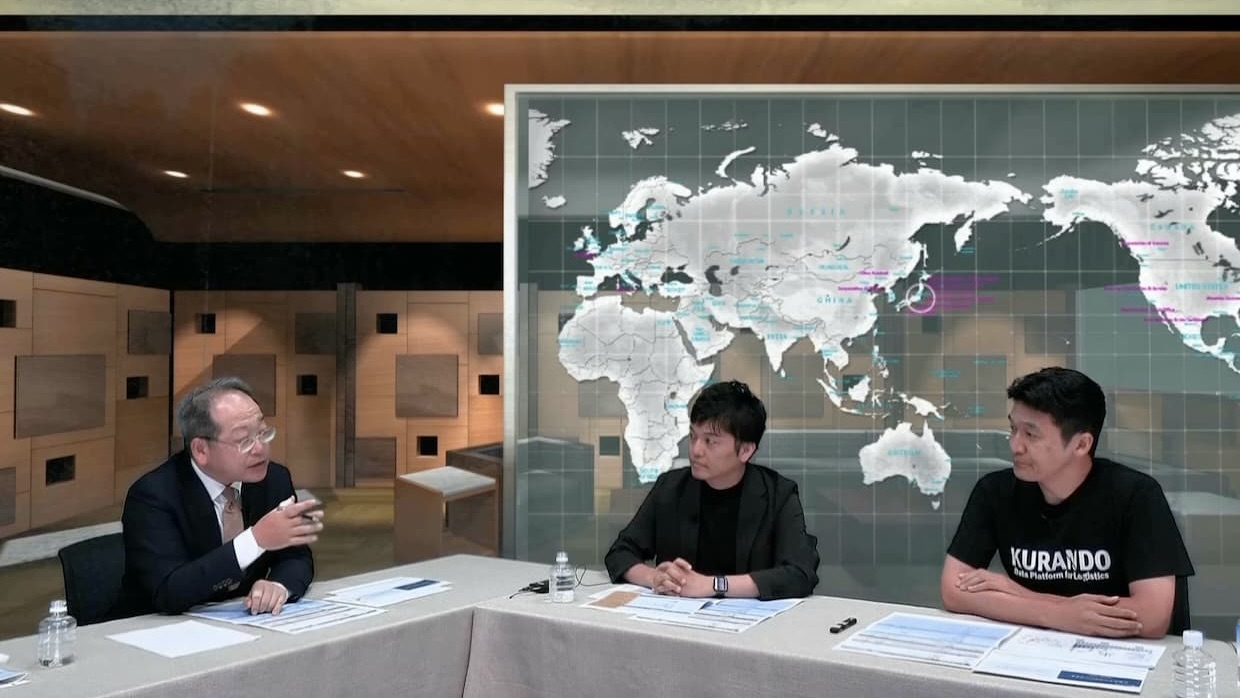
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。



















