ロジスティクスLOGISTICS TODAYが7日に開催したイベント「LOGI NEXT 25 Day1」で、「日本郵便問題は他人事か?店舗・配車・請求をつなぐ現場起点のDX戦略」と題したパネルセッションが行われた。
登壇したのは、テレニシ(大阪市中央区)法人事業本部ソリューション営業二部の吉田寛之部長、物流向けDX(デジタルトランスフォーメーション)サービスを展開するアセンド(東京都新宿区)の森居康晃COO、NBSロジソル(大分県日田市)の河野逸郎社長の3人。日本郵便の点呼不備問題を起点に、安全管理と現場負荷の両立について議論が交わされた。
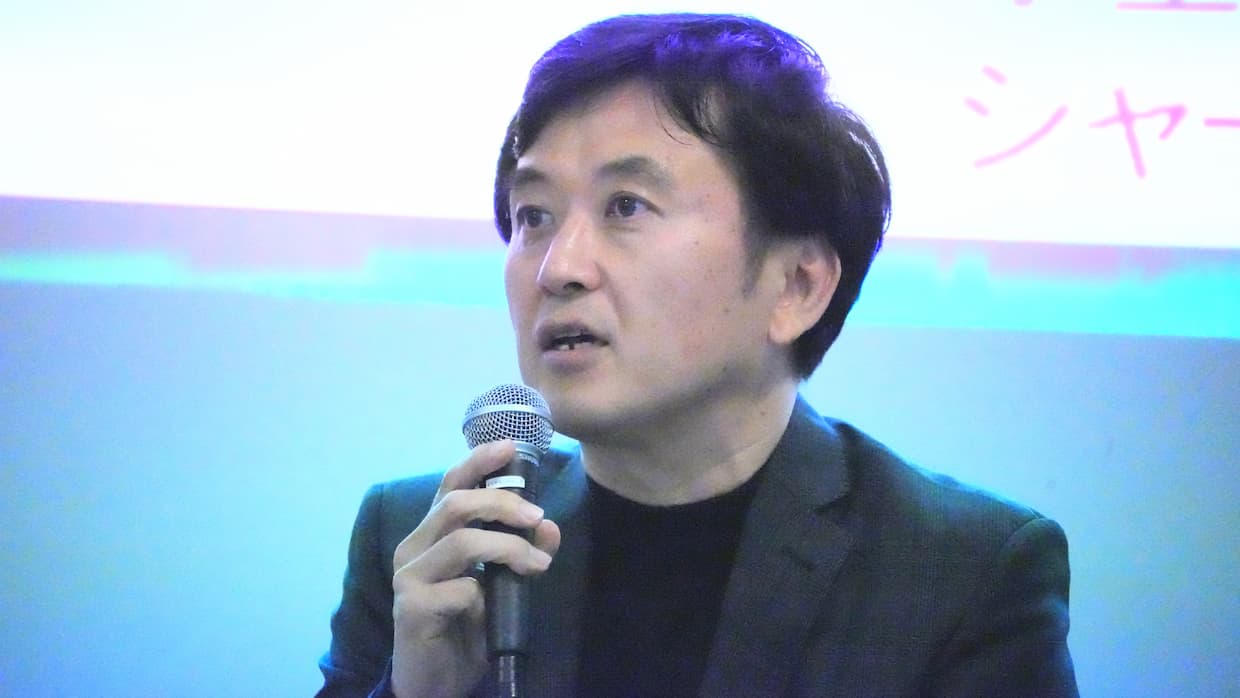
▲NBSロジソルの河野逸郎社長
吉田氏は、点呼の方法が対面、電話、IT点呼、遠隔点呼、業務前自動点呼と増え続けており、どれをどう使い分ければいいのか現場が迷いやすい状況になっていると指摘した。そのうえで、対面点呼はコミュニケーション面で価値がある一方、すべてを対面で行うと現場の負荷が大きくなるとし、業務特性と人に合わせた最適な組み合わせが必要だと述べた。
続いて森居氏は、日本郵便の点呼不備問題に触れながら、データを本部に集め、本部が判断する中央集権型の考え方自体がDXと相性が悪いと語った。本部と現場が異なるデータを見ている状態では、本質的な改善につながらないという。現場が状況に応じて判断でき、本部はモニタリングに徹する。両者が同じデータを見る構造をつくることが、DXの出発点になると強調した。

▲アセンドの森居康晃COO
また森居氏は、点呼データやデジタコデータをほかのシステムと連携することで、安全管理だけでなく経営面にも価値が生まれると説明した。拘束時間や待機時間、運行ごとの実績を配車情報とひもづければ、仕事ごとの原価を正しく把握でき、それが運賃交渉のエビデンスにもなると述べ、単独のシステムではなくデータがつながる仕組みの重要性を示した。
一方で河野氏は、運送会社としての現場課題を率直に語った。データが部門ごとに分断され共有されないこと、本部と現場で見ている数字が異なること、多くのデータが判断に使える状態まで整理されていないことが改善の障壁になっているという。報告するためのデータではなく、自然と情報が共有される状態こそDXであると述べ、仕組みづくりそのものの重要性を指摘した。

▲テレニシ法人事業本部ソリューション営業二部の吉田寛之部長
さらに河野氏は、荷主の安さ優先の選定姿勢に触れ、「安全投資やDXを進める会社ほど良い荷主に囲われる」とし、「安さだけで選ぶと結果的に輸送力不足につながる」と警鐘を鳴らした。
セッションの締めくくりで河野氏は、「DXは法改正への対応のために行うものではなく、ドライバーや社員が豊かに働ける環境をつくり、安全な社会につなげるための取り組みであるべき」だと語った。点呼DXを中心とした現場起点のDXこそ、これからの物流事業者の競争力を左右するテーマであるとの方向性で、3人の認識は一致した。
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。
















