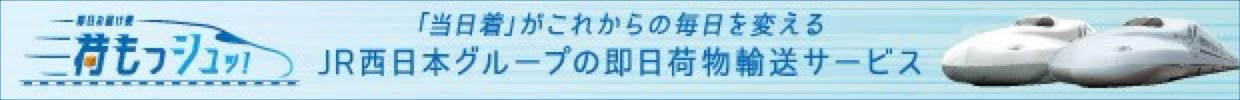イベント本誌主催のDX(デジタルトランスフォーメーション)による物流革新をテーマとするイベント「物流DX未来会議Day2」が18日、会場観覧とオンライン視聴によるハイブリッドで開催された。

▲オープニングセッションに登壇したX Mile代表取締役CEOの野呂寛之氏
X Mile(クロスマイル、東京都新宿区)の代表取締役CEO野呂寛之氏と本誌LOGISTICS TODAY編集長、赤澤裕介とのオープニングセッションでは、2024年問題の現状を再確認。24年も終盤を迎え、懸念された労働力不足、規制強化、技術革新など、業界全体に影響を及ぼす問題が顕在化するとともに、政府による法改正の具体的な中身も示されるなど制度改革も急ピッチで進められている。経営者の舵取りの難しさ、DX(導入も必須となっている状況が共有されるとともに、多様な事業者の事例から、それぞれの進むべき方向性を検討することが促された。
 運送会社、それぞれの未来戦略
運送会社、それぞれの未来戦略
続くセッションには、埼玉県春日部市の運送事業、ピーアール専務取締役の塚田高志氏、SBSホールディングス(HD)LT企画部部長の曲渕章浩氏、フジトランスポート代表取締役の松岡弘晃氏、X Mile物流プラットフォーム事業本部ゼネラルマネージャーの安藤雄真氏が登壇し、未来を見据えた運送会社の新しい戦略をテーマに討論。地場での配送事業、幹線運送事業、3PL事業者に、ITソリューションベンダーと、物流に携わりながらもその事業内容や企業規模もさまざまな事業者ごとの戦略が語られた。

▲セッション2の様子。(左から)LOGISTICS TODAYの赤澤裕介、SBSHDLT企画部部長の曲渕章浩氏、フジトランスポート代表取締役の松岡弘晃氏、ピーアール専務取締役の塚田高志氏、X Mileの安藤雄真氏
主な議論のテーマとなったのは、「人材戦略」「業界再編」「DX」。
業界にとっての課題である、人材採用に関しては、松岡氏から自社所属のトラックYouTuberの活動を入り口として、採用ホームページを経由したドライバー採用活動で、年間500人のドライバー採用の成果を残している事例が示された。それを受けて安藤氏は、人材採用における情報の届け方、届ける場所、届ける情報の中身が人材戦略では大切として、自社ホームページのメンテナンスなども人材戦略の取り組むべき対応であると、今すぐに手を付けられる人材戦略の改善も提起された。
M&A戦略など業界再編が加速している状況についても議論。全国展開に向けてM&Aに積極的に取り組んできた松岡氏からは、近年M&Aには慎重な判断が必要となるケースが増えていると指摘。一見、優良な会社に見えても、将来の賃金未払い訴訟リスクを抱えるような企業も多いことなどが紹介され、M&Aのスピードも変化していると言う。
同じくM&Aで事業拡大してきたSBSグループの曲渕氏からは、個人的な見解としながらも、物流業界内のM&Aだけではなく、DX推進や小売事業の物流参入などを見据えた異業種とのM&Aによる業界再編も進むのではとの見解も示された。
塚田氏は、中小のアナログ管理では実務が追いつかず、M&Aを選択肢とする動きも見られるとする。6万数千社の運送事業者の淘汰も進むとされ、特に中小零細は「生き残り」が事業テーマとなる局面で、M&Aを選択肢とする動きも見られるとする。
こうした運送業界再編下での生き残りに向けては、事業のDXが求められる状況だが、中小零細での導入ハードルは高いと塚田氏は言う。ただ、DXが中小には無縁との見解は否定し、自身の会社でもX Mileのソリューションを使用することで、荷主・元請け企業への交渉力を高めることに成功したこと、今後、共同配送などの拡大においてはDX無くしては実務が追いつかなくなることは間違いないと語った。
松岡氏からも、適正なコスト転嫁を認めない荷主とは取り引きの打ち切りを進めると同時に、ドライバーが各種データを共有できる社内独自のシステム作りに取り組んでいることも明かされるなど、登壇企業それぞれの立場での未来戦略が議論された。
 必要な物流システムを作り上げたエアークローゼットの取り組み
必要な物流システムを作り上げたエアークローゼットの取り組み
3つ目のセッションに登場したのは、エアークローゼットの取締役副社長でロジスティクスディヴィジョンディレクターを務める前川祐介氏。アパレルレンタル事業を展開する同社の事業基盤となるのが、循環型物流プラットフォーム「AC-PORT」であり、荷主の役割りと責任をテーマにした独自の社内物流システムの構築が紹介された。

▲セッション3に登壇したエアークローゼット副社長の前川祐介氏(中央)
創業時から社内に物流専門チームを設置して物流機能を内製化し、レンタルファッションの配送だけではなく、専用物流倉庫や専用クリーニング工場への返送なども物流オペレーションに組み込んだ複雑なシステムを独自に構築していることは興味深い。
こうした独自のプラットフォーム作りに向けては、IT基盤の発想、経営陣のITへの知見も重要として、経営陣のエンジニア経験が生かされているといい、自らが掲げる事業目標達成のために必要な物流システムは自分で作るという姿勢での事業構築期から、事業運用期へと成長を続け、さらなるデータ経営の精度向上を目指している。
今後に向けたAC -PORTの進化では、倉庫の移転拡張や保管、クリーニング、メンテナンス機能の集約や、ロボティクス、自動化での事業拡大を掲げる。また、ユーザー配送手段も契約1社に集約するのではなく、ユーザーにとって使いやすい配送手段を選べるような体制を整える。
さらに、独自開発した物流システム、プラットフォーム機能の外販も視野に入れ、toCだけではなくtoBとしての展開も拡大する。サーキュラーエコノミー、シェア型物流の構築に関して、今後はエアークローゼットが構築したシステムによる「循環型プラットフォーム事業」が基盤となることも想定すべきではないだろうか。
ITをベースに、物流経験者なら二の足を踏むような高度なシステムを、荷主としてすべて内製化し作り上げた同社の取り組みは、まさにCLO選任など、荷主の経営トップが物流を構築する、これからの物流のあるべき姿といえそうだ。
物流の門外漢だからこそ実現できた同社のロジスティクス戦略は、物流に責任を負うべき荷主事業者にとって示唆に富む内容となった。
 CLO選任など、立場の違いを超えた議論
CLO選任など、立場の違いを超えた議論
最後のパネルディスカッションでは、荷主の立場からはエアークローゼット前川氏、運送事業からはNBSロジソル(大分県日田市)の河野逸郎代表取締役、コンサルタント事業からローランド・ベルガーのパートナーでロジスティクス分野の専門家、小野塚征志氏が登壇。メディアの立場で本誌、赤澤編集長と、モデレーターとしてX Mile野呂氏が加わり、物流業界の未来を見据えた、新しいパートナーシップの在り方が議論された。

▲新たに登壇しパネルディスカッションに参加したNBSロジソル社長の河野逸郎氏(左から2番目)とローランド・ベルガーパートナーの小野塚征志氏(中央)
24年問題に関しては、それぞれの立場は違えど、いずれも「チャンス」と捉えており、「全員が変化せざるを得ないことに意味がある」(河野氏)、「今までになかったことを共同課題として取り組める機会」(前川氏)などの認識が示され、小野塚氏からは「ピンチはチャンス、市場のメカニズムが働く環境となることは望ましい」として、適正な事業者が生き残る契機と指摘する。
法改正によって荷主事業者にかかる責任は重くなり、さらに3200社程度と想定される特定荷主の取り組みも急がれるはずだが、「現状、関心を示しているのは、そのうちの3-500社程度では」(小野塚氏)との見解も示された。荷主事業者の立場からは、荷主も選別される局面で荷主の果たすべき役割について議論が活性化されること自体に意義があるとの意見が語られるとともに、荷主の取り組みが重要となる各種の制度変更について「違法行為を許さない」(小野塚氏)こと、不適正な会社が退場するような市場メカニズムを促す仕組みであるとの見解も示された。
また、物流業界での重要キーワードとなるCLO(物流統括管理者)に関しての議論では、明確な経営ビジョン、大局的・俯瞰的な視点、自らの掲げるビジョンを完遂する意志、統率力や調整力など、参加者それぞれの想定するCLO像が示されるとともに、CLOを育てるチーム作りや、CLO設置で荷主との関わり方が変化する3PL事業の未来像にまで話が及んだ。
求められる能力の難易度の高さや要件の多さから、CLO設置の取り組みはまだこれからの状況だが、物流最適化には「社内で声が大きい人をCLOにしたら良い」(小野塚氏)と、生産、調達、営業、管理部門などで発言力のある人材がCLOとして物流の実情を知り、事業課題として解決に取り組めるような考え方での選任や、社内ローテーションなどを通して戦略的にCLOを育てていくことの必要性についても提案された。
また、CLO選任において社内各部門との連携の重要性とともに、荷主の事情を物流・運送事業者が知ること、物流・運送事業の事情を荷主が知ることなど、相互理解やパートナーシップの構築が不可欠であり、ともに解決する姿勢が重要であると提起した。
さらに、相互理解に向けては「見える化」などDXの果たすべき役割は大きく、フィジカルインターネット構築へ向けてITソリューションベンダーにかかる期待は大きい。デジタル化を物流の共同利用、互いの得意領域のシェアリングなどにも生かしつつ、業界全体での連携や理解を深めあうことの重要性が再確認される議論となった。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com