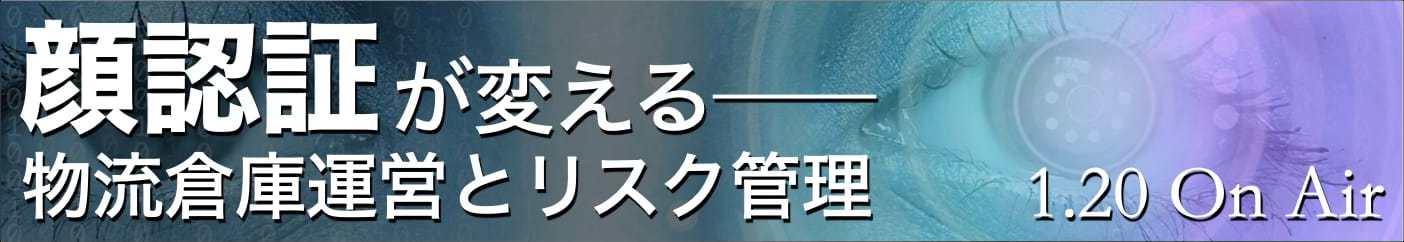話題経済産業省物流企画室課長補佐の大西智代氏は、本紙の取材に対し「これまで経産省は荷主企業への働きかけが十分ではなかった」と率直に認めた。トラックドライバー不足や高齢化を背景に“2024年問題”が深刻化するなか、同省も本格的に物流改革に乗り出した形だ。

▲経産省の大西智代氏
とりわけ注目されるのが、24年度補正予算に盛り込まれた「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業」である。荷主や物流事業者が連携して共同配送や標準化を進める際、設備投資などに対して最大2分の1の補助を行う仕組みだ。大西氏は「規制だけでなく、しっかりと支援も行うことで荷主企業の意識変革を促したい」と語る。
これまで国土交通省が主体となっていた物流行政は、「荷主側の協力が得られにくい」という課題を抱えてきた。こうした現状に対し、大西氏は「輸送や倉庫が担う部分だけでなく、荷主の都合や発注の仕方が物流現場の負担に直結する。そこを変えないと、24年問題の根本解決は難しい」と指摘する。経産省としては、今回の補助事業を通じて複数企業の共同輸送や情報システムの導入を後押しし、荷主にも持続可能な物流実現の当事者意識を持ってもらう狙いだ。25年以降、改正物流法の施行が本格化するなか、同省がどう“荷主主体”の物流改革を具体化していくか注目される。
 「縦割りの壁を超えるきっかけ」、24年の検証
「縦割りの壁を超えるきっかけ」、24年の検証
24年に入り、トラックドライバー不足や高齢化といった従来から指摘されてきた課題が、一層切迫した形で顕在化している。物流危機とも呼ばれるこの状況に対して、国交省が主導する法整備や施策はニュースでも多く報じられてきた。
一方、経産省は日本経済全体を支える省庁でありながら、これまでは「物流は国交省の領域」と見なされがちで、荷主(メーカーや小売など)の動向こそが物流改革の鍵を握るという認識が必ずしも浸透していなかった。
しかし、大西氏によれば、ここ数年で「物流を支えるのは運送事業者だけではなく、荷主企業の意識変革が欠かせない」という省内外の共通認識が高まったという。実際に24年までの間に、国交省や農林水産省と三省合同会議を開いて荷主・物流事業者に対する規制的措置を検討し、改正物流法を成立させるなど、かつての縦割りを越えた連携が形になり始めている。
その背景には、経産省自身の反省がある。「荷主企業へのアプローチが十分ではなかった」という声が省内で上がり、大西氏のように物流企画室で新たな役職や体制を整えた結果、24年を迎えるに至ってからようやく「本気で荷主を巻き込む」方針が具体化されたのである。
 改正物流法、荷主の協力義務化で何が変わる
改正物流法、荷主の協力義務化で何が変わる
24年に施行された改正物流法は、「荷主にも物流維持に協力する義務がある」と明確に打ち出した点で大きな意義を持つ。これまでは、労働負荷やコストを運送事業者側が一方的に背負ってきた構造が黙認されてきたが、この法律を機に、荷主の物流効率化への取り組みを法的根拠をもって求められるようになった。
もっとも、法律だけで企業の意識が変わるわけではない。大西氏は「国としてやる以上、最低限のラインは定めざるを得ないが、さらに創意工夫をもって高みを目指すことも大事になる」と強調する。
実際に、25年度4月からは全事業者に対して物流効率化への取り組みが努力義務として課され、26年度には特定事業者の指定や中長期計画の提出が始まる。まさに荷主企業の姿勢が問われる段階へと進むわけだが、その際に混乱が起こらないよう、ガイドラインや事例紹介をどれほど整備できるかが省庁としての腕の見せどころになる。
 物流効率化実証事業-24年度補正予算の補助制度
物流効率化実証事業-24年度補正予算の補助制度
規制だけではなく、支援策を手厚くすることも経産省が重視している点だ。大西氏が携わる「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業」はその一例で、24年度補正予算に再び盛り込まれ、複数企業が連携して設備投資やシステム導入を行う際の費用を2分の1補助する仕組みになっている。
昨年度の支援との違いは、必ず荷主企業を1社以上含むコンソーシアムであることを条件とし、企業規模を問わず幅広く支援対象にした点だ。たとえば、共通パレットや共同配送の拠点運用、倉庫管理システム(WMS)の導入、あるいはロボティクス活用など、複数の荷主・物流企業・ITベンダーなどがチームを組むケースであれば、補助対象として認められる可能性が高い。
大西氏は「企業同士が連携してこそ得られる効率化が大きい。荷主企業が主導してコンソーシアムをまとめるのが理想だが、3PLなどが動かしやすい場合もある。そこは柔軟に捉えている」と語る。支援を通じて何度か実証を回せば、効果が見えやすくなり、複数企業の連携モデルが急速に普及する可能性がある。
 複数企業の連携がポイント、共同輸送・共通化のメリット
複数企業の連携がポイント、共同輸送・共通化のメリット
物流現場では「トラック積載率の向上」や「共同輸配送」「在庫や保管拠点の共有化」などが昔から言われてきたが、実際には互いに競合する企業間の連携が進まず、業界で個別にシステム投資を行うだけで終わるケースが多かった。

しかし、24年問題による輸送能力のひっ迫や労働規制の強化に伴い、「今なら共同で取り組まなければ乗り切れない」という危機意識がかつてないほど高まっている。そこで、経産省が“後押し”として複数企業を支援する仕組みを整えたことは、大きなインパクトを生むと期待されている。
大西氏によれば「規模や業種を越えて複数社が同じパレットやシステムを活用できれば、人手不足の解消にもつながるし、輸送コスト全体が下がる。トラックドライバーや倉庫作業員の負担軽減にも寄与できるはずだ」とのことだ。現場の細かいオペレーションにまで手が届く支援であれば、企業が安心して取り組めるだろう。
 CLO導入に込める思い、企業経営と物流の“共創”
CLO導入に込める思い、企業経営と物流の“共創”
改正物流法では「CLO(チーフ・ロジスティクス・オフィサー)の設置を促す」文言も含まれ、経産省は企業内で物流を経営戦略の一部と捉えるためのキーパーソンを明確に示した。
大西氏は「まず『CLOって何をする人?』という段階から始まっているが、本来は荷主企業の中で“物流をコストセンターではなく、事業を成長させるエンジンとして位置付ける”役職にしたい」と語る。人材育成や情報発信の拡充にも意欲を見せており、「時間と予算が許せば、国内外のCLO事例を集めて企業が学べるプラットフォームを作りたい」とのことだ。
物流が全社的に最適化されれば、リードタイム短縮や在庫圧縮、サプライチェーン全体の競争力強化など、経営面のメリットは大きい。24年以降も“物流”をキーワードに自社のビジネスモデルを根本から見直す企業は増える見通しであり、CLOの導入によってその動きを後押しするという狙いがある。
 2024年問題の行方:補助事業が生む現場インパクト
2024年問題の行方:補助事業が生む現場インパクト
いわゆる“2024年問題”では、ドライバーの時間外労働規制が厳しくなることで運送コストが上昇し、場合によっては配送便数を減らさざるを得ない事態が懸念されている。すでに一部では商品の欠品や納期遅延なども起こり始め、メディアの報道などで消費者の耳にも入るようになった。
経産省がこの問題の打開策として注目しているのが、先述の補助制度による複数社連携モデルの創出だ。輸配送ルートの共同化や車両稼働率の向上を目的とする取り組みに、物流現場で使える最新技術を掛け合わせれば、総合的な効果が期待できる。
大西氏は「24年問題の本質は“コストカットのみに頼った時代の終焉”にある。今こそ『効率化』と『適正な賃金』を両立させ、労働環境を整える好機だと思う」と語る。安価な運賃に頼るビジネスモデルを見直す企業が増えれば、それだけ社会インフラとしての物流が安定するという見立てだ。
 25年以降に待ち受ける本格施行:特定事業者指定へのステップ
25年以降に待ち受ける本格施行:特定事業者指定へのステップ
24年を“助走”と位置付けるならば、25年以降がいよいよ物流改革の本格ステージとなる。改正物流法に則り、25年4月から全事業者には物流効率化への取り組みが努力義務として課され、26年度からは特定事業者が指定されて中長期計画の提出を求められる。
経産省としては、そこで企業が「どこから手をつければいいのか分からない」と混乱しないよう、ガイドラインや事例集を早めに整備しておきたい考えだ。24年度補正予算の助成を受けた企業の成果が具体的な形で出れば、ほかの企業も同様のプロセスを踏襲しやすくなるため、まずは補助事業の成功事例を蓄積する段階に力を入れるという。
大西氏は「25年や26年の段階で戸惑いが広がるようなら、せっかくの法改正や支援策も生きてこない。そこをスムーズに乗り越え、企業同士が自然発生的に連携し始めるような環境づくりを目指したい」と語る。
 省庁連携の課題、三省合同会議からの“次の一手”
省庁連携の課題、三省合同会議からの“次の一手”
物流行政は国交省が主導し、農水省が食品・農産物系物流で関わり、そして今回経産省が“荷主”という視点で深く関与する形が整ってきた。大西氏自身、「三省合同会議を一過性に終わらせないことが重要」と強調している。
物流を取り巻く法規制は幅広いが、民間企業からすれば「省庁の垣根を超えて一気通貫で協力してほしい」と望むのが普通だ。こうした声に応えるには、日常的な情報交換やワンストップ相談窓口の整備などが不可欠であり、現場で試験的に進めている施策もあるという。
大西氏は「私たちは条文を詰めるだけで手一杯になるときもあり、現場ニーズへのフォローが後回しになってしまう。そこは深く反省しており、疑問や要望にすぐ答えられるような連携体制が必要だ」と語る。次の一手としては省庁共同の説明会や勉強会なども検討されており、荷主や物流事業者が新しいシステムや投資を検討する際に役立つ情報を迅速に提供できる環境づくりを目指している。
24年は、日本の物流改革における大きなターニングポイントとなった。経産省が従来の“縦割り”を乗り越え、国交省・農水省と三省合同体制を築き、改正物流法の施行で荷主にも協力を求める明確な根拠を得たからだ。大西氏が担う補助制度「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業」では、企業同士の連携を促進する仕組みを整えつつ、実際の導入効果を“見える化”して横展開を目指している。
25年、そして26年にかけては、特定事業者の指定や中長期計画の提出といった本格的な運用フェーズに移る。CLOを設置し、物流を経営戦略の一角として位置付ける企業が増えれば、物流はコストセンターではなく“経済基盤を支える成長エンジン”へと転換していくだろう。
大西氏は「規制と支援だけで改革が完結するわけではない。荷主企業が当事者意識を持つことで初めて、“2024年問題”を好機に変えられる」と強調する。企業間連携モデルが拡大し、ドライバー不足や長時間労働など深刻化する課題を乗り越えた先には、国際競争力も見据えた新たな物流の姿があるかもしれない。このインタビューを通じて見えてきたのは、経産省が自らの“反省”を踏まえて着実に“転換”を図ろうとする姿勢だ。

◆一問一答
──物流を切り口に荷主企業と接点を持つことは、経産省としてはあまりなかった印象がある。仕事の内容にも変化はあったか。
私が着任したのは23年の夏頃。その頃から、物流の問題に正面から向き合う流れができ始めた。当時の中野剛志消費流通政策課長兼物流企画室長が「今まで経産省は荷主に対して十分な対応をしてこなかった」と反省していたことが大きな契機になったと理解している。そこから国交省の課長や関係省庁とも連携し、三省合同会議につながる形を作ることができた。
──着任した頃と比べて、荷主企業との付き合い方は変わったか。
今は改正物流法が法律として形になった。荷主企業に対して何もない状態で「何かやってください」とお願いするより、「こういう法律があるので、これに取り組んでください」と明確に伝えられるようになったことは、大きな進ちょくだと感じている。
──印象的だったのは、国の立場の話にもかかわらず「反省」という言葉が出てきたことだ。それは具体的にどういう内容か。
まず、「物流の問題は国交省がやればいい」と考えられていたことが大きい。いわゆる省庁の縦割りの中で「物流は国交省の担当」「経産省には関係ない」という状態が長い間続いていた。ほかにも、「経産省が物流インフラなどエッセンシャルサービスに十分な注意を向けてこなかった」との反省がある。当時の中野(剛志、)課長が雑誌記事で「物流の2024年問題の元凶は経産省」と答えていたのを見た人もいるかもしれない。
──個人的にはどのように思うか。
スーパーの棚に並ぶ商品や自販機で買える飲み物など、「誰かが運んでくれている」という事実を当たり前に捉えすぎていた。そこが揺らぐと経済活動は成り立たないのに、意識が向いていなかった点を個人的にも深く反省している。
──経産省としての「気づき」や、「ここでやらなければならない」という行政の転換点を意識したということか。今後は経産省が直接荷主企業に働きかける役割がさらに重要になると思うが、どう考えているか。
大きなプレッシャーを感じている。しかし、経産省は「経済活動の活性化」をミッションとする省庁だ。その基盤となる物流をサプライチェーンという大きな視点で捉え、持続可能にする必要がある。民間でも、物流分野が主軸ではなかったプレイヤーが2024年問題を受けて「自分たちも物流ソリューションを提供できるのではないか」と考え始めたり、業界を越えたいろいろな企業が連携して「一緒に何かやろう」という動きが出てきている。経産省としてできることは限られるかもしれないが、こうした民間の取り組みを後押ししたり、必要に応じて主導することで、将来的に良い形を作れると期待している。
──2024年問題に向き合うなかで、三省合同会議が大きな役割を果たしたと感じる。一過性に終わらせず、強化・発展させる必要があるのではないか。
三省合同会議は改正物流効率化法を中心とした議論がメインだ。他にも下請法の改正や実運送体制管理簿の話など、事業者からすると「物流だけでも、こんなに関係する法規制があるのか」という状況になっている。民間企業は法律や省庁の垣根を超えて最適なシステムやソリューションを考えているのに、私たちは条文を一つひとつ詰めるだけで手一杯で、法律の理解促進や連携にまで十分手が回っていない部分もある。そこは反省点だ。まずは関係省庁の間で普段から情報交換を密にし、疑問にすぐ答えられるようにしていきたい。
──国としてやる以上、「ここまではやってほしい」という最低ラインを示さざるを得ない。そのうえで「さらに創意工夫で高みを目指してほしい」と後押しすることが大事だろう。こうした取り組みを後押しするために、経産省として現在行っていることや始める予定のものがあれば教えてほしい。
たとえばCLO(チーフ・ロジスティクス・オフィサー)を置くことは、法律を通じた野心的なメッセージだ。「荷主の企業にはCLOを設置してほしい」という思いがあるが、「CLOとは何か」「どんな役職で、具体的にどんな業務を行うのか」といった疑問を持つ人は多いだろう。もし予算などが許せば、国内外のCLO事例やCLOになるまでの経歴、具体的な業務内容などを整理して情報発信をしていきたい。また、人材育成も含め、JILS(日本ロジスティクスシステム協会)やJPIC(日本フィジカルインターネットセンター)などでは既に勉強会や協議会が立ち上がっているので、そこにも積極的に連携していきたい。
──以前のイベントで、大西氏が「もし物流効率化に取り組んでいない荷主がいれば、きちんと対応していく」という強いメッセージを発していたのが印象的だった。今後、荷主にルールを守ってもらうために、一種の“ファイティングポーズ”も必要なのではないか。
改正物流法の趣旨はまさに「物流を維持するために、荷主も協力せよ」ということだ。安ければ何でもいいというコストカット型の経済ではない。現場で働く人の無駄な作業をなくすという意味での効率性や、サービスを持続させる意識を持ってほしいというメッセージである。下請法などにも通じるが、「とにかく安くやってほしい」という発想はどこにでもあり、結果的に物流など経済の土台を支える社会インフラが崩れる危険性がある。企業全体でエッセンシャルサービスの維持をちゃんと見て、考えるべき時代に入ったはずだ。適正な賃金が働いた人に渡る社会を企業ごとに心がける必要があるし、利益追求一辺倒では回らなくなってきていると感じている。
──補正予算が成立したことで、特に荷主向けの補助金が注目を集めている。改めて趣旨や経緯を聞きたい。
令和6年度の補正予算で「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業」という枠を確保した。昨年度も実施した「荷主による物流効率化の設備投資を進めるための補助金」であり、今年度は複数企業が連携し、荷主企業が1社以上含まれることを条件に、企業規模を問わず2分の1の補助率とする予定だ。たとえば複数の荷主が共通パレットを導入したり、共同配送の仕組みをつくる際のシステム投資などを想定している。
──荷主企業を必ず含むコンソーシアムに、物流企業やITベンダーなどが加わるのはOKか。大手3PLが旗振り役になるケースもあり得るのか。
あり得る。基本的には荷主主導が望ましいが、現状として3PLが動かしやすい場合もあるだろう。そこも含めて認める方針だ。
──補助金を受けた事業者がトライして「こういう効果があった」と実証できれば、次につながる。WMSやロボットなど、協調したほうがいい領域もあると思うが、それらも対象になるのか。
標準化や共通化にメリットがある取り組みであれば、可能性はある。荷主がきちんと現場を提供してデータを測定し、効果を検証できることが大前提だが、新しい技術を物流に転用して効率化できるのであれば、既存技術に限定せず申請できる。
──他産業の技術やアイデアを物流に転用するようなケースでも対象になるのか。
物流施設や倉庫、トラックドライバーへの具体的な効率化効果が見込めて、きちんと試算・検証できれば対象になり得る。
──2025年度や2026年度に向けた施策はあるか。24年度の取り組みをさらに拡充するイメージだろうか。
まずは荷主の物流効率化に向け、規制的措置と支援的措置を両輪でしっかり進めることが重要だ。規制的措置としては、改正物流法の執行を通じて取り組む。2025年4月からは全事業者に対して物流効率化の努力義務が課され、2026年度には特定事業者の指定や中長期計画の提出が行われる予定である。企業の関心はそこからさらに高まるはずなので、そのときに戸惑わないようガイドラインや指針を整備する考えだ。支援的措置については、先ほどの補正予算を確実に執行することが最優先だと思っている。