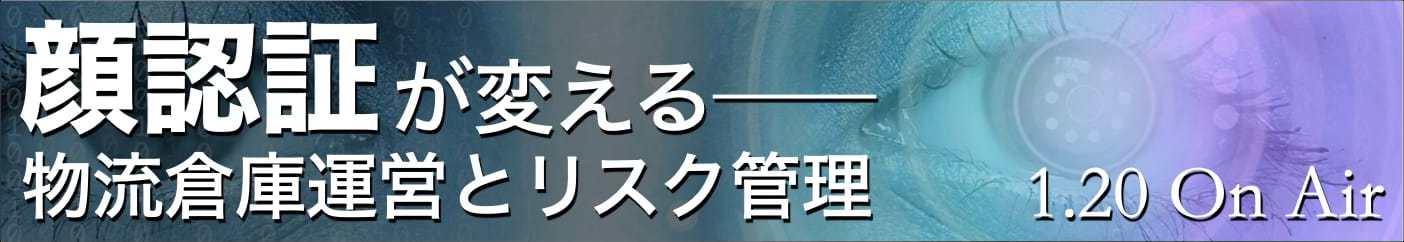ロジスティクス運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)は11日、「TDBC Forum 2025」を開催し、その中のパネルディスカッションに菱木運送(千葉県匝瑳市)社長の菱木博一氏を迎え、「受け身から提案へ、荷主を動かした物流会社のシナリオとは」を公開した。同社は長年の2024年問題対策としてトラックドライバーの待機時間削減とエビデンス創出に挑み、能動的アプローチで業界構造の変革に貢献する姿勢を示している。
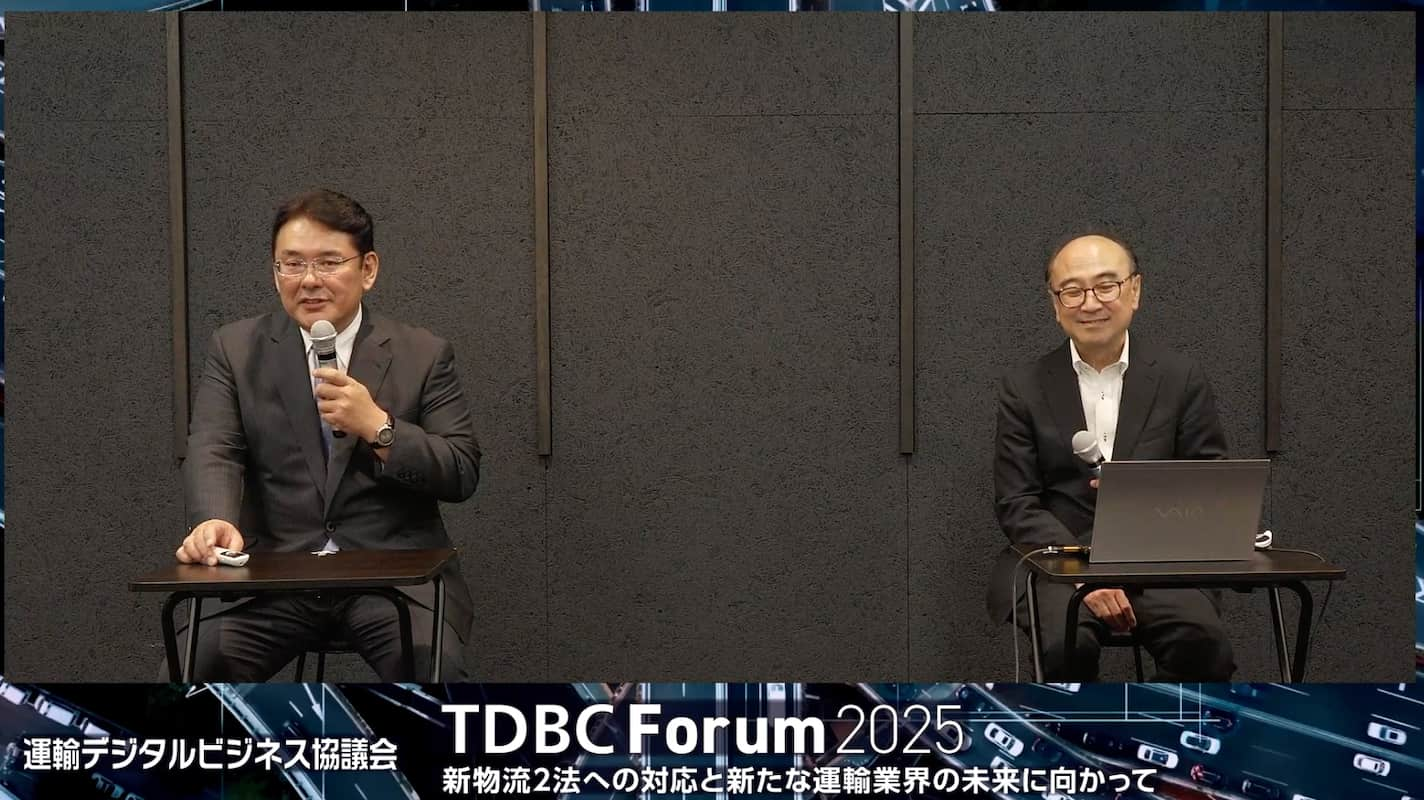
▲(左から)菱木博一社長、TDBC代表理事の小島薫氏(出所:TDBC)
菱木運送は10年以上前から「改善基準告示」順守を目指し、乗務員時計というシステムを運用している。そのシステムでは出勤から退勤までの全行程をリアルタイム表示でき、ドライバーが自らの状況を直観的に確認できる。菱木社長は「自社努力で順守可能な運行管理を続けたが、最後まで壁となったのは待機だった」と語った。待機時間は運行終了後でしか把握できなかったが、乗務員時計の管理者画面でリアルタイムに経過時間を可視化できるようになり、その場で状況を荷主側に改善要求できる仕組みをつくった。
さらに、菱木社長は重要なポイントとして、待機時間の正確な把握と「エビデンス」の創出を挙げた。従来はドライバーの手入力データによる集計しかなかったが、これに加え車両の位置情報から自動で待機場所・時間を算出できる方法を構築した。2つの集計方法によって、配車現場での誤差やデータの信頼性差異が明らかになった。例えばドライバー入力では13~14%の待機割合だったが、車両データ基準では30分以上の待機が2回に1回発生していることもある。こうして整えた正確なエビデンスは、荷主への説明や改善要求の根拠となる。営業開始時刻を基準に、事故都合・荷主都合を切り分けて集計し、客観性の高い証拠として運用している。
菱木社長は待機問題の解決を「荷主とのパートナーシップ形成のきっかけ」とした。集計した待機情報を曜日別・時間帯別に分析し、荷主ごとに経緯や発生原因までデータで説明する。単なる請求や改善申し入れだけではなく、荷主の現場負荷や作業員数の増減も視野に入れ、「ともにメリットを出す提案」に昇華する姿勢を明らかにした。「エビデンス」をそろえて能動的に交渉することで、一部顧客からは待機改善に取り組む姿勢や待機料支払いへの理解を得ている。
菱木社長は「待機、エビデンスにこだわる能動的行動を推進し、最終的に荷主行動の変容や持続的改善サイクルの発動を現場で実現している。これから運送会社が業界標準として、確実な証拠を示し能動的に提案することが物流全体の質と持続性を高めるうえで不可欠だ」と語った。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。