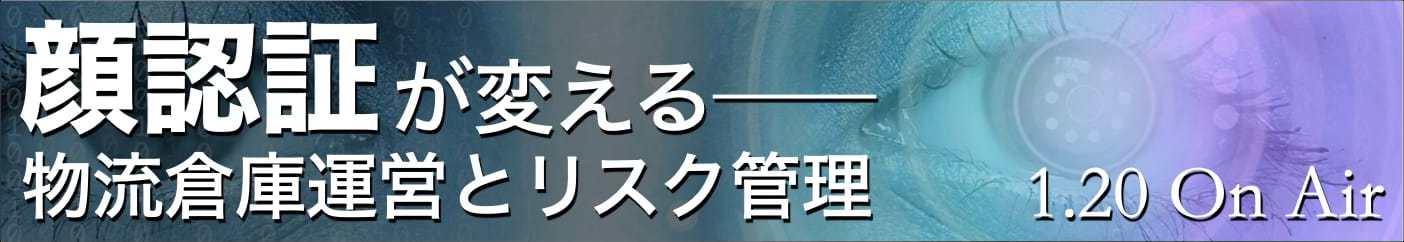話題近年の野村不動産による物流展示会の出展は、ほかのデベロッパーと一線を画すものとなっている。最新の物流施設開発動向をパネル展示するだけではなく、施設を舞台とした物流効率化、自動化の提案に重きを置き、出展ゾーンに関しても物流不動産の紹介エリアではなく、ソリューションの紹介ゾーンへ出展するなど独自のスタンスを貫く。
9月10日から12日にかけて東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」。この日本最大級の物流展示会においても、同社はひと際巨大なブースを「物流管理・システム化ゾーン」に構築する。その大きさは展示会最大規模となる810平方メートル・90小間に達し、これは昨年の同社ブースの3倍以上という圧倒的スケールだ。単なる最新施設紹介にとどまらない、「物流の最適化を提案する存在」としての意志を、空間そのものに凝縮させる姿勢だ。
今回、展示会を担当する、都市開発第二事業本部から物流事業部事業企画課の山崎陽世里氏、物流営業部ソリューション企画課の朝倉南氏、物流事業部事業企画課の新入社員、山田千夏氏から話を聞いた。
 展示ブースが出張版Techrum Hubに
展示ブースが出張版Techrum Hubに
今回の展示では、野村不動産が千葉県習志野市に開設している共創型実証施設「Techrum Hub」(テクラム・ハブ)のコンセプトを、そのまま展示会場に持ち込む。「習志野にある常設施設で実証している連携ソリューションの数々を、リアルな空間で来場者が体感できる『出張版テクラム・ハブ』として再現する」(山崎氏)という試みだ。ソリューションやマテハンなどを手がける企業同士の共創コンソーシアム、テクラムに参加するパートナー企業数は8月時点で120社と拡大し、「今回はその中からパートナー企業16社が参加して、これからの物流の姿を展示会場に完全再現する」(山崎氏)と意気込みを語る。野村不動産にとって過去最大規模となる出展スペースは、まさにテクラム・ハブの再現に必要だったもの。今回の出展に参加するテクラムのパートナー企業も昨年の11社から増加し、より多様な工程や課題解決のための提案が実現する。

▲野村不動産「INNOVATION EXPO」出展ブースにはTechrumパートナー企業16社が参加
 入庫から開梱まで、庫内工程間の自動連携をデモ実演
入庫から開梱まで、庫内工程間の自動連携をデモ実演
巨大ブースの出展の目玉となるのは、「入荷から出荷まで、物流作業工程の全域にわたるソリューション連携の実演」(朝倉氏)だ。トラック接車から出荷までを連続的に実演し、物流の各工程で、どのようなマテリアルハンドリング機器が稼働し、どのように次工程に繋がっていくのか、その一連の流れを、実際の倉庫空間さながらに再構成する。
たとえば「入荷ゾーン」では、荷台ウイングの自動開閉機構を備えたコンテナ車両を模した実機が持ち込まれ、そこからの自動フォークリフト(AGF)による荷下ろし実演がスタートとなる。荷下ろしされた荷物はそのまま、AGFが自動で次工程へと搬送する。マテハン以外にもバース予約・受付システムのソリューションベンダーも参加しているので、ハードとソフト両面からの荷待ち・荷役時間削減の具体的イメージが再現される。
次に連携する「デパレタイズゾーン」では、AGFが搬送してきた荷物について、パレット単位の積載物を箱単位に分解する。協働型ではなく、人手を介さずに自動でデパレタイズ処理を進めるロボット稼働も実演される。
箱単位にパレタイズされた荷物は、次に「開梱」の工程へと自動で引き継がれる。この「開梱ゾーン」では自動開梱機が連携して箱の天面を自動でカット、安全かつ正確な商品単位の管理・保管できる体制へと移行する。「ここまで入荷から荷下ろし、搬送、デパレタイジング、開梱までがすべて無人・自動で連携し、スムーズにつながっていく様子をデモ実演で披露。ぶつ切りの個別工程ではわかりにくかった、より有効な自動化機器連携の実現性を直感的に体感できる展示となる」(朝倉氏)
さらに「保管ゾーン」では、棚搬送型のGTP(Goods to Person)方式と、高密度ラックとAGV(無人搬送車)の連携方式が隣接して展示される。どちらも保管とピッキングの機能を担う自動化ソリューションだが、商品荷姿やオーダーの特性によって、どちらが適切かも比較・検討できるような配置と説明が加えられている。
「仕分けゾーン」においても、異なる2種類のソリューションを比較できる。1つは高速仕分けロボットによるフルオートメーション型。もう一つは、人の判断と自動化を組み合わせた半自動型のGAS(Gate Assort System)で、正確性と柔軟性のバランスを取ったアプローチだ。自社の現場に求められる最適な仕分けツールは何か、スピード、柔軟性、設置スペースなど、多様な観点から現実的な選択肢をその場で比較検証できる。
最終工程では、袋梱包機や、大量コード一括読み取りシステムで検品を支援するソリューションも出展し、最終出荷工程まで「物流を流れとして捉える」というテクラムの思想を、来場者が体感できるように構成されている。また、倉庫管理システム(WMS)などのソフトウエア、パレットシャトル自動倉庫、自動化機器導入効果を事前にシミュレーションするツールなど、来場者が考えるそれぞれの自動化だけではなく、こんなやり方があるのか、こんなシステムが有効なのかなど、多様な工程ごとに新しい気づきを得る機会となることも期待される。
 物流現場の見直し、気づきを促す展示構成
物流現場の見直し、気づきを促す展示構成
「工程単体」ではなく「連携と流れ」に重きを置き、さらにその実演によって来場者の理解を後押しする展示構成は、まさにテクラム・ハブが目指すもの。各工程の技術を横に並べるだけでなく、それぞれがどのように接続され、効率化の連鎖を生むのかが明示されている。
たとえば保管工程でわかるのは、単なる棚搬送や高密度保管の技術的差異ではなく、それが入荷-出荷のリードタイム全体にどう影響するかという視点である。仕分け工程においても、「どちらが優れているか」ではなく、「自社の運用条件で何が最適か」を自ら判断できるように導く。
ソフトウエアの紹介も、自動化ハード機器・マテハンとの統合された動作を通じて、運用効果を明確に提示し、個別説明では伝わりにくいソフトの導入イメージが、よりわかりやすく理解できる仕組みになっている。
 展示会から始まる、最適化への飽くなき検証
展示会から始まる、最適化への飽くなき検証
朝倉氏は、「まずは展示会で、物流の未来を体験してもらいたい。そして、もっと詳しく知りたい、ほかのソリューションも見てみたいという方は、ぜひ習志野のテクラム・ハブにもご来場いただきたい」と語る。展示会での気づきを入口として、より多くの参加パートナー企業のソリューションが揃うテクラム・ハブでさらに深く検証し、継続的な連携と共創への導線とする姿勢である。
庫内の長い工程での連携をわかりやすく解説するため、プロの実演販売士も参加する。会場内ではスタンプラリーなどの参加型企画も用意され、出展パートナー企業のソリューションを広く回遊しながら体験できるよう設計されている。入社して間もない山田氏も、「より一般の来場者に近い目線で、参加パートナー企業それぞれの良さをアピールできるように工夫を練り上げている」といい、未来の物流を支えるであろう人材のアイデアも生かされた展示となる。「パートナー企業同士の連携も、出展に向けた話し合い、協議などでさらに深まったのでは。これをきっかけにまた新しい共創アイデアが広がるかもしれない」(朝倉氏)
山崎氏は、「今回展示会で紹介したいのは、野村不動産が見据えている物流の未来そのもの。野村不動産の新たなコンセプトムービーも初公開予定で、同社が目指す未来像をビジュアルでも訴求する」と、次へと広がる展示、未来へつながる展示であると呼びかける。
 物流最適化の提案者としての姿勢、より明確に
物流最適化の提案者としての姿勢、より明確に
野村不動産が描く「物流の未来」とは、単なる倉庫開発ではない。人と技術、ハードとソフトをつなぎ、物流センターの内外を貫くサプライチェーン全体の効率化に貢献することである。展示会のテーマ「物流を止めない。社会を動かす。」を体現するこの取り組みは、逼迫する物流現場や人手不足といった課題に対する具体的な解であり、持続可能な社会づくりへの一歩でもある。
今後、野村不動産は物流不動産の枠を超え、業界全体を巻き込んだ価値共創の中核を担う存在として、「物流最適化の提案者」という立場をさらに鮮明にしていくだろう。

▲左から、朝倉南氏、山崎陽世里氏、山田千夏氏