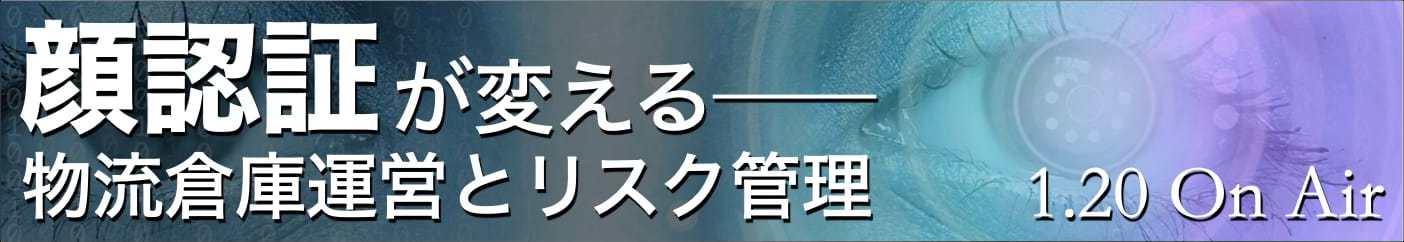行政・団体国土交通省は21日、第5回「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」をウェブ会議形式で開催した。次期大綱の策定に向け、荷主や物流事業者、自治体など各界の委員から、物流の現状と課題を踏まえた多角的な提言があった。議論では、フィジカルインターネットの推進やデータ基盤整備といったDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略に加え、サプライチェーン全体でのコスト負担のあり方や納品リードタイムの延長など商慣行の見直し、港湾・空港の国際競争力強化が主要な論点として浮かび上がった。
自治体からは、インフラ整備を核とした新たな物流網構築の動きが示された。京都府城陽市は、新名神高速道路の整備に合わせ、全国で初めて高速道路インターチェンジに直結する次世代型物流拠点の整備計画を説明。この施設は、自動運転トラックが一般道を経由せず直接アクセス可能な設計で、今後の普及を見据えた切り替え拠点としての活用を目指す。同市は、こうした基幹物流施設を全国に整備する必要性を訴え、国に対して広域的な取り組みと補助金など優遇制度の新設を要望した。
荷主企業からは、効率化に向けた具体的な取り組みと制度改革への要望が相次いだ。三菱食品は、物流DXを「可視化」「最適化」「オープン化」の3段階で進める戦略を紹介。フィジカルインターネットの実現に向け、GPSデータや運行データの標準規格整備、データ帰属に関するルール明確化の重要性を指摘した。
イオングローバルSCMは、小売業の視点から、納品のパレット化による荷受け時間の大幅な短縮効果(一例で1時間から18分へ)を報告し、T11型パレットへの統一を推進する考えを示した。また、ダブル連結トラックの通行規制緩和や、輸送トラックに対する高速道路料金の無料化といった大胆なインフラ・制度面の支援を求めた。JA全農は、青果物や畜産物の中継輸送の取り組みを紹介し、増加する物流コストを生産者だけでなくフードチェーン全体で適正に負担するルール作りを提言した。
経済界からは、よりマクロな視点での課題が提起された。日本経済団体連合会(経団連)は、ドライバーの負担軽減のため、納品リードタイムの延長など幅広い関係者の意識改革が不可欠だと強調。環境負荷の少ない内航海運や鉄道へのモーダルシフトを促すため、J-クレジット制度などを活用し、荷主に経済的メリットを提示する仕組みを提案した。国際競争力の分野では、日本の港湾のコンテナ取扱個数の順位低下に警鐘を鳴らし、船舶の大型化に対応するための港湾の選択的整備や、成田・羽田の一体運営による国際航空貨物の迅速化などを急ぐべきだと訴えた。
日本船主協会も、地政学リスクの高まりを背景に、国際海上輸送の安定確保の重要性を訴え、ゼロエミッション船の導入支援や船員不足に対応するための国による育成支援の強化を求めた。意見交換では、現在の「店着価格制」では着荷主に物流を効率化するインセンティブが働きにくいとの問題提起があり、配送品質に応じて価格が変わるなど、物流費を別建てで考える商慣行への転換や、消費者の行動変容を促す必要性についても議論が及んだ。
検討会は次回、9月下旬に開催し、論点整理と提言に盛り込む事項の検討を進める予定だ。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。