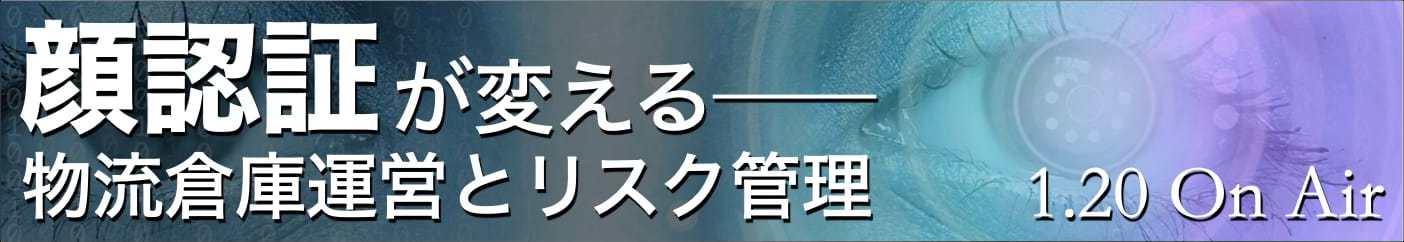ロジスティクス本誌編集部の記者たちが今週注目した物流ニュースを取り上げ、裏側の背景や今後の影響について座談会形式で語り合いました。記事本文だけでは伝えきれない現場の空気感や取材の視点を、読者と共有するのが狙いです。11月下旬の11月22日から28日のトピックを整理してみましょう。
◇
 労働力不足は「現象」、インフラ共有で解く物流未来
労働力不足は「現象」、インフラ共有で解く物流未来
記者A「人手不足はローカルな事情でありつつ、国際的に共有して解決すべきテーマだね」
記者C「ほかの国でも人手不足が進んでいるとなると、働き手によりよい条件を出せる国、機械や自動化でカバーできる国が伸びる。中国は機械化、自動化のスピードが速いし、日本も規制にかまけて悠長に構えていると置いていかれてしまう」
記者A「『足りないなら外国人ドライバーを連れてくればいい』みたいな発想だけだと、国際競争には到底勝てない。省人化のための自動化や機械化にどこまで本気で振り切れるかが問われてるのに、日本はトラックの自動運転一つとっても、日本発の技術にこだわりすぎ。そんなことをしていたら、周回遅れになってしまうよ」
記者D「日本の場合『細かすぎ』『過剰すぎ』みたいなサービスレベルが足かせになっている部分もあるよね」
記者B「ヨーロッパはユーロパレットのように、早い段階から標準化進めている。対して日本は自由競争に任せた結果、個社最適と不合理が積み上がってしまっている。国際物流の中で主導権を握れなかったら、周回遅れでは済まなくなるかもしれない。どこかで“攻め”に転じて、イニシアチブを取りにいかないと」
記者C「誰が旗を振るのかも大きいよね。ヨーロッパは青果物の規格も箱も物流側が主導して決めていったから効率化が進んだけど、日本は生産者サイドの事情が優先されがちで、標準化が遅れている面がある」
記者D「運ぶ側がもっと声を上げて、ルールづくりに踏み込んでいかないと、フィジカルインターネットどころじゃないよね」
 清涼飲料5社が共同で物流改革、賞味期限緩和も
清涼飲料5社が共同で物流改革、賞味期限緩和も
記者D「その“旗振り”という意味で、今週もう一つ注目したのが清涼飲料水5社の共同の取り組み。賞味期限の表示緩和を含めて、物流改革に向けた取り組みを業界横断で進めていく。これまでは商慣行とか取引慣行の“タブー”みたいな扱いで、なかなか触れられなかったところに複数社で踏み込んでいる」
記者B「メーカー単体で見ると損に見えることにもあえて踏み込んで、物流に寄り添う動きが出てきているのは大きいと思う」
記者C「ここ数年、賞味期限表示を“日”から“月”に変えるとか、返品ルールを見直すとか、フードロスを抑えつつちゃんと運べるようにする工夫は地道に増えてきているよね。それを今度は飲料5社が一緒にやりましょうという話になっているのは、さすがにインパクトがある」
記者A「もう一歩踏み込むなら、パッケージや容器のデザイン段階から“物流目線”を入れてほしいね。ペットボトルやキャップの形状はマーケティングの武器でもあるから、各社が競争するのは当然として、そこにも“標準化してよいところ”と“差別化すべきところ”の線引きを入れていく必要がある」
記者D「いわゆる“Design for Logistics”の発想だね。製品開発や生産領域まで巻き込んだ上流からの見直しが進んでいくと、共同物流の効果も一段上がるはず」
記者C「合わせるところは合わせて、競争するところは競争するという動きが、いろんな業界でようやく動き始めている」
記者B「輸送の共同化だけじゃなく、ボトルのリユースやリサイクル、資材の共通化まで踏み込めば、コストだけでなくブランド価値や社会貢献にもつながる。そこまで含めて“共同○○”の時代に入っていくんだろうなという感触はあるね」
 運送事業137手続きをオンライン化へ、国交省
運送事業137手続きをオンライン化へ、国交省
記者A「運送事業に関わるデータがきちんとデジタル化されていれば、指定された項目に沿って書類を組み立てる作業自体は、生成AIやAIエージェントでかなり代替できる。今までそれを代行していた行政書士は、むしろ“運送事業向け申請AIエージェント”をつくって売る側に回ってもらいたい」
記者B「トラック新法の実効性という意味でも、電子化はセットで進めないと回らないよね。トラック運送業の事業許可の更新を紙と人力だけで6万社分こなすのは無理。せっかく始まる制度を維持するためにも、電子化とAI活用はドシドシ進めていかないと」
記者C「事業者側は日々の運行データや点呼記録をちゃんとデジタルで残し、行政側はそれを前提に監査や巡回指導のやり方を変えていく。その上で、AIをどう使うかという議論に乗せていかないと、制度だけ作っても現場が追いつかない」
記者B「物流業界も“AIアンバサダー”みたいな役割を社内に置く企業が出始めているし、どこかで腹をくくってAIと共存する道を探さないといけないね」
 佐川急便が物量急増で配送遅延、配達通知を停止
佐川急便が物量急増で配送遅延、配達通知を停止
記者A「2週間くらい前から佐川側の現場で“年末ヤバそう”という話はちらほら聞こえていたけど、このタイミングで正式に荷受け制限の話が出てきた。年末の繁忙期本番はこれからなのに、すでにこの状況とは驚いた」
記者C「クリスマス前に一発大きく売りたい小売側の事情は分かるけど、ブラックフライデーで各社のセールが同じタイミングに集中しすぎているのは問題」
記者A「ニュースのコメントで“消費者は余裕を持って注文を”みたいな呼びかけも出ているけど、売る側にも何かしらのルールが必要でしょう。波動を平準化する努力目標みたいな枠組みを荷主側にも課していかないと、毎年同じことを繰り返すだけになってしまう」
記者C「この問題こそ、荷主側の意識変革とルールメイクがセットじゃないと解決しないよね。物流側だけに“がんばってくれ”と言っても、キャパは物理的に増えない。どこまでを“商売の自由”として残して、どこから先を“社会インフラを支える責任”として調整していくのか。今回のことをきっかけに、その線引きを社会全体で議論していかないとね」
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。