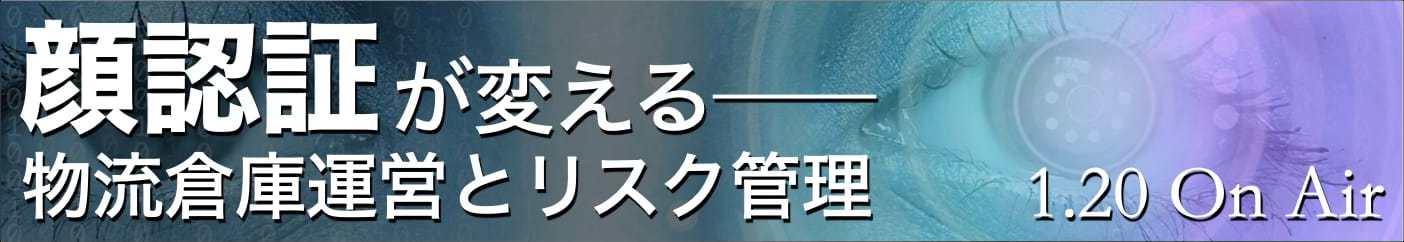ロジスティクス本誌編集部の記者たちが今週注目した物流ニュースを取り上げ、裏側の背景や今後の影響について座談会形式で語り合いました。記事本文だけでは伝えきれない現場の空気感や取材の視点を、読者と共有するのが狙いです。11月下旬の11月18日から21日のトピックを整理してみましょう。
◇
 特積み4社が東阪間で企業横断中継輸送「baton」実証
特積み4社が東阪間で企業横断中継輸送「baton」実証
記者A「一番印象に残っているのは、昨日の『baton』の共同配送の話かな。2社間の共同配送の実証実験ならいくらでも例があるけれど、今回はもっと大きな枠組みで複数社が組んでいこうとしているのがポイント。2月にまず共同配送を走らせると言っていたけれど、その先にルールづくりや仕組みづくりをどこまで積み上げられるか。フィジカルインターネット的な世界観にどれだけ近づけるのか、期待半分、本当に回るのかという疑念半分で見ていきたいね」
記者B「共同運行の話自体は90年代後半から延々とやってきてて、路線各社が余った荷物を寄せ集めて走らせるスキームを組んできたけれど、出発式までは盛り上がっても、その後スケールした例はほとんどないのが正直なところ。今回は東京海上が音頭を取って、国交省や経産省も一応乗っているという構図だけれど、本当に機能するのかなあ。ドライバーの相互利用という発想まで踏み込めれば、これまでと違う展開もあり得るかもしれないね」
記者C「気になったのは、中継拠点を自社の施設でやる前提になっていた点。浜松の『コネクトエリア』や、センコーがオープンプラットフォームとして整備した中継拠点は、この枠組みの中では使わないみたい。高速道路のサービスエリア、パーキングエリアがパンクしているからこそ、外部の中継拠点を整備してきたはずなのに、国が絡んだオープンプラットフォームですら使われないとなると、この種の中継拠点に本当にニーズがあるのかという疑問も出てくる」
記者B「日野とNLJ(ネクスト・ロジスティクス・ジャパン)がやっていた中継輸送のプロジェクトも頓挫しているし、国は国で中継拠点整備をうたっているのに、今回そこをあえて使わないのだとしたら政策との整合性はどうなるの?というのも疑問。もともと中継輸送は働き方改革対応が大義名分だったのに、高市内閣になって『行き過ぎた働き方規制を緩めよう』という議論まで出てきているでしょう。政治の風向きいかんでは、このプロジェクトの意味づけ自体が変わりかねないんじゃないかな」
記者C「記事には入ってなかったけれど、ドライバーがどの程度日帰り運行を望んでいるかという独自調査も会見では紹介されていて、全体では4人に1人、若い層だけを見ると20-30代で4割程度が日帰り運行を希望していたという数字。思ったほどみんな『日帰りしたい』わけでもないんだね」
記者C「中継方式でも、ドライバー交代方式は遅延リスクが重くなる。どちらか片方の便が事故や天候で5-6時間遅れたり、最悪たどり着けなかったりした場合、本来は動けるもう一方の便まで足止めになるし、日帰りのはずが泊まり運行に変わるケースも出てくる。通常なら1便で済んだ被害が2便に波及する構造なので、実務としてどう設計するのかは注目したいね」
 日本郵政物流事業530億円下方修正、点呼の代償重く
日本郵政物流事業530億円下方修正、点呼の代償重く
記者B「日本郵政・日本郵便の決算と中計も押さえておきたいね。郵便・物流事業は第2四半期時点で前回予想から530億円のマイナスで、外注費と人件費の増加が響いている構図。グループとしては、JPトナミグループの連結化による増収で数字を埋めているけれど、本業での赤字幅はインパクトが大きい」
記者A「中期計画によれば、全都道府県に置いてきた集配拠点の網を組み替えて、都市部は密度を高め、地方は統廃合し、空いた拠点は郵政不動産で活用するという方針だそう。ユニバーサルサービスの看板を少しずつ下ろしながら、サービスレベルと収益性の両方を見直さざるを得ない局面に入ったと言えるかもしれない」
記者B「総合物流企業を目指すという旗を掲げてきたけれど、その前提となる国内のガバナンスやルール順守をどこまで立て直せるのかねえ。今回の行政処分につながった記録簿の扱いやマニュアル改ざんの問題は、現場では半ば慣行になっていた面もあるはずで、そのツケが今後もコストとして表面化してくるんじゃないかな」
記者C「日本テレビのニュース番組では、遠隔点呼システムを導入しながら、アルコール検知器にストローを当てて何度吹いても作動しない映像が延々流れていた。せっかくDXを入れても、現場でちゃんと運用しきれていなければ投資もシステムベンダーも浮かばれないよねえ」
記者A「一方で、総合物流化に向けた布石は水面下で進めようとしている気配があるので各方面にアンテナ張っておかないといけないね」
 Uber、即時宅配便「Courier」22都道府県で開始
Uber、即時宅配便「Courier」22都道府県で開始
Uber Japanは、配車アプリで荷物を即時配達できる新サービス「Courier」(クーリエ)を22都道府県で開始した。Uber Eats配達パートナーが対応し、倉庫を介さず最短30分で届ける。料金は距離あたり1キロ890円からで、最大重量13キロ、重量8キロまで配送可能。アプリで依頼から決済、追跡まで完結する。広島・那覇・福岡での実証を経て本格展開に至り、地方都市への拡大も視野に入れる。10万人超の配達パートナーの新たな収入源となり、即配市場の拡大に寄与すると見込まれる。
記者C「イメージとしては、少し大きめの荷物にも対応できるバイク便に近いサービスなんじゃないかな。ただ、飲食店と個人宅の往復が中心だった配達員が、企業オフィスの館内物流まで担うようになると、受付やセキュリティー側から見れば『どこの誰か分からない人』が重要書類を持って出入りする状況になりかねない。身分確認の仕組みや、出入り可能な人を絞る運用がないと、トラブルの火種になりそう」
記者D「経営サイドから見れば、すでに街中に配達員というリソースを持っているUberが、その余剰時間を活用して新たな収益源を取りに行くという発想自体は合理的。一方で、今の配達員のモラルや教育水準のまま親書や機密性の高い文書を預けられるかと問われれば、かなり厳しい評価も出てくるはず。信頼性を担保するスクリーニングや研修の仕組みとセットで制度設計しないと、社会問題化するリスクもある」
記者A「既存プレイヤーでは、バイク便のセルートが立ち上げた『セルフィット』がギグワーカーを使ったラストマイル宅配を展開していて、ENEOSのガソリンスタンドやセブン‐イレブンのネットコンビニ配送などを請け負っている。オフィス配達のノウハウを持つ事業者が、この領域にどう絡んでくるかも含めて、マーケット全体のプレイヤー構図は整理して見ておきたいね」
記者B「このUberのスキームで一つ需要が出そうだと感じるのは、郵便局への差し出し代行。集荷をやめた郵便局も増えていて、企業側がわざわざ持ち込んでいるケースが少なくないよね。そこを自転車やバイクのネットワークで代行する形は、料金と品質の折り合いさえつけば、かなり相性が良いかもしれない」
記者D「ただ、そこまで踏み込むなら信書の扱いをどうするかという本質的な論点も避けられない。『赤いバイクだけが郵便物を扱う』というこれまでの暗黙の前提が崩れれば、日本郵便のブランドや信頼性にも影響あるはずだよね。時代のニーズは確実にあるけれど、誰がどの枠組みで担うのか、制度面の詰めがないと現場は混乱するんじゃないかな」
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。