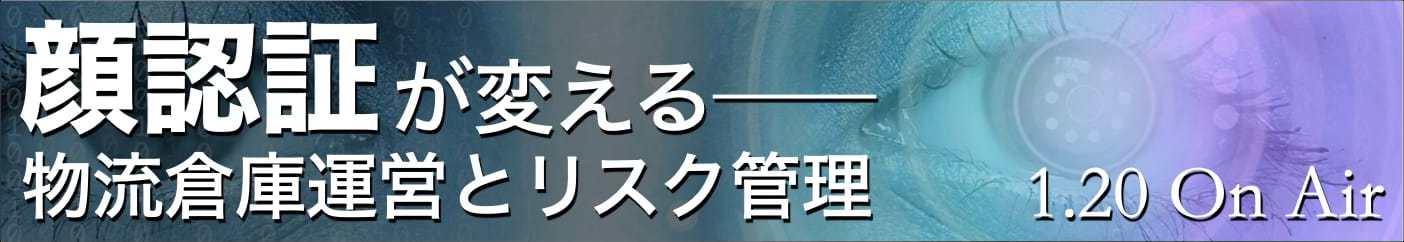ロジスティクスことしも残すところあと3か月を切った。日本各地の郵便局には、2026年用の年賀はがきが搬入され、10月30日からの販売に備えている。
日本郵便は、26年用の年賀はがきの当初発行枚数は7億4841万枚と発表した。これは03年のピーク44億5936万枚のほんの6分の1ほどであり、前年比マイナスが続く。昨年度の当初発行枚数は10億7000万枚だというから、30%の減少という後戻りできない急降下である。
年始挨拶そのものの手法が、デジタルへと急速に切り替わりつつある現状には抗いようがない。昨年度末、葬儀関連情報サイト運営のディライト(東京都新宿区)が実施したアンケート調査によれば、その年度で「年賀状を出さない」との回答が62.6%に上った。代替手段としてはLINE(46.7%)が最多で、「特に挨拶を行わない」が44.0%にも及ぶ。
また、年賀状印刷サービスを展開するフタバ(名古屋市昭和区)による同年度調査によれば、年賀状を出さない・やめる選択肢を選んだ理由としては、「手間の軽減」が43.2%、「メールやSNS等電子手段が十分だから」が42.7%という回答が多数を占める。多くの人が「便利さ」を求めて年賀のやり方を切り替えているのが確認できる。ことし新たに調査すれば、「郵便料金の値上げ」も上位に食い込むことだろう。
かくいう筆者の年賀状のやり取りも、コンビニエンスストアで「インクジェット対応年賀はがき10枚入りパック」を購入すれば事足りるようになった。とても年賀状文化の衰退を嘆くような立場には無く、「年賀状じまい」の報せに、寂しさよりもホッとする自分がいるのも確かである。
デジタル移行の波は、年賀状文化そのものを少しずつ溶かしていく。日頃、物流効率化を訴え、DX(デジタルトランスフォーメーション)やペーパーレス化を訴えている立場としては、日常にまで効率化が波及したとして歓迎すべきことなのかもしれない。しかし、元日の朝に近づく配達バイクの音やポストに落ちるはがきの音にワクワクした思いを、次代を担う人々と共感できないとすれば、やはりなんとも寂しいことだ。
それでも、時代は進む。こうした郵便・挨拶のデジタル化は、他分野にも波及するビジネスチャンスとしての側面を持つ。請求書業務、請求通知などはすでにDX化の潮流にあるが、年賀状を通じた挨拶のデジタル転換は、これまでの慣習の打破、「紙から電子移行」の象徴的前例になりうる。年賀挨拶をデジタルに切り替えられるなら、請求書・通知業務も「紙郵送から電子送信へ」の心理的抵抗も一層低くなるだろう。
運送業界などでは、今でもメールではなく礼状のやりとりなどに重きをおくとも聞く。年賀挨拶という親密性の高い領域ですら「紙ではなくデジタルでいい」という選択肢が受容され始めたという実績は、ビジネス文書の電子化を訴求する事業者にとって攻略ポイントとなるだろう。かつて「年賀状くらいは郵便で」と抵抗していた層でさえ、気づけば「デジタルで十分」と思い始めているからだ。
年賀状が「悪しき因習」であるならば、このまま駆逐されても仕方あるまい。しかし、年賀状はそうではないだろう。自身、今でも細々とやり取りを続けているのは、 申し訳程度に書き足された「ことしこそ飲みましょう」の一言に、その人が過ごした一年を思い、胸があたたかくなるからだ。昭和・平成を生きた世代にとって、それは単なる連絡手段ではなく、年に一度の「人付き合いの再起動」でもあった。年賀状のやり取りには、便利さの対極にある「面倒くささ」「煩わしさ」がある。しかしそれこそが、人をつなぐ力になっているとの思いは強い。
元旦から走り回る配達員の姿、赤いバイクの出発式の様子も、私たち世代にとっては正月だけの胸躍る記憶だった。この10月は、日本郵政民営化から20周年という節目となるが、人手不足やコスト増、社会の変容など、郵便事業を取り巻く環境は厳しさを増すだろう。働き方の見直しは重要だが、それでも「面倒くささ」「煩わしさ」に負けて事業の根幹を疎かにしてはいけないのは当然だ。点呼体制の再整備などを通じ、日本文化の一風景として人と人をつなぐ重要な役割を担う業務に、あらためて誇りと責任を感じてもらいたい。
もちろん、年賀状という文化が完全に消え去ることはないだろう。激減したとはいえ7億枚というポテンシャルがあることも確かだ。私たちの知っているような文化をそのままの形で次代につなげられなくても、1枚のはがきに心をこめるという年賀状の意義、重みはむしろ増し、デジタルでは代替できない文化としてその価値が評価されるはずだ。
日本レコード協会は、昨年のアナログレコードの生産量が前年比17%増の314万9000枚、生産額は同26%増の78億8700万円となったと発表している。70億円を超えたのは1989年以来35年ぶりだという。音楽同様に広い裾野を持つ年賀状という文化もまた、デジタル化によって完全に消え去るのではなく、“再発見”されるときが来る。
年賀状のインクのかすれや書き損じの修正跡も、アナログレコードのノイズと同様に、デジタルでは決して再現できない“痕跡”である。AI(人工知能)全盛という、これまでまだ誰も知らない新時代に突入することで、かえってその“痕跡”に価値を見出す世代が生み出されるのではないだろうか。(大津鉄也)
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。