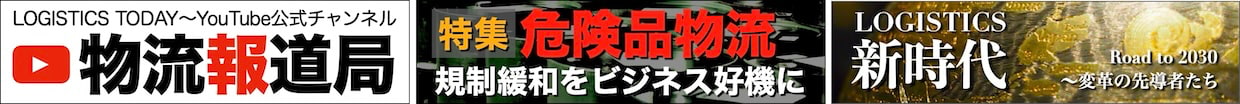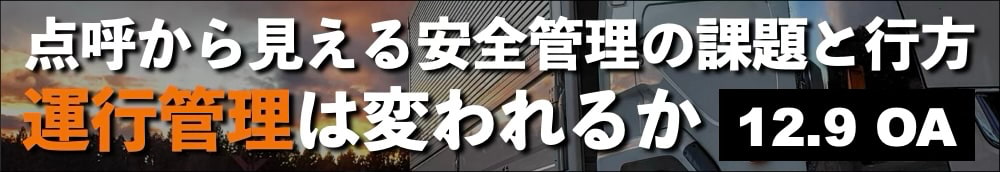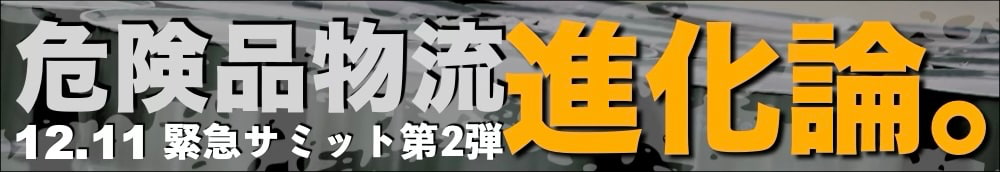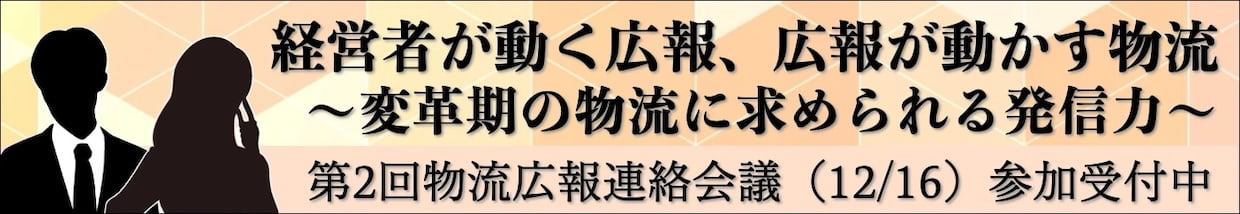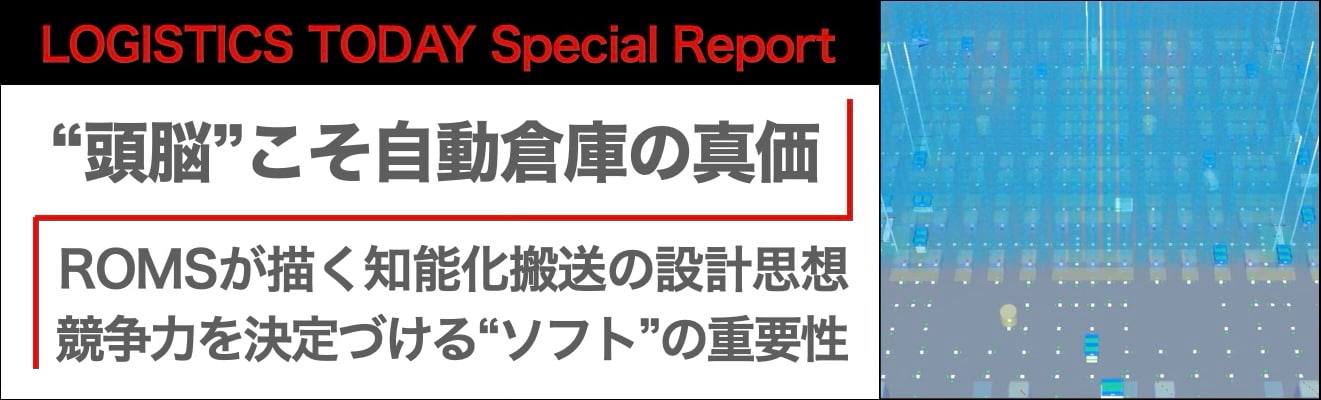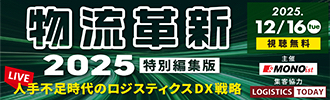記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「トップバリュ、即席麺輸送にレンタルパレット導入」(9月2日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)
◇
ロジスティクス日本パレットレンタル(JPR、東京都千代田区)は、物流業界が直面する2024年問題に対応するため、レンタルパレットの「共有」を軸としたサプライチェーン全体の効率化を推進している。発荷主と着荷主の協力を促す仕組みとDX(デジタルトランスフォーメーション)を組み合わせ、ドライバーの負担軽減と輸送力の安定確保を目指す。同社の取り組みは、個社の効率化にとどまらず、持続可能な物流基盤の構築に向けた重要な一手だ。
物流業界は深刻なトラックドライバー不足に直面し、荷役作業の効率化と待機時間の短縮が喫緊の課題となっている。 国も改正物流効率化法を通じて、発着荷主に対策を促す。これまで、即席麺や菓子類などの軽量物は、トラックの積載効率を最大化できる「ばら積み」輸送が主流だった。しかし、ドライバーの労働環境改善が最優先されるなか、荷役時間を大幅に短縮できるパレット輸送への転換が、軽量物分野でも不可欠な流れとなっている。

▲パレット輸送によってドライバーの負荷が軽減(出所:JPR)
同社が提供するレンタルパレットの仕組みは、この課題解決の中核を担う。メーカーなどの荷主が自社でパレットを所有する場合、納品先での管理や空パレットの回収にかかる非効率な輸送が負担となる。レンタル方式は、こうした手間とコストを解消する。一方、小売の物流センターなど着荷主側にとっても、複数の納品事業者が標準規格のパレットを利用することで、荷受け作業の手順が統一され、管理が格段に容易になるという利点がある。
従来、ドライバーの荷役作業は運賃に含まれる「見えないコスト」と見なされがちだったが、物流を安定的に維持するための「必要な投資」として、発荷主と着荷主双方の理解が進んでいる。まさに「発荷主と着荷主の協力」が、サプライチェーン全体の生産性向上を実現する鍵だ。
同社は、パレット利用をさらに促進するため、DXの推進にも力を入れる。 パレットにIDを付与したシステムや納品書のデジタル化など、新たな付加価値を提供し、利用企業の導入ハードルを下げている。また、急増する需要に対応すべく、供給体制の強化も急ぐ。

▲東条デポの完成イメージ(出所:JPR)
24年度のレンタルパレット供給枚数は、前年度比5.8%増の5309万枚と過去最高を更新した。8月には、全国に60か所ある拠点の中でも中核施設である「JPR東条デポ」(兵庫県加東市)を拡張。無人フォークリフトやRFID(電子タグ)などの先進技術を導入し、関西圏を中心とした供給能力を大幅に引き上げた。パレットの活用は、手作業で1.5時間から2時間かかる荷役作業を4分の1に短縮する効果があり、同社の循環型サービスは、持続可能な物流基盤づくりを力強く後押しする。
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。