イベント物流DX開発を手がけるX Mile(クロスマイル、東京都新宿区)は業界横断型イベント「物流DX未来会議2025」を開催した。3会場で全15セッションを実施し、延べ1500人が参加した。
メインセッションが行われるROOM1でのオープニングセッションでは同社代表取締役CEOの野呂寛之氏と、モデレーターを務めるLOGISTICS TODAY社長兼編集長の⾚澤裕介が登壇。野呂氏は「物流をコストではなく品質に」と提言。さまざまな変化にさらされている物流業界に、「共に新しい形の物流を作っていこう」と呼びかけた。
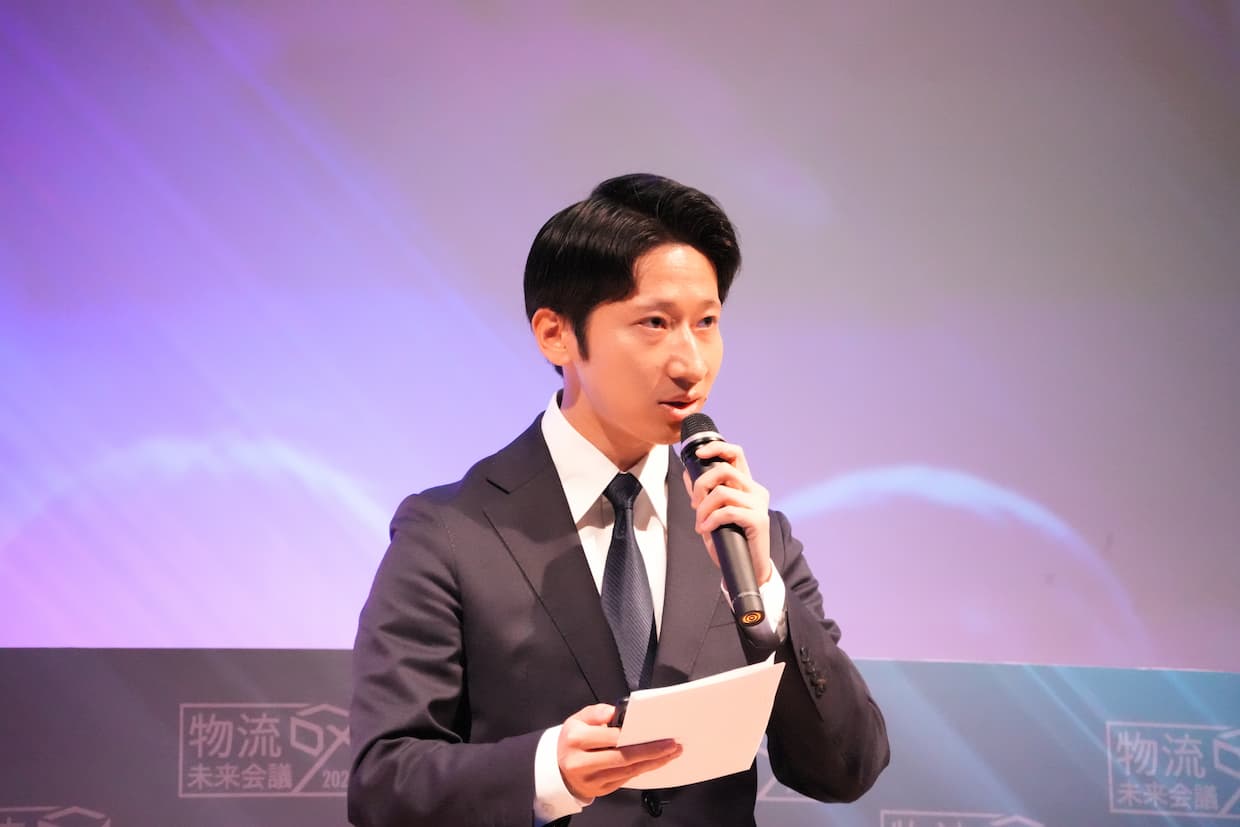
▲X Mileの野呂寛之社長
◇
脱Excelが利益体質の鍵、ログラスが提言
当たり前の徹底が鍵、トラボックス会長が新法解説
同会場では続いて「サプライチェーン構造改革の最前線と未来」と題したセッションが行われ、流通経済大学流通情報学部教授で物流科学研究所所長を務める矢野裕児氏が登壇。24年問題を機に加速する物流構造改革の方向性を語った。

▲LOGISTICS TODAY社長兼編集長、赤澤裕介
矢野氏はまず、ドライバー不足を「予測を超えて進む確実な人口減の結果」と分析。物流業界を支えてきた第2次ベビーブーム世代が50代後半に差し掛かり、若年層の補充も見込めないと指摘した。そのうえで「これまでの改革は運送事業者が中心だったが、荷主を巻き込まなければ昭和型物流から抜け出せない。今後はサプライチェーン全体の構造を変えなければならない」と訴えた。
議論は「全体最適」というキーワードに及んだ。矢野氏は「個別最適では限界があると分かっていても、全体最適とは何かが共有されていない。共通の目標や指標がなければ、言葉の遊びで終わってしまう」と警鐘を鳴らした。赤澤氏も「従来のルールでは対応できない領域に突入している」と応じ、着荷主を含むプレーヤー全体での再設計が必要だと述べた。
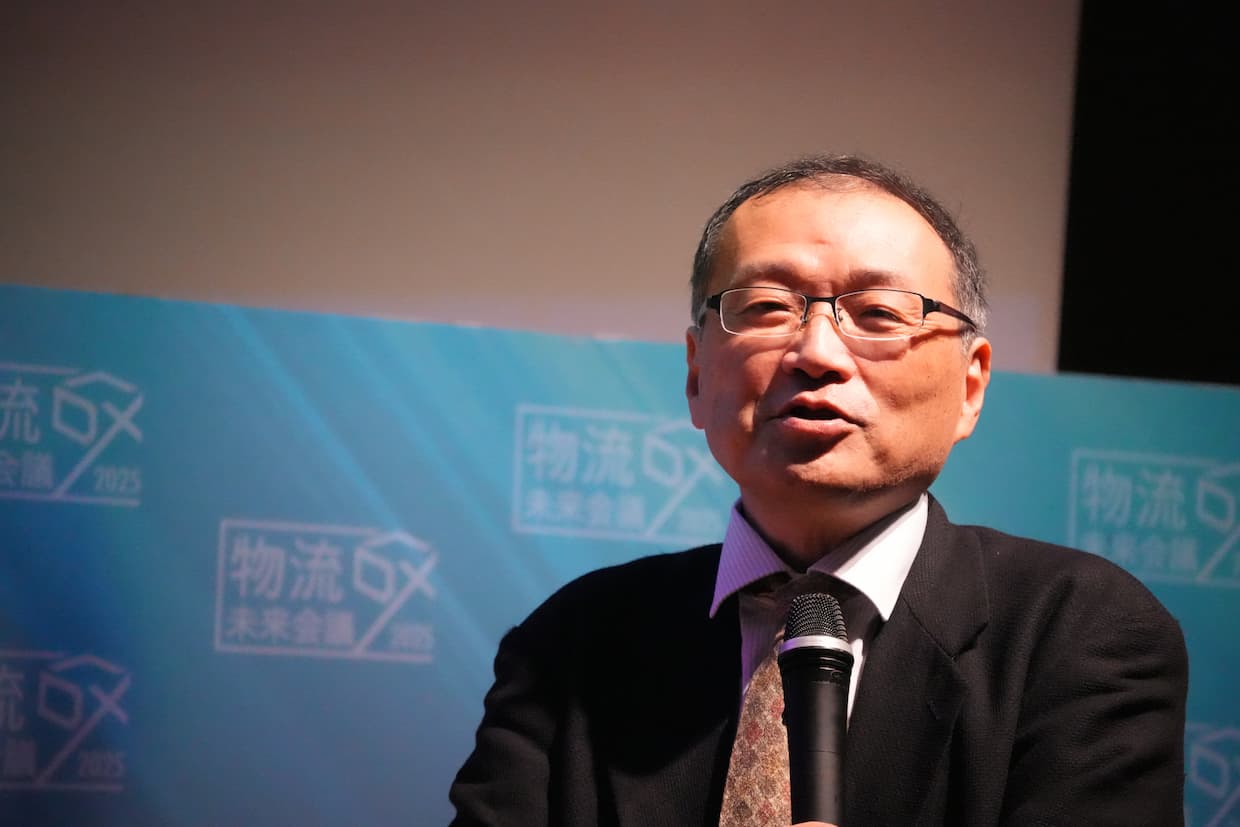
▲流通経済大学流通情報学部 教授で物流科学研究所所の矢野裕児氏
さらに両氏は、改革の基盤となる標準化・ルーティン化の遅れを指摘。赤澤氏が「パレット標準化だけで60年議論している」と苦言を呈すると、矢野氏は「業務が定型化されていなければ情報化も機械化も進まない。今やらなければ本当の改革は難しい」と応じた。
また、荷主企業に課せられたCLO(物流統括管理者)設置義務について、矢野氏は「単に3PLに任せる時代は終わった。ロジスティクスを企業経営の全体最適の一部に組み込むことが必要」と強調した。共同配送・共同物流についても「単なる組み合わせでは失敗する。各社が自社の物流条件を変える覚悟がなければ持続しない」と述べた。
最後に「サプライチェーン改革を支えるのは人材だ」として、流通経済大学が文部科学省のリカレント教育事業で始めたサプライチェーン講座を紹介。「データサイエンスを含めた体系的な知識を社会人が学ぶ場を通じ、物流を俯瞰的に考えられる人を増やすことが改革の第一歩」と締めくくった。
◇
続くセッションでは「特定荷主が導く物流改革」と題し、YKK AP常務執行役員でCLO兼ロジスティクス部長の岩崎稔氏と、フィジカルインターネットセンター理事長で流通科学大学名誉教授の森隆行氏が登壇。荷主企業主導の物流改革に焦点が当てられた。
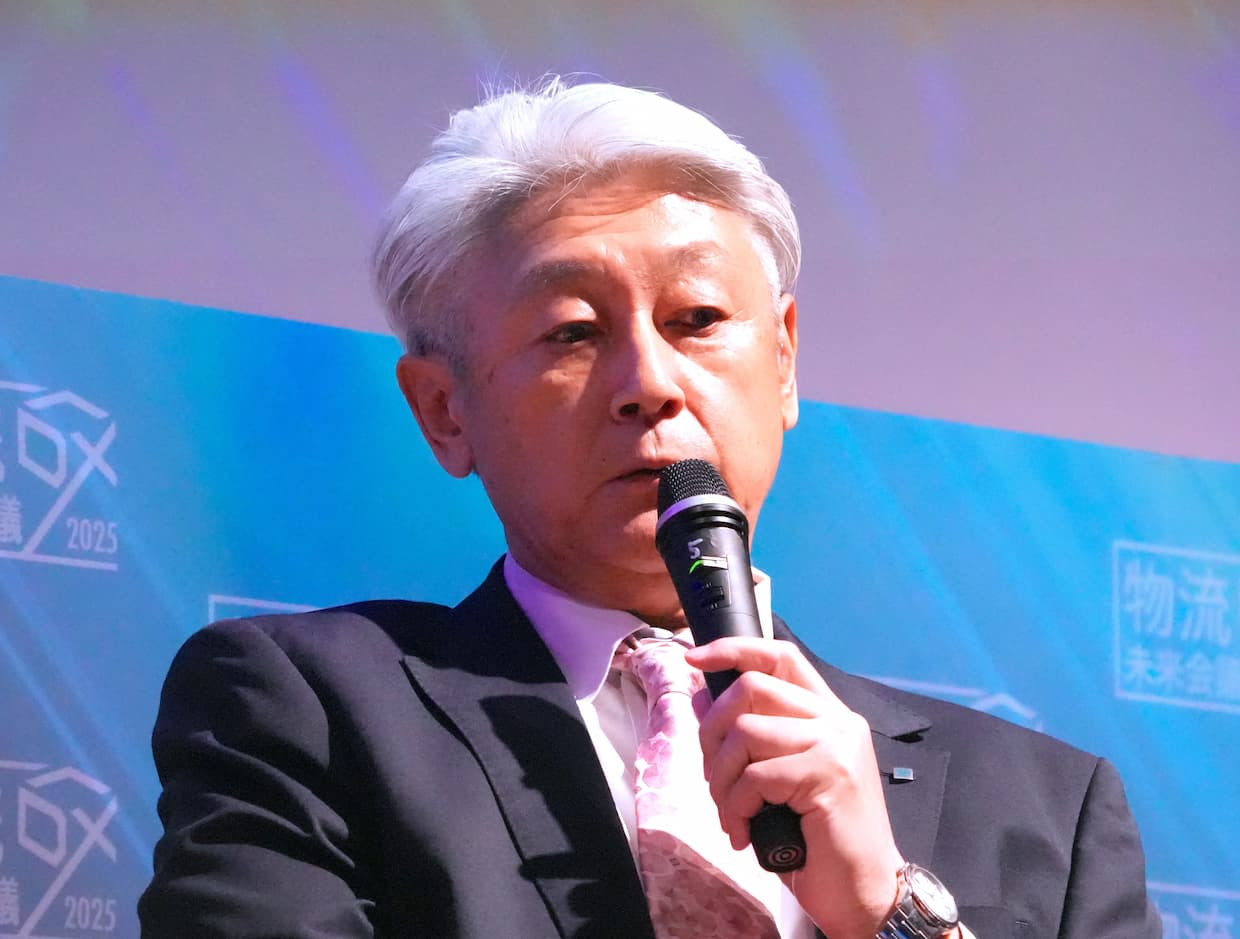
▲YKK AP常務執行役員CLOの岩崎稔氏
森氏は冒頭、「これまでの物流改革は運送事業者任せだったが、24年問題では荷主が当事者として責任を負う段階に入った」と指摘。物流を「空気や水のように、必要な時に安く手に入るもの」と考えてきた企業文化が変わりつつあると語った。一方で岩崎氏も「ものづくり企業は“作れば終わり”という感覚が残っていたが、それでは通用しない。7-8年前から意識改革を進めてきた」と応じた。
議論は、物流費上昇への対応に移った。岩崎氏は「政府の適正原価制度のもと、運賃は今後さらに上昇する。YKK APでは中期経営計画の中で上昇率を織り込み、受け入れたうえで効率化を図っている」と説明。単なる値上げ交渉ではなく、物流事業者とともに改善策を構築する姿勢を強調した。「押し付けではなく、双方の知恵を出し合って最適解を探る関係が必要だ」と述べた。
岩崎氏はまた、地方拠点を抱える荷主の現実にも触れた。「北陸は車両保有台数が全国で最も少ない地域。固定的な取引先だけに頼るのではなく、異業種連携を広げて輸送力を確保していく」と説明。CLOとして、既存の取引構造を超えた新たなサプライチェーン構築の必要性を示した。

▲フィジカルインターネットセンター理事長で流通科学大学名誉教授の森隆行氏
森氏はフィジカルインターネット構想について「持続可能で環境に優しい物流体系を目指す世界的な動き」と紹介。日本も欧米と並びロードマップを策定しており、「産官学の連携が不可欠。大学も実務教育を強化し、産業界との橋渡し役を担うべきだ」と述べた。
岩崎氏は「講義を通じて物流に関心を持つ学生が増えている。企業の現場課題を具体的に伝えることが次世代の育成につながる」と語り、CLOとして教育現場にも関与している姿勢を明かした。最後に「法改正で来年には3000社以上のCLOが誕生する。課題は山積しているが、横の連携を深め、産業全体で改革を支え合うことが重要だ」と呼びかけた。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。



















