
記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「デイブレイク、特殊冷凍技術で冷凍寿司を海外展開」(10月2日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)
◇
ロジスティクス冷凍技術は、食品保存のための手段から、いまや“物流の形を変える技術”へと進化している。その最前線に立つのが、特殊冷凍技術を軸に食品産業と物流の変革を進めるデイブレイク(東京都品川区)だ。同社は、出来たての感動を世界へ届けるというビジョンのもと、独自の冷凍技術を武器に、時間と距離の制約を超えたコールドチェーンの可能性を拡大している。

▲ARTLOCK FREEZER(アートロックフリーザー)
主要事業は、きめ細やかな冷気でムラなくスピーディーな冷凍を実現する特殊冷凍機「ARTLOCK FREEZER」(アートロックフリーザー)の提供だ。乾燥、酸化、変色を防ぐ、圧倒的な冷凍品質を誇る。経営企画室の松本知世氏は、「これまで冷凍は無理、不向きとされていた食材や商品への活用や、多様な業界への導入も進んでいる」という。
締めたての刺身そのままの鮮度、出来たて和菓子のもちもちとした食感、ふわふわ・サクサクの食感を織り重ねたスイーツ、パン製品の繊細さなどもそのまま再現できる独自の冷凍技術が同社事業の基盤。揚げたてのフライの食感、日本人がこだわるお米の炊きたてのおいしさも忠実に再現する。さらに、こうした特殊冷凍ソリューションをビジネスに活用できるようなコンサルティングや、素材・レシピの開発、冷凍食材の商品企画開発や流通販売なども展開し、食品流通の夜明け=デイブレイクを目指す。
 「時間」と「距離」の制約を超えて感動を広げる
「時間」と「距離」の制約を超えて感動を広げる
冷凍食品の特性を、物流危機をはじめとした社会課題の解決に活用しようという取り組みにも意欲的だ。新規事業開発室室長の五十嵐圭佑氏は、「冷凍技術の活用によって、物流における『時間』『距離』の課題を乗り越えることができる」と表現する。
従来、日配品のような生鮮・惣菜カテゴリーのチルド物流では、配送可能距離や時間、配送回数などの制限にしばられた物流を構築せざるを得なかった。しかし、冷凍食品であれば、配送圏は一気に日本中、さらには世界へと『距離』が広がる。『時間』の壁となっていた賞味期限を延長できることで、納品回数や在庫管理の最適化にもつながり、物流効率の向上、CO2排出量の削減に直結するなど、物流の自由度も上がる。
さらに松本氏は、同社技術の真価は単なる“長持ち”ではなく、「“おいしさの再現性”こそが強み、他社との違い」だと語る。解凍後も食感や風味を損なわず、まるで出来たてのような品質を保つことで実現するのは、時間と距離という配送圏の拡大だけではない。「おいしい、こんなのはじめてという食の感動を広げること」(松本氏)こそが、同社だけが提供できる価値なのだという。
 冷凍寿司が生んだ新たな“体験価値”
冷凍寿司が生んだ新たな“体験価値”
食の感動体験を拡大する技術、その象徴的な成果として注目を集めるのが「冷凍寿司」の海外展開だ。

▲冷凍寿司。冷蔵解凍、常温解凍で出来たての味を再現できる
シャリとネタを分けず、完成形のまま高品質で冷凍・解凍できるのは、同社の独自技術があってこそ。米国・ハワイでは、日本から輸出された冷凍寿司が現地大手スーパー「Mitsuwa Marketplace」(ミツワマーケットプレイス)で販売を開始している。現地では“冷凍であることに気づかず”に楽しむ消費者も多く、日本の味をそのまま届けることに成功している。
「“Sushi”という言葉は定着していても、その本当のおいしさまでは届けきれていない。日本ならではの味で感動を届けることができれば、多様なビジネスチャンスも広がる」(松本氏)
 冷凍技術がもたらす人手不足解消と需給・生産の最適化
冷凍技術がもたらす人手不足解消と需給・生産の最適化
物流危機の要因の1つである人手不足対策にも、特殊冷凍技術は大きく貢献する。五十嵐氏は、「冷凍技術の活用には攻めと守りの両側面があり、新しい商圏への販売拡大という攻めだけではなく、人手不足のなかで効率的に利益を上げるための守りの活用でも有用」と語る。
米国が日本から発送する冷凍寿司市場として期待できるのは、本格的な“Sushi”へのニーズが高いにも関わらず、現地職人が不足しているからだ。国内でも、例えばうなぎを提供する店舗では熟練のうなぎ職人の確保が課題となるが、同社技術の導入により職人不足による機会損失を防いだ事例もある。特別な調理技術を要する商品でも、セントラルキッチンで一括製造し、必要なタイミングで各店舗へ配送することで、職人の数を増やさずに出店拡大が実現できる。
また、冷凍を前提とした計画生産、需給設計により、繁閑差を平準化し、フードロスの削減にもつながる。とれたて・できたてを超える“最適なタイミングの味”を届けるという発想は、物流における新しい効率性の指標になるだろう。
 「独自のコールドチェーン構築」掲げ、連携で次のステージへ
「独自のコールドチェーン構築」掲げ、連携で次のステージへ
デイブレイクは、特殊冷凍機器の開発・販売にとどまらず、特殊冷凍のトータルソリューション提供者として活躍の領域を広げる。さらにその先、次なるビジョンとして掲げるのは“独自のコールドチェーン構築”である。冷凍設備における加工や保管、輸送までを一体化した、冷凍技術の知見を生かした最適物流網の形成を目指すという。
同社が掲げるコールドチェーン構想の実現には、単なる自社冷凍技術の延長だけではたどり着けない。生産者や施設、運送、小売など各専門領域それぞれに、「出来たてそのままの冷凍食品のおいしさ」を届けるための、一歩先に踏み込んだ取り組み、協力が不可欠となる。

▲パナソニック「VIXELL(ビクセル)」
例えば冷凍寿司においては、大手酢メーカーによる冷凍-解凍に最適化したすし酢の研究が重要な役割を果たしたという。また、これまでの冷凍寿司の航空輸送では、輸送工程のつなぎ目で発生する温度変化による品質劣化が課題だったが、ここではパナソニックの医薬品用冷凍コンテナ「VIXELL」(ビクセル)によって課題解決の実証に結びつけることができた。ビクセルの高性能断熱構造により、輸送全体で温度安定を実現。海上輸送の主要ルートに加えて、スピード感のある航空輸送という可能性が開かれた。
米国国内の配送網拡大やサービス品質向上を考えれば、現地を知り尽くした物流事業者との連携も必須だ。日本の生産技術、冷凍技術、さらに物流企業が培ってきた正確な温度管理・配送システムを組み合わせた“オールジャパン”の連携によって、日本の味だけではなく、日本の冷凍物流サービスを世界に問う姿勢である。
米国をはじめとした各国の規制も、1社だけでは立ち向かえない高いハードルだという。「輸出にあたって寿司というカテゴリーがない。枠組みがないルートの開拓、ルール作りに関しての道も切り拓いている状況」(五十嵐氏)だけに、ともに道を切り拓く仲間を集めることこそが、コールドチェーン構築の推進力となる。
目指すのは、冷凍という「共通技術基盤」を介して、食品、機器、物流が連鎖的に価値を生み出すような仕組み作り。五十嵐氏は、多様なパートナーが、それぞれの得意領域を生かして、世界市場にトライする、そんなコールドチェーン構想への参画を呼びかける。
ターゲットは、米国だけでなくアジア、ASEANなど全世界の市場だ。また、寿司だけではなくラーメンやうどんなど、特定の商品やエリアに限定せず全方位型のアプローチを展開する中から、新しい道筋も拓かれる。多様なチャレンジャーが集うことで、寿司だけではなく新規商材などを海外展開するルートも開拓されるだろう。
 世界へ広がり、常識を変える「日本の冷凍物流品質」
世界へ広がり、常識を変える「日本の冷凍物流品質」
冷凍技術の活用が、物流効率化に貢献する部分は大きい。問題は、冷凍食品の価値が消費者に受け入れてもらえるかどうかだ。
冷凍したらおいしくない。そんな思い込みを覆すこと自体が、冷凍寿司の海外展開の大きな意義となる。運送状況の可視化や温度管理の厳格化を通じて、“おいしさそのままに届ける”仕組みの精度はさらに高まっている。日本が誇る食文化を、日本が誇る物流技術で世界へ届けることで、距離や時間の壁を越え、感動もグローバルに循環し始める。冷凍食品が生み出す感動が世界から逆輸入されるとき、それは日本の消費者の“思い込み”を揺さぶる瞬間でもある。「こうでなければ」という常識がほどけ、新しい価値観が芽生えれば、物流のあり方そのものを変えていくのではないか。
いまや、さまざまなおかずを詰め合わせた弁当でも、各惣菜ごとに最適な冷凍技術と計画生産・保管の最適化が導入されている。弁当、外食店、ホテルのバンケットなど、私たちは知らぬ間に、冷凍食品のおいしさに驚かされているのかもしれない。
「冷凍でも良い」ではなく、「冷凍が良い」。そんな選択をする人が増えていくことこそ、 特殊冷凍技術と物流が融合した“独自のコールドチェーン”を動かす原動力となる。(大津鉄也)
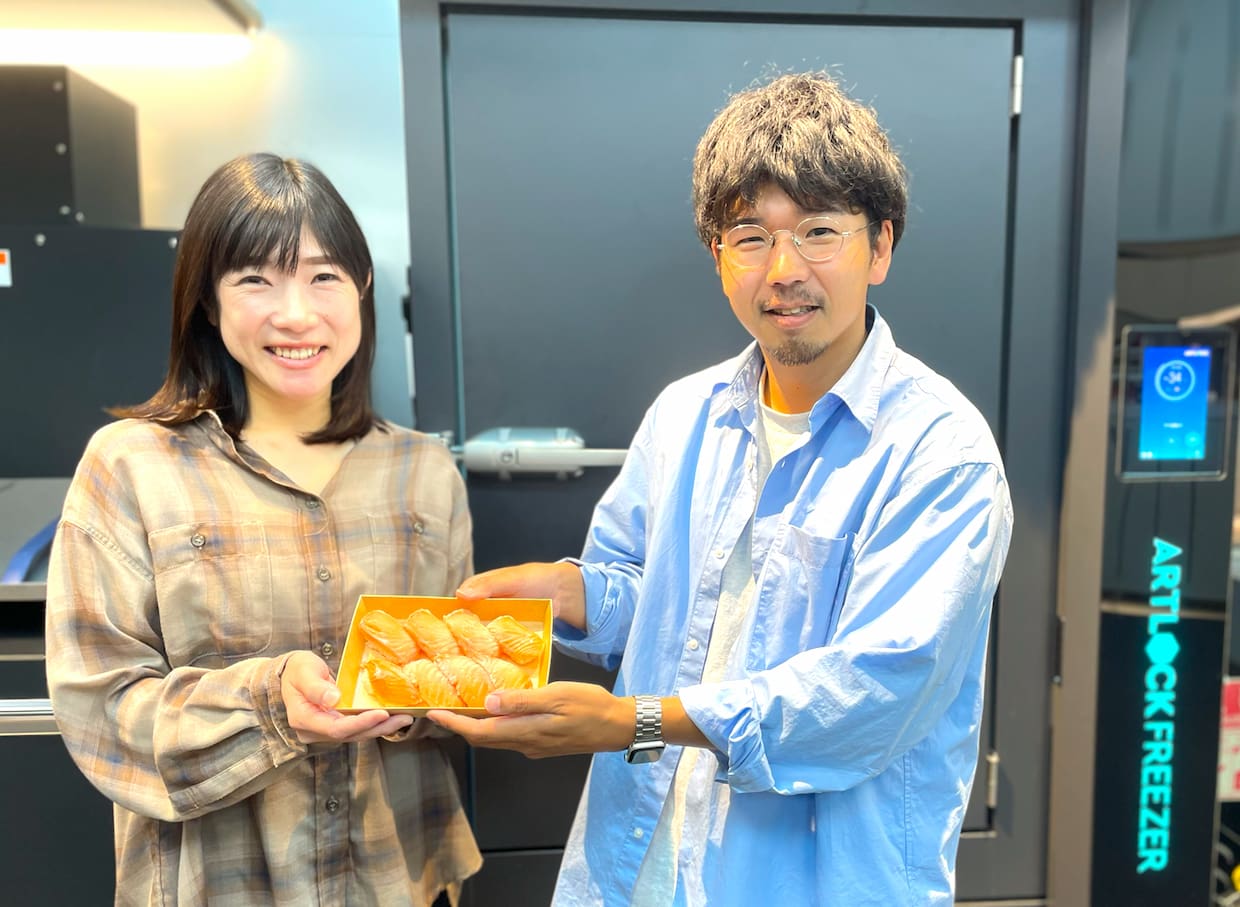
▲(左から)松本氏、五十嵐氏
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。




















