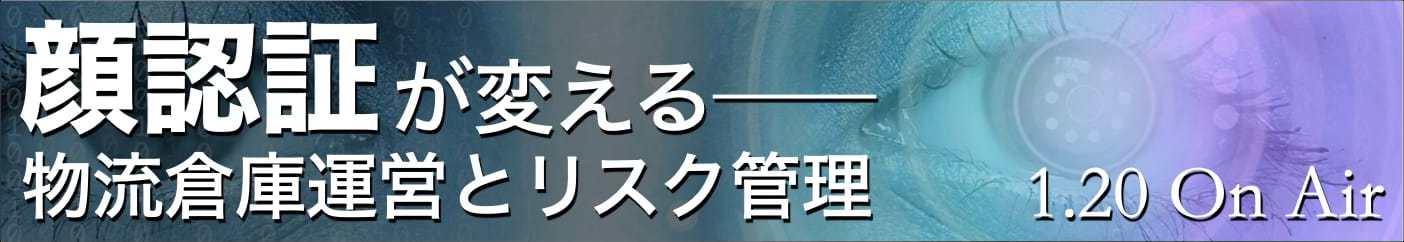ロジスティクスコロナ禍を経て一般家庭での冷凍食品の需要はますます高まっている。また一方では、労働力の不足から外食産業や給食などでの需要も高まっており、冷凍物流の必要性も高まるばかりだ。こうした状況のなか、冷凍冷蔵品の物流の上流から下流までに強みを持つSBSフレックが厚木物流センターを開設。冷凍物流に特化した3PLである同社の、拠点開発の狙いを聞いた。

▲SBSフレック厚木物流センターの外観イメージ
 全国に配送網があるからこそ実現できる小ロットからのローコスト配送
全国に配送網があるからこそ実現できる小ロットからのローコスト配送
物流業、運送業は慢性的に人手が不足している業界だが、飲食サービス業、福祉介護事業などの労働集約的な業界は同様に労働力の不足にあえいでいる。こうした背景から、近年は福祉介護施設の食事(給食)は冷凍食品に移行が進み、冷凍物流への需要がますます高まっているという状況だ。飲食店であっても「完調品」(完全調理食品)と呼ばれる冷凍食品を提供している店舗も、もはや珍しくなくなっている。

▲常務執行役員営業推進本部長の吉田和明氏
冷凍食品の需要と普及は加速するばかりだが、SBSフレックが自社での拠点開発ではなく、低温物流専門デベロッパーの霞ヶ関キャピタルからの賃貸を選んだのもこうした状況への対応というのが大きな理由となっている。建築資材は引き続き高騰の傾向にあり、用地買収を含めると、稼働まで早くても2〜3年といった時間はかかってしまう。「ニーズの変化にスピード感を持って対応するため」(常務執行役員営業推進本部長の吉田和明氏)の選択が物件の賃貸であったのだ。

▲営業推進本部・営業開発第一部長の岡野光誠氏
SBSフレックはもともと冷凍冷蔵食品の物流に強みを持っているが、その最大の強みの1つが同社が全国に持つ配送網だろう。全国に70の拠点を展開し、それぞれの拠点が配送網を構築している。関東だけでも180社の協力会社が冷凍冷蔵品の配送を担う。この配送網を生かして全国で冷凍品の配送を行うことができるだけでなく、同社の冷凍配送は「大手では実現できない効率的な配送を目指している」(営業推進本部・営業開発第一部長の岡野光誠氏)。
これを実現するために、ほかの荷物と積み合わせる共同配送を行っていく計画だ。冷凍配送用には軽バン、ワンボックス、1トン車、4トン車など、協力会社の多様な車両を使っているが、ドライのトラックでの配送も計画しており、利用可能な車両を使って実現していく。
また、商品の仕分けや流通加工においても、細かいニーズに対応し、1日に数千から数万ピースのピッキングから出荷に対応すべく、専用のマテハンを導入し、日々品質と生産性の向上に努めており、温度管理や誤出荷の抑止をはじめとする高い品質で評価を得ているという。吉田氏は「庫内の生産性と高い品質もSBSフレック冷凍プラットフォームの強みにしていきたい」と強調とした。

▲グロスで仕分けされた荷物を、マルチカートなどを使って膨大な数の細かなピッキングを行う。ルート別に分けられた荷物を、配送網を使って最後まで運びきる。
ここ数年で利用が増えているのは冷凍食品だけではない。コロナ禍の「おうち需要」で、EC(電子商取引)の利用は2019年の19兆2800億円から、23年には23兆6900億円へ成長。24年には27兆円規模に達するといわれている。厚木物流センターでは、冷凍食品のEC(電子商取引)需要にも応えていく構えだ。
 全国で大型冷凍拠点を強化しBCPにも対応
全国で大型冷凍拠点を強化しBCPにも対応
SBSフレックは昨年、6月に仙台、7月には北海道・石狩、さらにことし2月には九州に次々と大型の冷凍拠点を開設し、この厚木が第4の大型拠点となる。その厚木物流センターは足元である関東圏の1都6県をカバーする拠点としての機能を果たすのはもちろんだが、「全国の冷凍物流ネットワークの『マザーデポ』としての役割を持たせる」(吉田氏)というプランなのだという。
SBSフレックのいうマザーデポはいわば、同社の物流ネットワークの総合窓口。荷主は厚木センターに納品しさえすれば、同社が全国に持つ配送ネットワークを利用して、日本中に冷凍品を流通させることができるというのだ。保管はもちろんのこと、北海道、宮城、福岡の在庫も合わせて管理することで、不足のあるエリアには厚木から補充が行うことができる。また、拠点間での在庫の融通も可能だ。

▲執行役員・関東統括支店長の小河原勝行氏
厚木物流センターに入荷した荷物はすべて「ロット単位、日付単位で管理。ピッキングのタイミングで配送先までひも付けられ、入荷から出荷、配送までのすべてのプロセスでトレース可能」(執行役員・関東統括支店長の小河原勝行氏)になっており、この情報は荷主も閲覧可能。冷凍食品はリードタイムが長いので、厚木に荷物を集積した上で全国の在庫の配置や量の調整などを行うことができる。
また、特定の配送拠点が災害で機能しなくなった際も、近隣の拠点から必要な荷物を集めるといったコントロールもできることから、事業継続性を担保する役割も担う。
さらに、ある配送拠点で特定の商品が大量に必要となるようなケースにも、できるだけ近い拠点から必要な数を手配することでリードタイムを短くするといった運用も可能となる。荷主は個別の配送拠点やエリアへの配送の手間を意識することなく、ひたすら厚木という窓口的な拠点に荷物を運んでしまえば、全国の隅々まで商品を流通させることができるのだ。集荷もSBSフレックに任せるのであれば、出荷の輸配送についても考える必要がなく、自社の製品の製造に専念していればよいことになる。
 厚木物流センターで実現する「冷凍物流プラットフォーム」
厚木物流センターで実現する「冷凍物流プラットフォーム」
 ここまではどちらかというと物流の川下の動きばかりを紹介してきたが、同社が冷凍物流において提供するのは保管、配送だけではない。原料の調達先の材料の納入や在庫調整など、製造と物流の川上のプロセスもカバーし、サプライチェーン全体の物流サービスを提供することを通して、冷凍食品の製造と物流のあらゆるプロセスに関与するというのが、SBSフレックの構想だ。「メーカーであれば製品作りに、ファブレスの企業であれば商品企画と営業だけに専念してもらえる」(吉田氏)ような冷凍物流を実現していく。これが同社の思い描く「冷凍物流プラットフォーム」だ。旧来の3PLの枠組みを超えたサービスを全国規模で展開していく予定だ。
ここまではどちらかというと物流の川下の動きばかりを紹介してきたが、同社が冷凍物流において提供するのは保管、配送だけではない。原料の調達先の材料の納入や在庫調整など、製造と物流の川上のプロセスもカバーし、サプライチェーン全体の物流サービスを提供することを通して、冷凍食品の製造と物流のあらゆるプロセスに関与するというのが、SBSフレックの構想だ。「メーカーであれば製品作りに、ファブレスの企業であれば商品企画と営業だけに専念してもらえる」(吉田氏)ような冷凍物流を実現していく。これが同社の思い描く「冷凍物流プラットフォーム」だ。旧来の3PLの枠組みを超えたサービスを全国規模で展開していく予定だ。
これまでSBSフレックは特定のメーカー、荷主の物流に携わることが多かったが、強みが生きる時流に合わせて、より多様な荷主の物流を担う方向に舵を切りつつある。数多の強豪がひしめく中で同社が武器とするのは、「大手では真似のできない低コストと、エリアごとに完結させることができる全国の小口輸配送配送網」(岡野氏)だ。来年4月からは茨城県阿見町の拠点も本格稼働を始める。首都圏から一気通貫で全国への配送が可能な同社のサービスの今後に期待したい。
 所在地:神奈川県厚木市飯山南3110
所在地:神奈川県厚木市飯山南3110冷凍:1万9000トン(5度〜マイナス25度対応)
冷蔵:8600トン(5度)
バース:11台
詳細:https://www.sbs-flec.co.jp/flec/atsugi/
電話:0120-836-095
メール:okano.kosei@sbs-group.co.jp(担当:岡野氏)