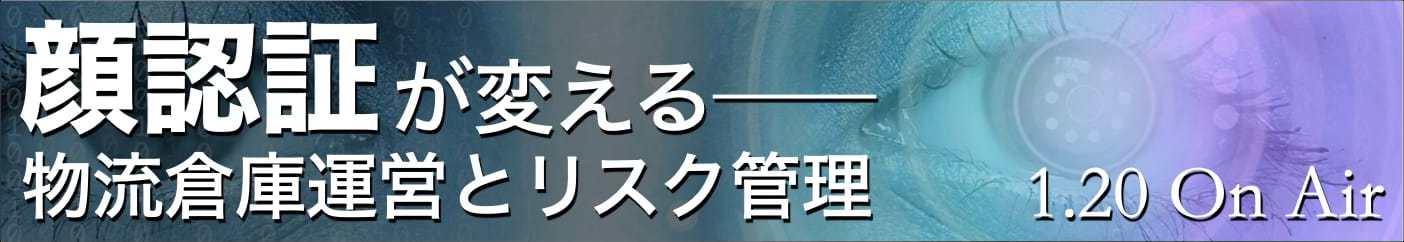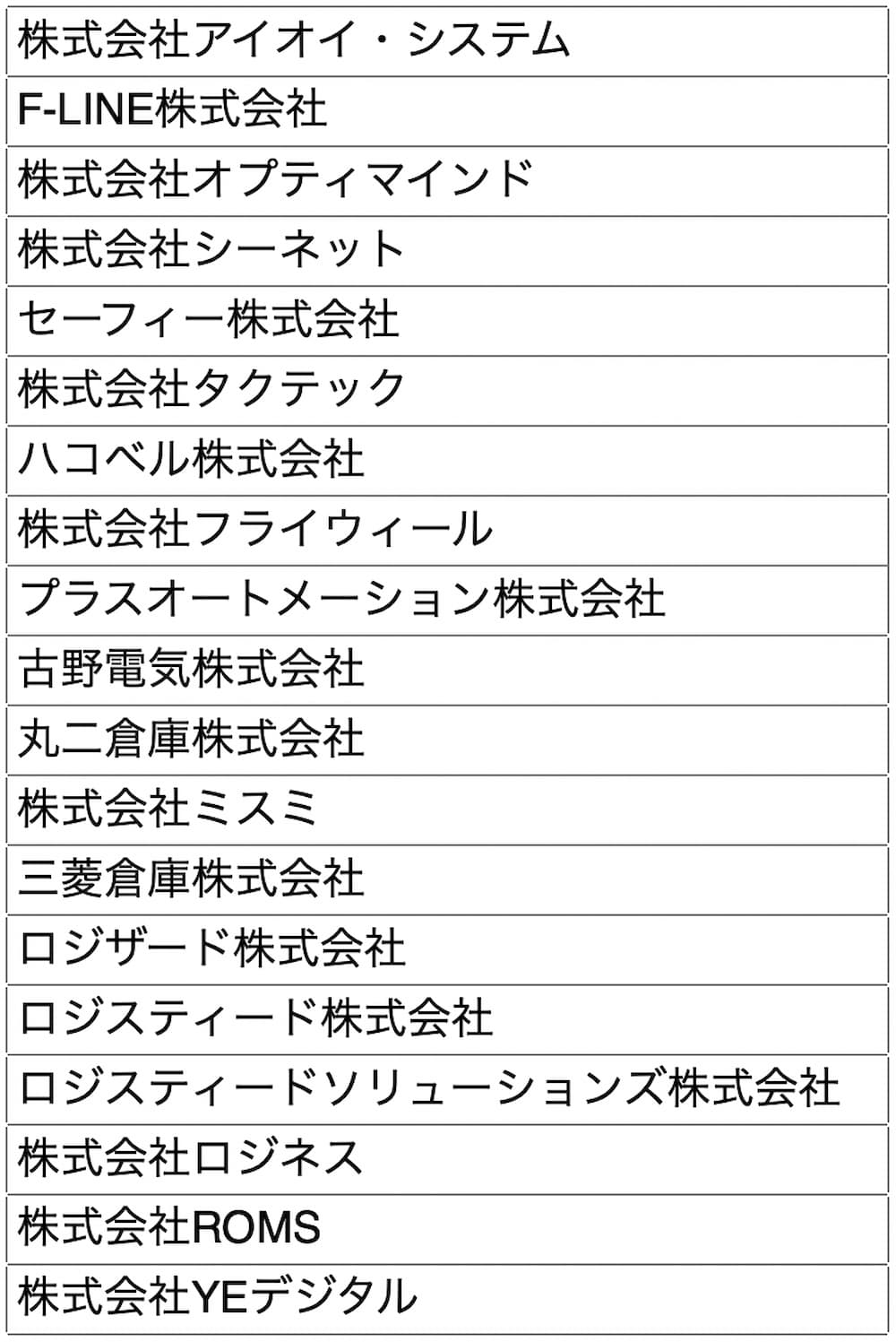ロジスティクス変革のシナリオと将来像を巡る本格的な議論が熱を帯びた。22日にLOGISTICS TODAYが主催したオンラインイベント「第三回物流DX会議」では、ライブ配信のセッションの裏側で、荷主、物流会社、ソリューションベンダーが物流の未来について議論するラウンドテーブルを開催。本稿ではその後半戦をレポートする。
<<【ラウンドテーブルレポート前編はこちら】「ガラパゴス化と「肌感覚」運営からの脱却を議論」
 データ活用とシステム標準化で挑む物流変革
データ活用とシステム標準化で挑む物流変革
後半戦の第二ラウンドでは、現在各社が直面する課題への対応策から、根本的な解決に向けて国や自治体、ベンダーに期待する支援まで、参加者が自身の経験に基づき、率直に意見交換をした。議論は次第に深みを増し、単なる現状報告を超えた。今後の取り組みへの展望や課題認識について、建設的な対話が続いた。参加者それぞれが立場から見た変革の必要性と、その実現に向けた現実的なアプローチについて、有意義な情報を共有した。

▲ラウンドテーブルの様子
 データ連携の範囲拡大と事務作業の場所的制約からの脱却
データ連携の範囲拡大と事務作業の場所的制約からの脱却
データ活用戦略の大胆な方向転換が俎上に載った。これまでWMSなどに眠る膨大な物流情報の宝庫を、在庫回転率の解析や拠点間配送の効率化といった「身内の論理」に閉じ込めていた従来路線を一変。今度は自社の守備範囲を超えた未踏の領域へと、データの触手を大胆に伸ばす構想が打ち出された。具体的には、メーカーから卸、小売まで一貫したデータ連携により、短期的なリターンは見込めなくとも、長期的な価値創造を目指すアプローチを提案した。
また、倉庫業界特有の課題として、事務作業の場所的制約からの脱却を議論した。従来は倉庫内の事務所で担っていた業務を、立地や労働環境の良い場所に集約することで、人材確保と業務効率化の両立を図る取り組みを紹介した。
 システム標準化とバース管理の運用課題解決
システム標準化とバース管理の運用課題解決
さらに、データの標準化と連携を最重要課題として位置づけた。製造業における物流部門が個別システムを構築することでAPI連携が複雑化し、システム構築者の退職によりメンテナンスが困難になる多数の事例について報告があった。この課題に対し、標準APIの社内統一や、異なるフォーマットのデータを効率的に活用する仕組みの構築が急務という声が挙がった。
バース管理システムの運用課題も深刻な問題として議論した。システム導入後もドライバーの操作不備や運用の不完全性により期待した効果を得ていないケースが多発している現状を報告。この解決策として、入退場管理システムとの連携により、人的操作に依存しない自動化の推進を提案した。
 補助金制度改善と国主導の標準化推進への期待
補助金制度改善と国主導の標準化推進への期待
あるテーブルは、補助金制度の改善を強く求めた。特に物流DX補助金については、申請期間の短さ(2週間程度)と単年度制限により、中小企業が活用困難な状況を指摘。制度設計の見直しと、より使いやすい補助金制度の構築を要望した。
標準化の推進についても国の積極的な関与を求めた。個別最適に陥りがちな業界特性を踏まえ、サプライチェーン全体での最適化を実現するためのリーダーシップに期待した。また、オープンプラットフォームの構築について、発荷主、着荷主、運送会社がそれぞれ異なるシステムを使用している現状を改善し、共通のプラットフォームを通じた効率的な情報連携の実現を提案した。

▲ラウンドテーブルの様子
 水平分業型ロボット開発とサプライチェーン情報連携
水平分業型ロボット開発とサプライチェーン情報連携
また、別のテーブルではロボット技術の活用について水平分業型へのアプローチの提案があった。従来の垂直統合型ロボット開発とは異なり、ハードウェア、制御システム、物流アプリケーションをそれぞれ専門企業が担当し、協業により最適なソリューションを提供する手法が注目を集めた。これにより、コスト削減とユーザーニーズへの柔軟な対応が可能になるとの見解を示した。
データ活用の新たな取り組みとして、従来のWMS活用範囲を超えて、サプライチェーン全体での情報連携を目指す方向性を議論した。特に、自社が直接関与しない領域まで情報をつなげることで、最終ユーザーまでのメリット創出を図る取り組みを紹介した。
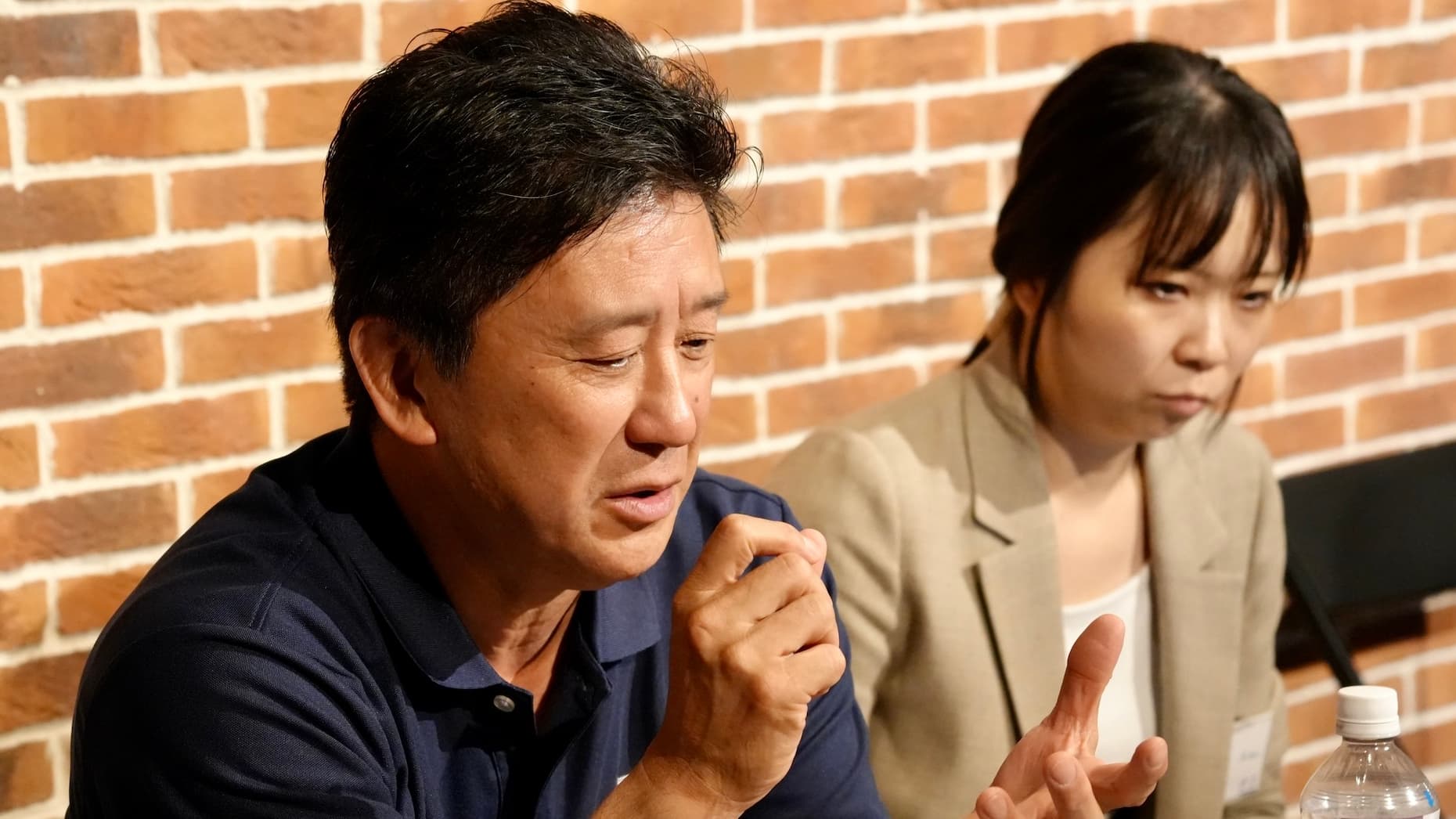
▲ラウンドテーブルの様子
 ETC活用入場管理システムと可視化ソリューション
ETC活用入場管理システムと可視化ソリューション
ある参加者は、ETC車載機を活用した革新的な入退場管理システムを紹介した。従来のナンバープレート認識システムの課題である天候による認識精度低下を克服し、ETCとカメラのハイブリッド方式により確実な車両識別を実現している。このシステムは港湾や製造現場で実用化し、無人化による人件費削減と履歴管理の完全自動化を達成している。
さらに、横連携と可視化を重視したソリューション提供により、リアルタイムでの滞留状況把握と改善のための基礎データ提供を実現している事例を報告。企業が自社の滞留状況を正確に把握できていない現状を改善する取り組みを評価した。
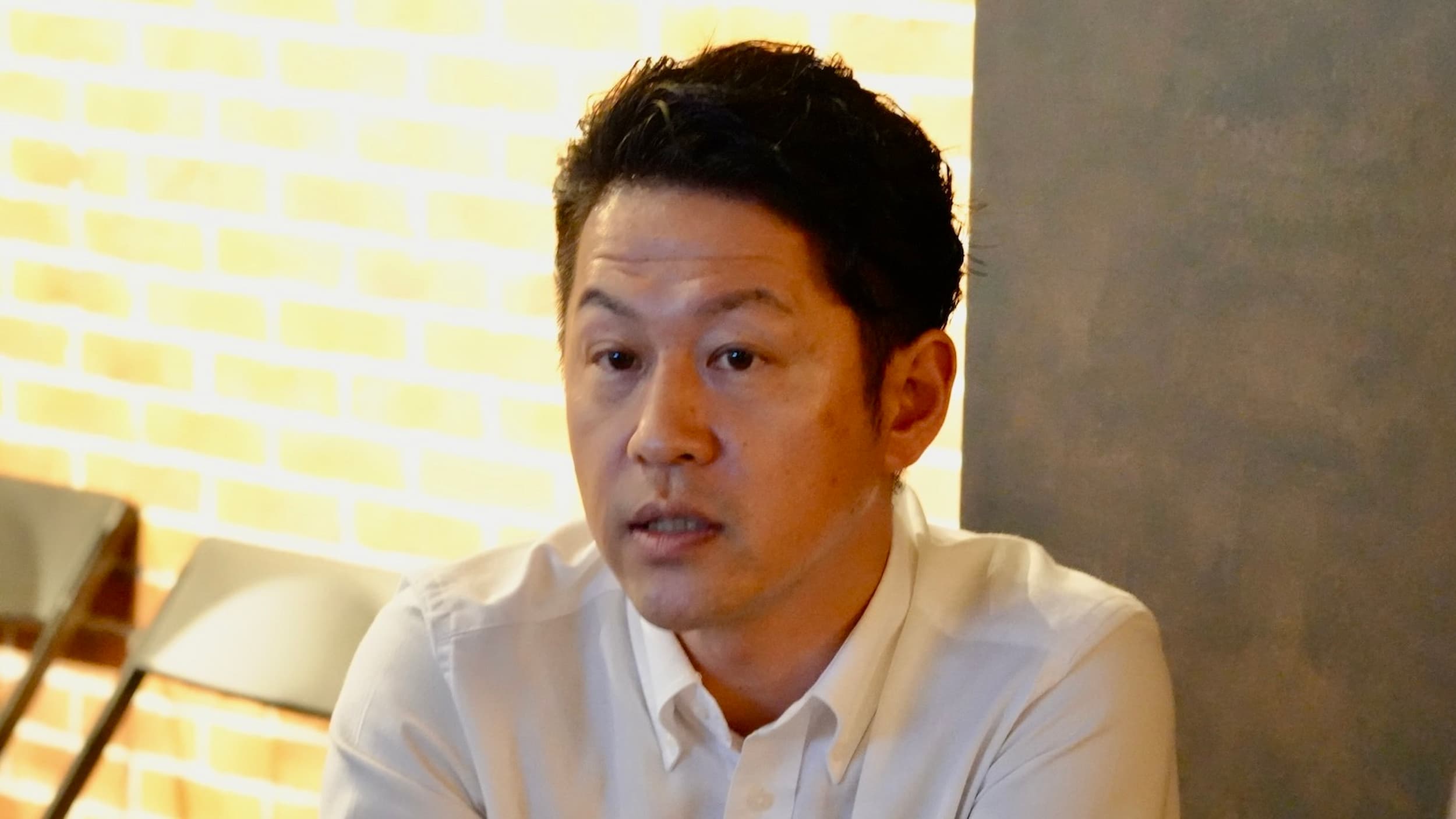
▲ラウンドテーブルの様子
 業界イメージ向上と課題解決型営業への転換
業界イメージ向上と課題解決型営業への転換
また別のテーブルでは、物流業界への注目度向上を重要課題として提起した。CLO(Chief Logistics Officer)設置の動きを評価したが、さらなる加速が必要と一同が声を揃えた。また、物流の関連団体が多すぎるとの指摘があった。展示会や会議を統合すれば、業界関係者の負担軽減と効率的な情報交換が実現できるとの提案があった。
補助金制度については、中小企業向けの手厚い支援継続と申請手続きの簡略化への要望があった。ベンダーに対しては、課題解決型営業への転換を強く求め、自社製品の販売に固執せず、顧客の真の課題解決に最適なソリューションを提案する姿勢を重要視した。
また、自動化プロジェクトにおいて参加者が求めたのは、一期一会の商売からの完全脱却だ。誠実なコミュニケーションと戦略的な予備費設定による堅実なプロジェクト運営、そして導入後も見捨てない生涯サポート宣言、これこそが物流DX成功の新たな方程式だと、参加者は熱く語り合った。
 強調と共創による業界全体の発展を目指して
強調と共創による業界全体の発展を目指して
後半では協調と共創の重要性を強調した。競争ではなく協業により業界全体の発展を目指す姿勢を、参加者間で共有した。あるテーブルから浮上した「物流をかっこいい業界に」という提言は、まさに傾聴に値するものだった。物流業界を蝕む慢性的な人手不足の根深い要因を、業界全体に染み付いた「地味で泥臭い」というイメージに鋭く切り込んで分析。人材を引き寄せる業界ブランディングと、くすんだ印象を一新する戦略について、熱のこもった議論が繰り広げられた。フィジカルインターネットの実現に向けた人材育成の重要性も指摘した。国の政策目標達成には民間企業の積極的な参画と、それを支える人材の確保・育成が不可欠とした。
参加者は異業種間の対話機会を業界の孤島化からの脱却への第一歩と位置づけ、継続的な協業関係の構築への熱い期待を込めて語った。信頼関係は名刺交換のみでは生まれず、共に汗を流す実践の場で醸成するものとの声があった。小規模でも血の通った共同プロジェクトの積み重ねが業界変革の礎石になるとの共通認識に達した。自社の利益追求という狭い枠組み的発想を超え、業界全体の発展を目指す大河の流れへの転換こそが、物流DX推進の真の原動力となることを参加者は確信している様子だった。
<<【ラウンドテーブルレポート前編はこちら】「ガラパゴス化と「肌感覚」運営からの脱却を議論」
■「第三回物流DX会議」配信会場で併催されたラウンドテーブルの模様(後編)
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。