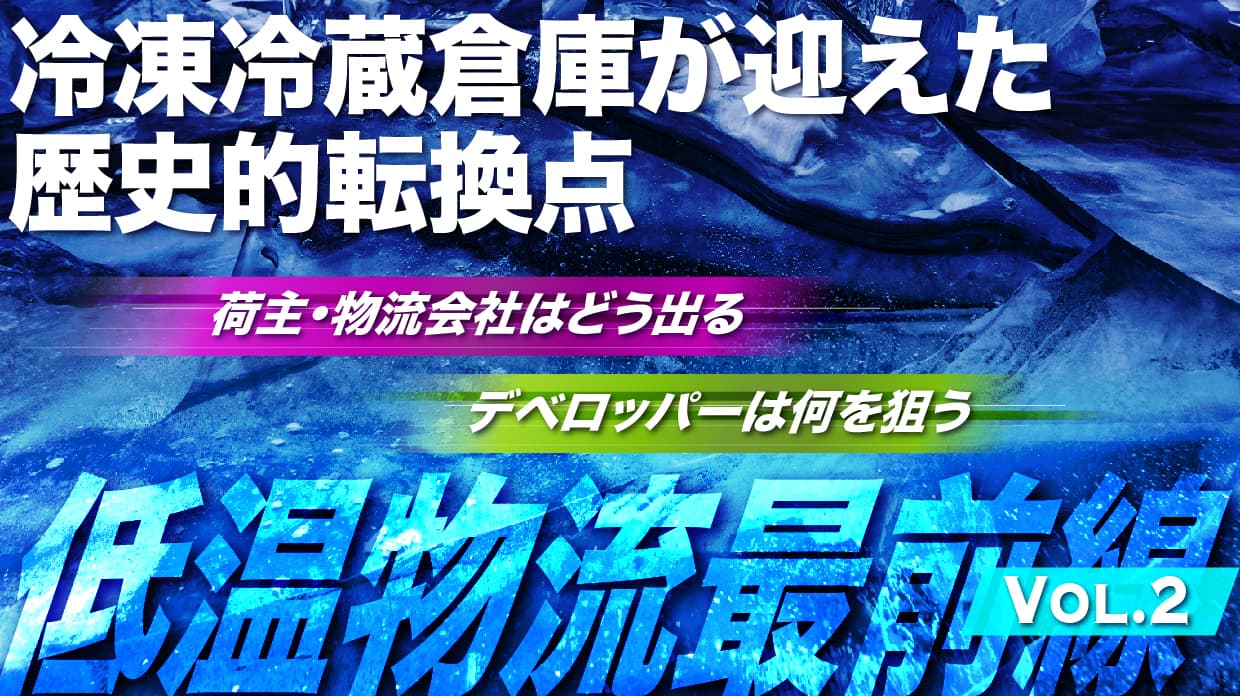
話題低温物流の変革期を迎え、これまで自社倉庫運用が主流だった冷凍冷蔵市場にデベロッパーが参入、賃貸型での運用提案が相次いでいる。それに対して、ユーザー側も今後は低温物流拠点の賃貸利用意向が4割以上と高い数字となり、そのうちの65.5%がマルチテナント型を希望するという結果が本誌アンケートでも確認されており、デベロッパー側の今後の取り組みにも大きな影響を与えそうだ。
本誌では、デベロッパーを対象に、各社のこれまでの冷凍冷蔵施設開発の取り組みや今後の計画についてアンケート調査した。ユーザーサイドの期待に対して、供給側の動向はどうなっているのだろうか。
 冷凍冷蔵施設開発意向の高まり明確に、施設市場は新たな局面
冷凍冷蔵施設開発意向の高まり明確に、施設市場は新たな局面
デベロッパー16社からの回答では、今後の「冷凍冷蔵施設」開発予定なしとしたのは1社のみ、他のデベロッパーはすべて開発予定ありとして、94%のデベロッパーが市場の活況を感じ取って対応の必要性を認識しているのがわかる。
ただ、開発を予定する施設の種類に関しては、ユーザー側で利用意向が強い「設備既設のマルチテナント」を限定した回答は3社にとどまった。マルチでの開発を目指すとした3社はいずれも、すでに同様の施設を開発・企画中としており、マルチ開発で先行するデベロッパーによるスタートダッシュが市況の盛り上がりを演出していることがわかる。
マルチテナント冷凍冷蔵施設開発を目指す具体的な理由の回答では、「冷凍食品の成長、フロン規制による既存倉庫の設備入れ替え、老朽化による建て替えなどでニーズが増えてくる」と、さらなる市場の拡大を想定してのものや、「テナントの入居を決定するタイミングが竣工直前から1年前であることが多く、BTS型のテナント探索が困難なため、建物を先行着工させ、マルチ型のテナントニーズを拾っていくことが必要」とする意見が得られた。ニーズが発生してから施設を用意するのでは間に合わず、あらかじめ標準的施設を用意しておくべきという姿勢での開発が、冷凍冷蔵施設市場を開拓しているデベロッパーの取り組み姿勢となっている。

![]()

▲冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応したマルチテナント型物流施設(左から)「DPL大阪舞洲」、「GLP川崎II」の完成イメージ(出所:大和ハウス工業、日本GLP)
なかでも、BTS1棟(延床面積1万5918平方メートル)とマルチテナント11棟(合計延床面積29万1922平方メートル)と突出した開発計画を回答したデベロッパーは、「すでに施設開発を手掛けて実際の需要の高さを感じる」ことを、積極展開の理由に挙げる。また、「自社で冷凍冷蔵倉庫を開発すると2、3年はかかり、ドライ倉庫を賃借して冷凍設備を敷設するにも1年はかかる。設備投資が不要な冷凍冷蔵倉庫をデベロッパーが供給すれば、クイックスタートを望む3PL事業者や荷主が、初期投資を抑えながらコンパクトでスピーディーな成長を追い求めることができる」と、マルチテナント冷凍冷蔵施設開発のパイオニアとして、ユーザーの利用意向をキャッチアップした結果の開発であることがわかり、「先行逃げ切り」の戦略を展開する予定だ。
 根強いBTS型開発という現実的な施設供給の取り組み
根強いBTS型開発という現実的な施設供給の取り組み
そのほかの「開発計画あり」とする企業では、マルチテナントかBTSか、どちらでの開発を計画しているのかとの質問に、「その他」あるいはマルチとBTSを併記する回答が多く、現状賃貸の種類は未定ながら、テナントとの調整のなかでニーズを確認しながらというニュアンスでの開発を目指すようである。低温物流ニーズの高まりは認識しながらも、「今後の開発における、あらゆる選択肢にマルチも含まれる」という対応となっている。
現在市場をリードしているデベロッパーは、すでにBTS、もしくは後付け型マルチでの開発経験を踏まえて、既設のマルチテナント開発に踏み切ったケースが多く、今後開発を本格化させるデベロッパーでも、まずはリアルな利用者のニーズや要望を把握することからノウハウを積み上げようと行動している。
現在開発中の物件では、後付けマルチが3社4棟、BTSが3社3棟、既設マルチは3社17棟と、既設マルチの開発が急増しているが、そのうち16棟が「今後も既設マルチ開発を予定する」2社によるものであり、現状では賃貸型既設マルチ型冷凍冷蔵倉庫は、ノウハウを固めたデベロッパーが独占する状況になりつつある。

▲冷凍冷蔵物流施設開発を推進する霞ヶ関キャピタルが手掛ける冷凍自動倉庫「LOGI FLAG TECH 所沢I」の完成イメージ(出所:霞ヶ関キャピタル)
一方、これまで、冷凍冷蔵施設の開発実績のないデベロッパーのうち、今後BTSに限定しての開発予定ありとするのが2社。現在、すでにBTSで開発中という1社は今後もBTSでの開発を計画する。冷凍冷蔵施設の開発歴のない企業の回答では、今後の開発予定にBTSとマルチを併記し、「現在、開発用地の仕込みに取り組んでいる」として、新たな領域への取り組みを不可避としながら、市場を見極めているようである。
後付けマルチの開発実績を持つデベロッパーの1つは、これまでの経験を踏まえた上で、あえて今後の開発予定をマルチではなく、BTSと回答する。設定温度や需要率など要望が多岐にわたるため、「マルチテナントとしての開発よりもBTSとして開発する方がテナント企業にとって使いやすい施設を提供できる」ことを理由に挙げる。ただし、「マルチテナントの後付けタイプの入居受け入れは案件次第で検討する」予定だとして、あくまでもテナント意向に沿った開発を計画する。
現在、後付けマルチを開発中のデベロッパー3社のうち1社は、今後も「オプションとして後付けできる開発を続ける計画」。別の1社も、今後については「顧客ニーズに柔軟に対応する」として、テナントニーズを推し量る状況のようだ。

▲キユーソー流通システム専用の冷凍冷蔵拠点として開発された「プロロジスパーク仙台泉」(出所:プロロジス)
BTSで開発に新たに取り組んでいるデベロッパーは明確に、「冷凍冷蔵の設定温度帯は各社違うため、マルチでの計画にはハードルを感じる」として、テナント意向に基づいたBTSでの開発を重視すると回答している。業界では大手とされるデベロッパーの1つも、「冷凍冷蔵倉庫に関するスタディは随時行っている」として、BTS案件の開発にはいつでも取り組める状況だが、マルチに関しては検討段階と回答する。地域デベロッパーからは、そもそもまだマルチテナントの冷蔵冷凍倉庫がなく、市場性がわからないため、地方ではまずはBTSの開発でノウハウを蓄積する段階とする。
 これまでにない「トレンド」に定着した冷凍冷蔵施設開発
これまでにない「トレンド」に定着した冷凍冷蔵施設開発
このようにマルチテナントで既設の冷凍冷蔵施設を開発するという動きは、デベロッパーにも先読みのできないリスクを抱えたプロジェクトであり、市場の盛り上がりに比べると慎重な姿勢もうかがえる。ただそれだけを見て、積極派と消極派に二分される判断とするのは、やや早計かもしれない。
マルチテナントだけで見れば、市場で先行するデベロッパーの動向が際立つのは確かだ。しかし、回答を寄せたほとんどのデベロッパーが、BTSであれ、形態未定であれ冷凍冷蔵施設開発に取り組もうとしているのは、これまでの賃貸施設供給ではあり得なかった大きな変革であることは間違いない。

▲「ロジポート北柏」に増築した冷凍冷蔵倉庫。今後、既存施設への増築ニーズが拡大する可能性も低くはないだろう。(出所:ラサールロジポート投資法人)
ドライ型倉庫も登場当初は疑問視されながらも、20年の時を経てすっかりと「標準」として定着してきた変化が、今、冷凍冷蔵施設においても始まったばかりだと捉える方が正解ではないか。先行者による積極的な開発に加えて、それに追随して市場拡大を目指す開発が続くことで、さらなる大きな物流市場の変化のうねり、新たな変革期となる様子を目の当たりにしているのだと気付く。物流施設市場の新しい潮流の入り口に立っていること、そこで今やるべきことは何かを、各デベロッパーが真剣に模索している状況なのである。
パンデミック1つで大きく消費構造が変わったように、不確実な未来だからこそ、ユーザーにとっては、多様な選択肢が必要だということは間違いない。未来にあるべき冷凍冷蔵物流施設の標準型も、社会の変化や時代の流れでさらに変化することも予想される。ドライ倉庫が標準化に要した時間を考えると、デベロッパーによる冷凍冷蔵施設の開発は、まだ横一線でスタートを切ったばかりなのだ。





















