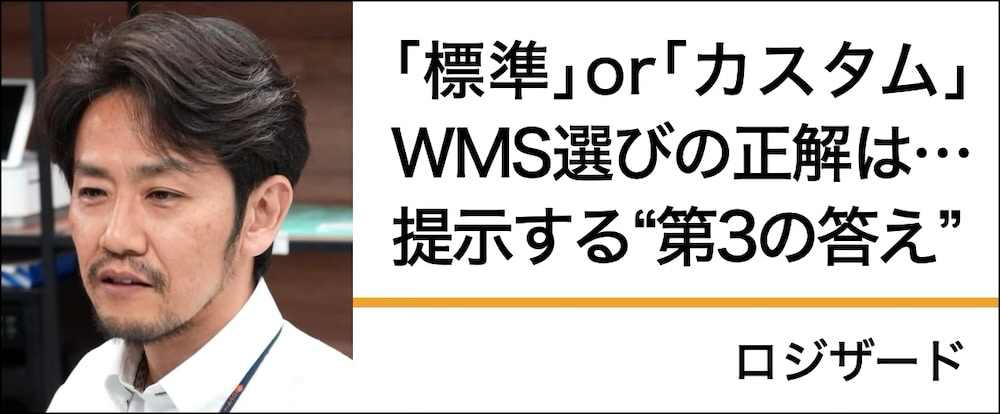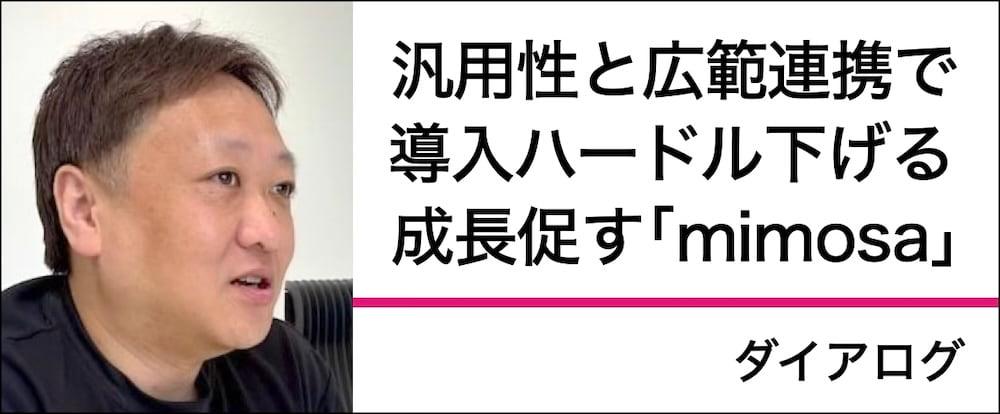話題物流業界が直面する最も深刻な課題の一つは、人手不足と人件費の増加である。高齢化によるドライバーや庫内作業員の減少、採用コストの高騰は、物流センターの運営維持をますます困難にしている。その一方で、EC(電子商取引)市場の拡大、温度管理を要する食品・医薬品などの取り扱い増加により、オペレーションは複雑化するばかりだ。物流現場の省力化・効率化を進めなければ、事業継続さえ危うい時代が来るのは間違いない。
この根本的課題を解決するには、アナログ管理からデータを前提とした管理体制への転換が不可欠である。誤出荷や棚卸差異を減らし、正確な在庫情報をリアルタイムで把握する仕組みは、人手不足を補い、業務品質を安定させる物流の生命線となる。
さらにことしは、経済産業省が注意喚起した、デジタル化・業務効率化の遅れが日本産業の経済的損失に直結するという「2025年の崖」の真っ只中にあたる。高齢化による技術継承問題、レガシーシステム刷新の遅れは、物流危機に直結する。属人的でブラックボックス化した倉庫管理では、ベテランが退職した瞬間にオペレーションが崩壊しかねない。倉庫管理システムによる業務知識の形式知化と、誰もが扱えるデータ基盤の整備は、「崖」を回避するための最重要課題であるとともに、各社の中核システムがレガシーシステムとなっていないかも、確認する必要がある。
 「庫内管理ツール」から「データ基盤」への進化
「庫内管理ツール」から「データ基盤」への進化
WMSはこれまで、庫内DX(デジタルトランスフォーメーション)の入り口として、入出庫管理やロケーション管理、棚卸などをシステム化し、人的ミスを減らし業務を標準化する役割を果たしてきた。しかし早期にデジタル化を進めた企業ほど、古いWMSの「レガシー化」に悩むケースも少なくない。独自仕様へのカスタマイズを重ねた結果、保守が難しくなり、新たな自動倉庫や搬送ロボットとの連携改修コストが膨張している現場もある。
一方で、庫内自動化への投資を最大限に生かす中核は依然としてWMSだ。各設備から得られるデータをWMSが柔軟に取り込み、最適な入出庫計画や在庫配置を生成し、より効率的な運用へフィードバックできなければ、せっかくの自動化投資の効果も半減する。
もはや「庫内管理だけ」で完結する時代ではない。マテハン、受発注、調達、配送といった外部データを取り込み、活用し、全体最適を設計するための「データ基盤」として進化することこそ、WMSが果たすべき新たな使命となっている。

 個別最適化から全体最適化へ-標準化とデータ連携の必然
個別最適化から全体最適化へ-標準化とデータ連携の必然
黎明期のWMSは「個別最適化」によって、荷主や業種ごとのフローに対応する細やかなカスタマイズこそが、ベンダーの差別化ポイントであり、運用企業の競争価値を高める源泉だった。しかし今日、物流業界全体が「個別最適化の限界」に直面している。庫内だけを最適化しても、配送計画や調達計画、在庫戦略と連動しなければ、サプライチェーン全体の効率化は実現できない。
在庫過多や欠品、無駄な横持ちや長時間待機といった課題を解消するには、製造、荷主、物流事業者、卸、小売まで含む情報共有が不可欠であり、業界一丸で「全体最適化」に向けた大転換が求められている。WMSも、閉ざされたデータによる個別カスタマイズではなく、標準化や連携しやすさが評価される局面を迎えている。
ここで重要なのは、WMSに求められる「標準化」が差別化を消すものではないという点だ。API対応や他システムとの連携機能は当たり前になっても、これは競争をなくすのではなく、差別化のスタートラインを底上げする動きとなるだろう。標準機能を常にブラッシュアップしながら、「どのデータを、どのタイミングで、どのように活用するか」が、ベンダーごとの真の競争軸になる。
 標準機能は「どれも同じ」ではない、未来のSCハブを見極めよ
標準機能は「どれも同じ」ではない、未来のSCハブを見極めよ
標準インターフェースやAPI接続が必須条件に近づく一方で、物流オペレーションはむしろ複雑さを増している。ECの拡大と多様化、温度帯管理、トレーサビリティ要求、短納期化など、管理要件の高度化も進む。WMSは単なるデータ管理ツールではなく、庫内全体の業務を可視化し、課題を抽出し、改善を提案するための基盤として機能することが前提になる。
そのため、ベンダー間の差別化は「ソフトの機能」だけではなく「物流業務設計力」「業界特化対応力」「現場への運用支援力」、さらに「データ活用提案力」などへシフトするのではないだろうか。標準化が進むからこそ、実装・運用フェーズでの差が企業の競争力を左右する時代となる。
利用者側も、単なる機能比較ではなく、自社の物流課題を共有し、解決を支援してくれるパートナーとしてベンダーを評価する必要がある。導入実績などを参考にしつつも、その「事例」が自社の課題解決にどの程度フィットするか、どれくらい真摯に向き合う姿勢かを見極める視点が重要だ。
現場ごとの運用特性、商流・物量・人員の違いはむしろ多様化し、それぞれの現場に即したWMSの柔軟性は必要不可欠だ。WMS機能も標準型に集約されるのではなく、連携可能性の拡張、場合によってはWMS間の連携も含めて、サプライチェーン全体の在庫情報を束ねるハブへと成長していくのではないか。

 サプライチェーンをつなぐ情報ハブとしてのWMS
サプライチェーンをつなぐ情報ハブとしてのWMS
では、サプライチェーン全体の在庫情報を束ねるハブとしてのWMSが、他領域と連携することでどのような具体的メリットが生まれるのだろうか。
調達領域との連携では、発注計画と入荷予定をWMSに反映し、庫内作業の段取りを事前に最適化できる。人員配置の平準化や無駄な待機時間削減につながる。
バース管理との統合では、トラック到着予定をWMSが取得し、入荷・出荷作業計画をリアルタイムに反映させることで、バースの混雑を緩和し、ドライバー不足時代に重要な稼働効率を向上できるだろう。配送計画や動態管理システムとの連携では、出荷オーダー情報を事前共有し、ピッキング計画を自動生成することで人的負荷を軽減。配送ルートや積載率の最適化と出荷タイミングを連動させれば、CO2排出削減など社会的課題解決にも貢献する。
このように、WMSは庫内を超えた調達計画、バース計画、配送計画までをつなぐ情報ハブとなり、全体最適を実現するためのプラットフォームへと進化していくことが期待されている。荷待ち・荷役時間の削減、積載率の向上などは、一刻も早い「成果」が求められる状況だ。現状の施策に満足せず次の改善を検証し続けることは、今まで目が届かなかった領域までも俯瞰すること。WMSを通してサプライチェーン広域を可視化することが、抜本的な物流革新に臨む基本姿勢となる。
 業界構造変化に対応する、共通言語としてのWMS
業界構造変化に対応する、共通言語としてのWMS
WMSベンダー各社に話を聞くと、近年、WMSは物流倉庫領域だけでなく、製造業の現場で活用が広がっているという。基幹システムを補完するためのWMSでは、すでに現状の物流環境に対応できないことに加え、特定荷主事業者、特に大手メーカーなどにCLO(物流統括管理者)設置が義務化されることで、調達計画や生産計画と、物流計画における分断を排除し、一体で業務設計する責任が問われるようになったことも影響しているのだろう。
サプライチェーンの最適化に向けて、WMSは、庫内在庫だけでなく調達先や生産工程の在庫情報とも連携し、基幹システムなどの上位システムとデータをシームレスに結ぶことが重要となる。単なる社内最適化ツールを超え、持続可能なサプライチェーンを支える共通基盤として、産業全体でのデータ利活用を促す役割を担う。物流コスト削減のためだけの効率化ではなく、社会的責任としての効率化へと、より高い視座で活用されるツールとならなければならない。

荷主だけではない。3PLや物流事業者を中心に、運送事業者やソリューション提供者にも、LPD(Logistics Producer)という概念のもとでCLOのカウンターパートとして課題を分析し、提案する力が必要という考え方が示されるようになった。WMSは、こうしたCLOとLPDをつなぐ共通言語として、多様なジャンルやレイヤーのデータ共有を促す中核となる。それに伴って、WMSベンダー自身もまた、CLOとLPDと同じ高いレベルの「データ活用提案力」を備えなくてはならなくなるだろう。
物流は、もはや1社だけが効率化を追求しても意味のない時代に入った。個別最適を超え、共同化・標準化を通じてサプライチェーン全体を変革するためには、CLO体制が有効に機能することが重要だ。CLO同士はもちろん、CLOと直接・間接的につながる物流関係者全員に、閉ざされたデータではなく共同利用できるデータを集めていくことで、今まで気づかなかった改善点も見つかるかもしれない。
CLOを中心とした物流革新の「管制塔」が物流を俯瞰し、その判断の拠り所とするのがWMSである。「2025年の崖」から飛び立たなければいけない私たちが、WMSの変化と進化が指し示す未来に向けてどんなルートを選ぶのか、他人事ではなくそれぞれの領域からフライトプランを示すときである。
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。