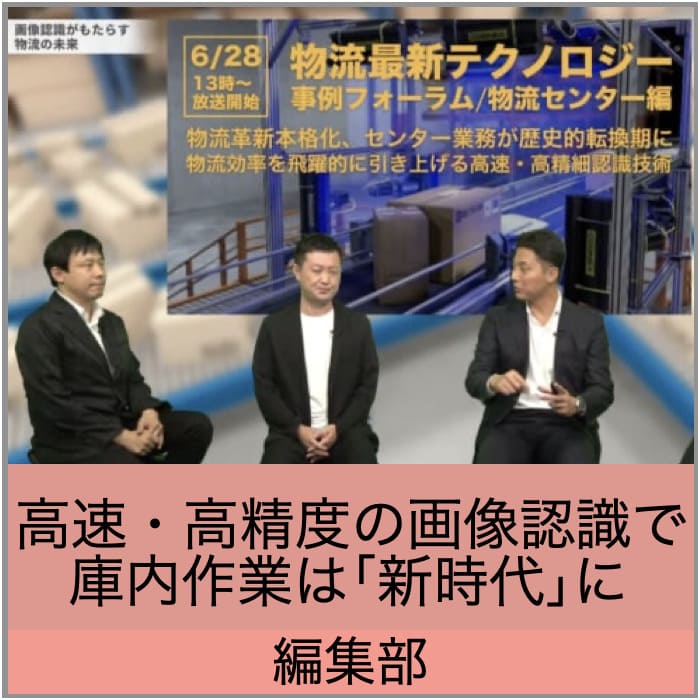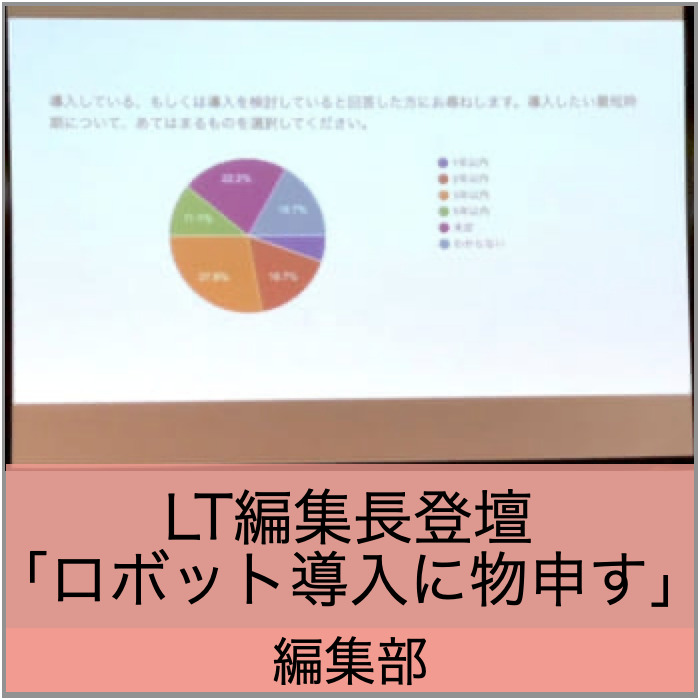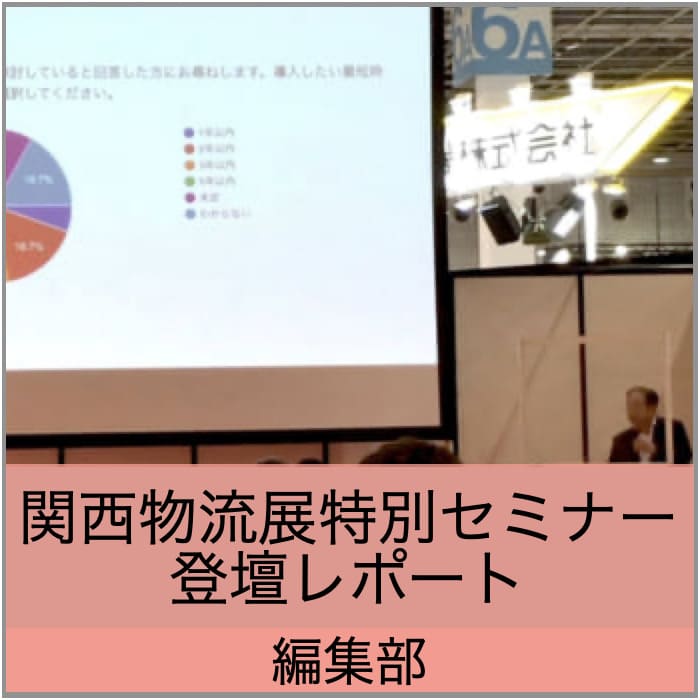話題 LOGISTICS TODAY(東京都新宿区)の赤澤裕介編集長と永田利紀・企画編集委員が登壇した、「第3回関西物流展」「第1回マテハン・物流機器開発展」の特別セミナー講演「物流ロボット導入事例、隠された『その後』を徹底追跡〜忖度なし。使えたのか、使えなかったのか〜」の現地レポート。第2回は、ロボット導入における「目的」と「手段」の明確化について考えます。
LOGISTICS TODAY(東京都新宿区)の赤澤裕介編集長と永田利紀・企画編集委員が登壇した、「第3回関西物流展」「第1回マテハン・物流機器開発展」の特別セミナー講演「物流ロボット導入事例、隠された『その後』を徹底追跡〜忖度なし。使えたのか、使えなかったのか〜」の現地レポート。第2回は、ロボット導入における「目的」と「手段」の明確化について考えます。
 自動化を「仕入れる」発想からの脱却を
自動化を「仕入れる」発想からの脱却を
<赤澤>
「ロボットを導入して失敗している」と今の時点で認識してる方はそんなに多くはないんですけれども、ただ実際にですね、取材を進めてみるとなんとなく違和感を抱くことがあります。特にロボットの取材では、非常に多くあるんですよ。
どういうことかというと、我々から見ると取材した内容の中で、最初からそういう目的を設定して、導入を検討されたんですか、導入したんですか、という話がなんとなく途中で変わって、成功のハードルがどんどん下がってきているような話もちらほらあったりして。お書きいただいたところで「保管の製品と自動倉庫の空間の不一致」とか、「最終的に採算が合わず発注間際で断念した」とか、この辺りの意見が複数見受けられたので、これは代表的な意見だなと思ってここに書いておきました。
永田さん、どうでしょう。導入にあたって最初の検討するときの思いと、それを実際に進めていく中で、会社の中での事情といいますか、つまり上層部との意見の食い違いだとか、いろんなことがハードルになってきますよね。
<永田>
そうですね。自動化は仕入れできないとおわかりいただきたい。自動化を仕入れようとしている認識が、私は非常に多いです。モノを買うように自動化を仕入れるという思考回路は見直さなければいけません。例えば物流業務の委託と内製っていう問題があるのですが、物流業務を仕入れるように委託の選択をとる会社は、自動化を仕入れるという方法をとりがちなんです。企業の中の思考回路がそうなっているのであれば、自動化という「パッケージ」を仕入れることはやめていただいて、自動化はあくまで「ツール」と割り切って、もう一度お考えいただきたいと思います。
<赤澤>
ありがとうございます。要するにロボットを購入することがだんだん目的化してくるケースが、失敗に近づいていくような事例に見受けられるわけですよね。ここからですね。今ご紹介したような導入意向、導入のニーズの状況を踏まえて、お話しを進めていきたいと思います。
最初に、皆さんにもぜひお考えいただきたいのは、先ほどから永田の方から飛び出してきている言葉です。「何のために物流ロボットって導入するんですか」について考えてみたいと思います。これを考えるにあたって、永田さん、どうですか。やはり目的と手段について情報を整理する必要があるんじゃないかということですよね。
 物流ロボットを導入するうえで整理しておきたい「目的」と「手段」
物流ロボットを導入するうえで整理しておきたい「目的」と「手段」
<永田>
例えば、とある大企業の内部だけのセミナーでの話ですが、研修部とか人事部あたりがものすごく反対していまして。何を憂いているかといいますと「人が足らなくなって自動化。属人業務を排除するために自動化。属人=高コストだから自動化」というところで始めたにもかかわらず、自動化が進みすぎたり、ロボットが出来が良すぎたりしてしまうと人間を凌駕してしまうのではないか、追いやられるのではないかということを危惧して、敵視するような感情が蔓延するケースもあります。「そもそも御社は一体何のために自動化を求められたのですか」という問いに対して、部門によって違う、ケースによって違う、現場によって違う、ということがありますので、まずは一枚岩となって、一緒にしてください。自動化を多面的に捉えるのは良くないです。ここから、まず整理していただきたいと思います。
<赤澤>
なるほど、ありがとうございます。ロボット導入の動きが企業の中で始まるときに、いろんな動き出し方があると思います。最近は企業の中で「ロボットを導入しなければ、そこから発想をスタートしなければ進んでいかない」といった強迫観念に駆られている経営者の方を見ることが増えてきた気がしています。
<永田>
バイパス手術みたいなもので、あるところからあるところまでを受け止めて、そこに自動化みたいな対応を入れて、流れを良くする。そもそも人間にそういう外科手術的なことをすると、当然ながら血が流れて、会社によっては出血多量でおかしくなったりする。なので、いきなりの外科手術は無理なんだ、ということが実態としてあります。
もうひとつは基本的には、現既存業務と並行させるっていう時間が必ず必要です。それは企業体力とか当然、二重業務になる期間も出てくるので、そこをどう考えるかの選択肢をたくさん作った上で、テーブルを囲んでいただかないとならないと思います。
<赤澤>
そうですね。はい、ありがとうございます。要するに、物流ロボットに何を求めるのかをしっかりとお考えいただくということです。先ほど話がありましたけど、「自動化」を買うという発想よりも、もう一歩進めて「時間」を買うみたいな要素がありますよね。あまりを多く求めすぎない方がいいんじゃないかな、みたいなことがこの後の話で実感いただけるんじゃないかと思います。
 企業のロボット導入失敗例に見る「最初から成功することはない」という現実
企業のロボット導入失敗例に見る「最初から成功することはない」という現実
<赤澤>
次に話を進めてみますね。今回、失敗事例の追求をこの講演会の内容に決めさせていただいたのですけれども、そのきっかけになったのが、数年前に取材させていただいたある関西の通販企業ですね。関西の方に聞くと「あそこは自社で物流のオペレーションをやっていて、なかなか手堅い物流の運用していると知られてる」といわれる会社でした。
ここが京都に物流センターを立ち上げるということで、2015年ぐらいに動きが始まって、20年前後に当時としては、比較的先進的な自動倉庫を導入されました。夏前に導入して、その夏の繁忙期に合わせてフル稼働、と目論んでいらっしゃったわけです。その会社は上場企業だったのですが、結果的になぜか出荷能力がロボットを導入したことによって70%ぐらい下がって、もうどうしようもないと、株主に対して報告しなければいけない事態になってしまったことがありました。物流のオペレーションでは、非常に定評のある会社だったのですけれども、何でこんなことが起こったんだろうなと、当時永田といろんな意見交換をしたことがあるんです。永田さん、覚えていますか。
<永田>
当然企業情報なのですべて開示されなかったわけですが、サプライヤーとの関係も大事にされていたので、情報が出てこなかったんですけれども。たぶん商品マスターの登録のところでつまずいたのではないかと。機械なので人間同士のように「これちょっとやっておいてくれ」とか「これちょっと不具合出てるから直しておいてくれ」という融通が利かないんです。
いかほど優れた機械であっても「1+1」を入れないと動かないといった部分の不整備だったのではないかと。つまり業態がEC(電子商取引)なので。物流業務でEC業務ほど簡単なものってないと思うんですよ。でも単純で浅いので1回トラブルが出ると、もうバイパスを補完しようがなくて、結局出荷が止まってしまったということだと思います。
<赤澤>
ありがとうございます。取材した私の当時の感想としては、この会社確かに数字にはっきりとトラブルが反映されてしまっていたので、公表しないわけにはいかなかったのだと思います。けど、それがものすごく良かったなと思っています。それによって、検証されたわけです。
「何で失敗したのか」会社を挙げて検証する動きになられました。そのときに私が違和感を持ったのは、当時今から5年ほど前ですが、メーカー側がその失敗事例を隠したがるんですよ。我々メディアに対して、そういう動きに出るのは、なんとなくわかるんですけれども、その企業に対しても「そういう情報をあまりおおっぴらにするのは」という感じで。その会社としてはですね「失敗の原因を徹底追求して次の改善につなげていきたい、何とか使いこなす方向に持っていきたい」と思うんだけれども、供給元からの「遠慮してもらえないか」みたいな空気感が結果的には足を引っ張ってしまったと思います。結構ロボットを使いこなすまでの時間が延びてしまったと感じました。
何でこんな話をしているかというと、これがその後の物流企業のロボット導入にかなり大きな影響を与えたんだろうなと、感じるからです。やはりあの記事で、あの事例を読んだときに、感じるものがあって「結局ロボット導入を決めて、いきなり成功する会社ってまずないんだ、必ず何かつまずいてるんだ」と。どこに失敗していくのか、というその情報とか対応、ノウハウを会社の中に蓄積しているから、うちは今こうやって使いこなせているんだよ、とおっしゃる取材先が増えてきたなと思っております。そういう動きが一般化するにつれて、メーカー側の対応も変わってきたように思います。なので最初の事例として取り上げました。
第3回は、ロボットに求める「正確さ」について考えます。
■物流ロボット特集